前の10件 | -
ゆくとしくるとし
テレビの画面にでてきたのは二人組の漫才師「ゆくとし くるとし」
「なあ。今年はどんな年だった?」
「僕には365日だったかな」
「かなじゃない。誰にとっても1年は365日なんだ」
「地球も大変だ。365回もくるくる回るんだから……365回転ルッツだ」
「・・・?」
「地球は…後ろ向きに氷上をスーッと滑りながら跳び上がりのモーションに入る。次の瞬間。片足のトウを突き回転しながらジャンプするんだ。1年の間に365回転だ」
「くるくると?」
「そう。大晦日の真夜中に1度休んで元旦の朝にはまた1回転目から始めるんだ…ふう、タフだぜ地球は」
「初日の出くるくる。目が回らないのか?」
「大丈夫。地球はベテラン選手だ。かなりのベテランだ」
「ベテランの地球がくるくると」
「そう。時速1700kmで」
「シートベルトは?」
「もちろん必要だ。アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)のない地球は急ブレーキを踏むかもしれない」
「そんな・・・」
「地球がブレーキを踏んでも安全なように…地軸は傾いているんだ」
「マエストロが振る指揮棒のように?」
「そう。地軸の傾きがソナタ形式で奏でる第4楽章クライマックスが大晦日なんだ」
「ブラボー」
「アンコールはないけどね」
「毎日は二度と戻らない」
「Every day is a new day」
「年老いた漁師は今日も海へと向かう・・・」
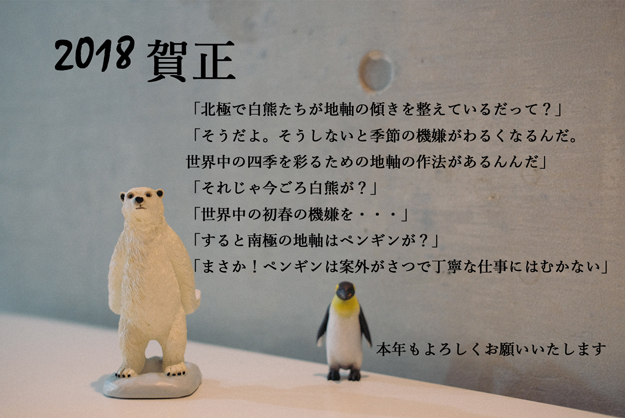
***
年老いた自転車乗りはレースから足を洗って数年がたちました。
今年はグランフォンド(山岳コースをメインとした長距離系ロングライドイベント)に5回参加しました。
2017年9月17日開催の「八甲田グランフォンド」はきつかった。
台風18号が東北を直撃する前日。雨は降らなかったが強風の中を走った。
どこを?
往路:青森公立大学(青森市)→八甲田山登り(萱野高原〜酸ヶ湯温泉方面)→八甲田山下り→奥入瀬渓流上り下り→十和田湖
復路:違うルートで十和田湖→奥入瀬渓流上り下り→八甲田山登り(谷地温泉〜田代平〜八甲田温泉)→八甲田山下り→青森公立大学(青森市)
強風区間横風で側溝に落下した人や……etc.
走行距離は140㎞とそんなに長くはない割に
獲得標高が2807mなので足が削れらました(汗)

八甲田酸ヶ湯温泉エイドステーション

十和田湖エイドステーション
** *
2016年03月マルがひょいと出て行った。
2016年07月保護猫2匹がやってきた。
リビア山猫のようなキジトラは雌猫「メメ」
気むずかしくてなかなか近寄ってこないが猫じゃらしで遊びたくなると大声で鳴いて
「遊んで〜遊んで〜」と要求する。
メンドクセーけど可愛い娘。
2017年12月で2歳6ヶ月
サバシロ顔面ハチワレ雄猫「ニケ」
人なつこくってうるさくっていつも動き回っている。
ネズミの玩具を飲み込んで腸閉塞になってるのに診察のとき気持ちよさそうにお腹を触られていた。
メンドクセーけど可愛い息子。
2017年12月で1歳7ヶ月




***
ここからは宣伝です。
ステマでも釣りでもありません。
完全無欠な宣伝です。堂々とした誘導です。
ボクの畏友「金井真紀」(http://uzumakido.com)
彼女の最新刊「パリのすてきなおじさん」が好評です。
『難民問題、テロ事件、差別の歴史……。 世界は混沌としていて、人生はほろ苦い。 だけどパリのおじさんは、今日も空を見上げる。 軽くて、深くて、愛おしい、おじさんインタビュー&スケッチ集 中島京子さん推薦! 「パリは人種のるつぼ、おじさんのサラダボウルだ。 読めば21世紀の隣人の姿が浮かび上がり、 クスクスも赤ワインも、より味わい深くなる。」』(内容紹介)
ああ。
かつてはボクの駄文ブログにイラストを描いてくれたフリーライター兼イラストレーターが
今じゃ著書5冊の作家兼絵師と職業欄が漢字でうまるあっぱれな展開になっております。
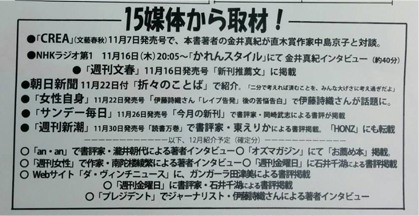

各誌に素敵な書評が載ったのですけど著作権もあるのでここでの紹介は控えます。
10月24日発売で既に三刷の展開となってますが・・・
発売当初は不安にかられた作家はボクにアマゾンレビューへの書評投稿を依頼してきまた。
以下は投稿者名「まる」で書いたボクの駄文です。
【著者の得意技連発にニヤニヤ】
本著「パリのすてきなおじさん」でも相変わらず各章のタイトルにしびれる。
前著『はたらく動物と』で僕が気に入ったのは
盲ろうの方と盲導犬の章に付されたタイトル
『自由とは ビールを 飲みにいく夜道』 だった。
暗い夜道を相棒盲導犬となんの気後れも気張りもなくフラリとビールを飲みに行く軽やかな描写に揺れる風の心地を感じた。
今回は各章のタイトルが「パリのすてきなおじさん」たちが著者の前で発した一言になっている。
「二分考えれば済むことを、みんな大げさに考え過ぎだよ」
「人生を学んでいるあいだに手遅れになる。大事なことを後回しにするな。」
「生まれ育った国にはもう帰らない。だからこそぼくは母国語を学ぶ」
「どこにだって、いいやつもいるしバカもいる。」
「選択肢はひとつ。前を向いて生きていくしかない。」
「大事なのは将来ではない。いまですよ。」
タイトルが目に飛び込む。
著者がパリで採取したおじさんたちの言葉。
インタビューされた”おじさん”はどこでこの科白を言うんだろ?
どんな話しの内容で、どんな展開で、どんな表情で言うんだろ?
ドキドキワクワクしながら読み進める。
その台詞は宗教でもなく哲学でもなく好きなことを好きなようにやってきた人間の内部で醸成された言葉。好きなことを続けてきた日々。ある者は軽やかに、ある者は地道に、ある者は頑固にやってきた。
ふふ。好きなことをやってこないと添えられた絵(ポートレイト)のような顔にはならないんだな。読者はその顔(絵)を見るだけでも眼福ですぞ。
ああ……世界はたくさんの色でみちている。
まさしく色々だ。
そして世界は色々な人生でみちている。
ドキドキワクワクニヤニヤして頁をくる指が止まる。
おじさんの話を聞くことでみえてくる地域と国の問題、歴史と移民の問題。
第二次大戦下のフランスでユダヤ人が迫害を受けていただなんて今回本書で初めて知った。
生存者の口から語られるその苛烈。
最終章。
通りがかりの書店で俳句本に目をとめたためにであったベトナム人の方。
その口から語られるベトナム戦争に翻弄された自らと家族の半生。
どうしてこういう方と巡り会う「出会いがしら」を著者はたぐりよせるのだ?
まるで操られているかのような偶然だ。
松茸狩り名人のような、昆虫採取の天才少年のようなその特殊能力のおかげで
「パリのすてきなおじさん」の人生の片々から世界の多様性を疑似体験できるのが本書です。
「どこにだって、いいやつもいるしバカもいる。」けど
「いいやつ」のほうがちょっとだけど多いはずだよ、きっと世界は。
そう思える幸せをかんじる本でした。
以上を投稿した2日後に彼女から嬉しいメールがきた。
『朝から担当編集者が騒いでるよ。
まるさんっていう人がめちゃめちゃいいコメントを書いてくれてます!
とても勉強になります!
だって。
猫まる、人まる、ともに感謝。』
えっへん(笑)
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/パリのすてきなおじさん-金井-真紀/dp/4760149112/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1514677643&sr=1-1&refinements=p_27%3A金井真紀
***
今年の10月から毎日聞いている「GoGo Penguin」
イギリスのピアノ・ベース・ドラムズの3人組
一応ジャズピアノトリオということだけど・・・
3枚目のアルバムがブルーノートから発売されたけど・・・
2018年2月にブルーノート東京でライブやるけど・・・
ジャズじゃくくれないとっても素敵な音楽です。
変拍子の波にたゆたう快感よ。
GoGo Penguin
" Hopopono " (Official Video)
https://youtu.be/-UtAV_azaBc
" Garden Dog BBQ " Live Session
https://youtu.be/6HtuAh62Dc4
So Long
Chapter #1 水分70%
目覚めたときにここは舟の中なんだと言われればそんな気になってしまうような細長
い部屋だ。
南向きの窓からみえる雑木林がさわさわと風に揺れている。不規則な形をした緑色の
生物がゆっくり呼吸をしているようだ。
二人の男は窓際に置かれたテーブルで向き合って座っていた。二人とも中年と呼ばれる
ようになってからたっぷり十年は経っているような年嵩だ。
窓ガラスを通して入る陽の光でカップのコーヒーから上る湯気が銀色に輝いた。
トマトと胡瓜のサンドイッチを一口囓りビールを飲むと顔を上げた男はモーザン。サン
ドイッチが不味いのか、ビールが不味いのか、それとも機嫌がわるいのか・・強張った
顔つきだ。
煙草の煙を吐きだしウイスキー・ソーダを飲んでいる男がララファン。ウイスキー・ソーダ
が美味いのかそれとも機嫌が良いのか雑木林をみている顔はほころんでいる。
「どうしてさ・・」ララファンがぼそりと言葉を床にこぼした。
モーザンはサンドイッチで口をいっぱいにし、返事のかわりに怒り肩から不穏を放った。
熟れすぎたトマトのような不機嫌が部屋の中を流れた。
ララファンは焼き茄子のような呑気で不機嫌を払いのけ話しを続けた。
「あの映画・・『明日に向かって撃て』さ。ラストはあそこで急に終わったんだろ?」
サンドイッチを食べる手を止めたモーザンはやれやれという表情で答えた。
「あの先に起こることは誰でも分かるからカットしたんだろ」
「主人公の二人は助からない?」ララファンは煙草の煙を細く長く吹き出した。
「助かると思うか・・」モーザンはサンドイッチの皿を脇へよけテーブルを右拳で叩いた。
「奇跡は起きない?」
「だろうな・・・」
「今の俺たちは・・?」
「もっとやばいな」
「でも命まではとられないだろ?」
「あのな。連中との契約には・・失敗した場合の担保は腎臓二個って書いてあるんだ」
「それが?」
「知らないのか。人間はな腎臓を二個取られたら生きていられないんだ」
「たった二個で?」
「二個で全部だ」
「サーカス団へ売られた腎臓は練習をつんで空中ブランコ乗りになる。サーカス団の
花形スター”そら豆兄弟”の誕生だ」
「・・・・・」
「じゃあさ。こんなのはどう?
棚から落ちてきたぼた餅を拾って・・猫が持っている小判と交換して・・漁夫のリー君に
小判を渡して二人乗りの蜘蛛の糸を手配してもらって。
こんな町とは今日でおさらばさ。なんてのは?」
「黙れ!」
「それじゃシンプルにさ・・ヒーローが現れて助けてくれるとか?」
「ヒーローは・・口うるさい中年男を助けない」
「・・・それは差別だ」
「あのな。ヒーローが現れて一発逆転なんてのはな、めったに起きないんだ」
モーザンは立ち上がり冷蔵庫から新しい缶ビールを出して口へ運んだ。
「一発で無理なら三発打てば逆転できるかも」ララファンは落花生の皮を割るような
乾いた声でけろりと言った。
「いいか。こんなくそったれな状況に首までつかっているときに・・ふざけるな」
モーザンは声を投げつけた。
「サイコロを振ったのはあんただ」ララファンは苦い笑いをぽんっと放った。
「出た目に乗ったのはおまえだ」
「ああ。俺はあんたと遊ぶのが好きだからな」
「それが・・このざまだ。どこで状況が狂ったんだ?」モーザンはテーブルの脚を蹴った。
テーブルの上で跳ねたウイスキー・ソーダのグラスをすくいあげて飲むとララファンは
笑いながら言った。
「想定外のことは起きるものさ」
「この計画に破綻はなかったはずだ」
「十二時過ぎにガラスの靴を置き忘れる作戦をたてても、王子は興味がなかったかもしれない」
「準備にぬかりはなかった」
「あんたは欲張りなのさ。もっともっとと無茶なオプションを計画に盛り込む。
エスキモーに冷蔵庫を売ろうとするような無茶だ」
「貪欲はな・・現代の美徳なんだ。無欲で謙虚なんてのは砂漠の砂より価値がない」
モーザンはビールを飲み終え拳で缶を潰すと話を続けた。
「俺が貪欲ならお前はなんだ?いつも楽しけりゃいいっていういい加減な生き方だ」
「いい加減じゃない、良い加減だ。俺は良い湯加減のような人間なのさ。
いいか、人間の本質は嬉しい・楽しい・気持ちいいだ」
「お前が手を抜いたんだ。。だから完璧だった計画も実行段階でクラックがはいった」
「ほんとは人間の本質は水分60%だ。猫は水分70%で蜜柑は水分85%だ。
だから猫や蜜柑はみずみずしい存在なんだ」
「は?」
「だから。蜜柑のような存在は人間じゃくて、猫なんだ」
「そんなことはどうでもいい。おまえがガラスの靴に王子好みの香水をふりかけるのを
忘れたから計画にクラックがはいったんだ」
「クラックがはいってスタックして身動きできなくなったら抜け出す方法を考えりゃいい」
「どこだ・・この計画のどこに間違いがあったんだ?」
「間違った答えを添削するより、新しい解答を作っちゃえばいい」
「そんな簡単じゃないんだ!」
煙草の箱をつかんだモーザンはララファンの顔めがけて投げた。椅子を回転させてよけたララファンは向きなおると笑って言った。
「考えるのはあんただ。俺はそのアイデアに乗って楽しむ」
「・・・・・」
青いインクのような憂鬱を両手で振り払うと顔から笑いを消したララファンが喉を
ごくりと鳴らして低い声で言った。
「いいか。アイデア出しはあんただ。計画立案はあんたで、実行は俺だ。
命懸けで考えろ。そのあとは技術屋の俺にまかせろ。
このくそったれの泥沼からあんたを引きずり出してやる。命懸けでな」
そのときだ。部屋のなかに陽をたっぷり浴びた檸檬色の風が吹いた。
窓の隙間から一匹の猫が入ってきて蜜柑が転がるような軽やかさで床に飛びおりた。
サバトラ柄の毛並みのオス猫だった。
尻尾を上にたててゆっくりと歩く姿はふてぶてしくもあり老齢のおもむきだが緑の瞳は
美しく輝き背中から後ろ足へのラインが柳のようにしなやかに揺れた。
テーブル近くまで来ると歩くのをやめうずくまった。
身体を内側に丸めると後ろ足で首を掻きはじめた。
ひとしきり首を掻いておおきな欠伸をすると首輪から紙片が落ちた。木枝に結ぶおみくじ
のように畳んで折ってある紙片だった。
前足で紙片を前へ前へと押してララファンの足元まで運ぶと目を細めて笑っているような
顔になった。
紙片を拾い上げて見ているララファンにむかって「なんだよそれ?」モーザンが声を投げた。
ララファンは机の上に紙を広げて置いた。
紙には下手くそなひきつった(まるで爪で書いたような・・)平仮名でこう書かれていた。
『やりかたはみっつしかない
ただしいやりかた
まちがったやりかた
おまえのやりかただ』
二人はにやりと笑った。
数秒後。
笑いが爆発した。
「だ、そうだ!」笑いやんだララファンが言った。
「ああ。俺のやりかたでいくしかないんだな」モーザンはまだ笑っていた。
ゆらりと風が吹き周囲の景色が膨らんで見えた。
猫はまた大きな欠伸をすると後ろ足で首を掻き目を細めた。
檸檬色の風が背中の毛を波のように揺らした。
猫は身体を内側に曲げ丸くなり後ろ足だけ伸ばして眠っている。
大きな疑問符のような形になって眠っていた。
春とはいってもまだ風はまだ肌寒い。ララファンが大きな疑問符に毛布をかけると
モーザンが呟いた。
「こんなのはどうだ?」
「いいんじゃないか」にやりとララファンが笑った。
「まだ話してねえよ」ぐすりとモーザンが笑った。
寝返りをうった猫は身体の内側で前足と後ろ足を繋げて円をつくった。
「ほら。マル・・だってさ。猫もそれで良いって賛成してるぜ」ララファンが軽やかに言った。
「だから。まだ話してねえって」モーザンはまだ笑っていた。
猫が大きな欠伸をするとまた陽を浴びた檸檬色の風が部屋のなかを吹き渡った。
景色の輪郭と色がすこしにじんだ。
Chapter #2 so long
ここから始まる報告はフィクションではなく事実です。
(センスのない悪ふざけではなく……残念ながら事実です)
2016年03月16日夕刻のことです。
マルが旅立ちました。
我慢せず気ままに機嫌良く毎日を謳歌した17歳10ヶ月でした。
マルは2011年6月に糖尿病と診断され、それから朝・夕2回インスリンを注射してきました。
この1年で5.2キロの体重が3.9キロまで減りましたがマルは体重減少なぞどこ吹く風・・
『それがどうかしたか』とばかり、食べ・眠り・動き・食べ・眠りの機嫌の良い毎日でした。
2〜3ヶ月前から徐々に動く量が減ってきてもまあ寄る年波もあるのさと思っていました。
なんといっても旅立つ2日前でさえ朝には階段を昇り2階で眠る僕を起こしに来ましたし、
僕が座るソファへジャンプして登ってきたほどですから。
かつてはインスリンを朝3単位・夕3単位注射していのが徐々に減量し、昨年秋からは
朝・夕1単位となりました。
インスリンを減少していったのに今年2月初旬からは間歇的な低血糖発作に3回みまわれました。
インスリン製剤の変更や用量を減量調節することで対応し、2月下旬から2週間以上は発作が
なかったのですが……。
3月13日の発作はインスリン減量前の2月よりひどい発作で。それでも注射器で砂糖水を口へ
入れ飲ませると元気になりましたので安堵したのですが……。
15日には希釈インスリン0.33(1/3)単位という少量でも低血糖発作が出現し一旦は砂糖水
で回復したのですが……。同日入院し点滴もしましたが体調は回復せず翌16日夕刻に自宅で
見守るため退院となりました。
19時30分でした。マルはゆっくり呼吸を止めました。
僕のお腹の上で眠るのが好きで、妻の膝の上で休むのが好きな猫でした。
最後も妻のその膝の上で休んだまま眠りにつきました。
苦しそうなそぶりもみせず手早く身支度を整えた慌ただしい旅立ちでした。
マルらしいちょっと自分勝手で少しそっけのない幕引きでした。
Chapter #3 幕間のご挨拶
茜色の夕焼け雲が雑木林の上へながれてきたころ、2人は台所にいた。
モーザンは米を手早く研ぎ炊飯器にセットした。その中へ冷蔵庫で眠っていたサンマ蒲焼き缶詰を汁ごと全部入れ、さらには昆布茶と梅干しを入れた。炊飯器のスイッチを押すと、トマトジュースを飲んだ。
ララファンは大根とオクラをマヨネーズとカラシであえたサラダをつくった。
50分後。
炊き込みご飯を大皿へ盛るとその上にきざんだ青葱をのせた。互いに湯気をかき分け大皿から自分の小皿へ移した。
それを2人はビールを飲みながら無言で食べた。
猫のような速度と猫のような集中力で食べた。
食べ終えた二人は食後の運動代わりに始めるかというような雰囲気で言い合いを始めた。
「おまえは好き勝手やってばっかりのふざけたやつだ!」モーザンが声を張り上げた。
「そういうあんたは欲張りだ!」ララファンが声を張り上げ応じた。
窓際のラジオではボブ・ディランが『I shall be released』を歌っていた。
床に寝そべっていた猫が新玉葱のような甘えた声で鳴いた。
***
マルは我慢をしないで好き放題に行動する猫でした。いつでも朗らかで機嫌良く行動する
猫でした。
そして遊びにも食餌にも貪欲で欲張りな猫でした。手にしたいものにはすぐに立ち上がり
猫パンチを繰り出しました。
僕がマルから教わったこと。
良い機嫌で『とても楽しい(ララファン( lot of fun ))』と生きることが大切なんだってこと。
そして『もっともっと(モーザン( more than ))』と欲張りになること、
満足して立ち止まらないこと。
そしてそして『オレはオレのやり方でやる。お前はお前のやり方でやれ』でした。
ああ。マルはつくづくビートニクでロックな猫でした。
今回はマルの『幕引きのご挨拶』になるような物語にならないかなと思い書き始めました。
それでも書いているうちにこう思いました。
マルの新しい写真は載せることはもうできないけれど、物語の中になら何度でもマルは登場できる。
そこで。
今回は幕引きじゃなくて、マルからの『幕間のご挨拶』ってことにさせて頂くことと相成りました。
それでは。
マルからの幕間の挨拶です。
『おたのしみはこれからだ』

2016-02-11

2016-02-17

2016-02-28

2016-03-06

2016-03-09

2016-03-09
大滝詠一 『夢で逢えたら』

目覚めたときにここは舟の中なんだと言われればそんな気になってしまうような細長
い部屋だ。
南向きの窓からみえる雑木林がさわさわと風に揺れている。不規則な形をした緑色の
生物がゆっくり呼吸をしているようだ。
二人の男は窓際に置かれたテーブルで向き合って座っていた。二人とも中年と呼ばれる
ようになってからたっぷり十年は経っているような年嵩だ。
窓ガラスを通して入る陽の光でカップのコーヒーから上る湯気が銀色に輝いた。
トマトと胡瓜のサンドイッチを一口囓りビールを飲むと顔を上げた男はモーザン。サン
ドイッチが不味いのか、ビールが不味いのか、それとも機嫌がわるいのか・・強張った
顔つきだ。
煙草の煙を吐きだしウイスキー・ソーダを飲んでいる男がララファン。ウイスキー・ソーダ
が美味いのかそれとも機嫌が良いのか雑木林をみている顔はほころんでいる。
「どうしてさ・・」ララファンがぼそりと言葉を床にこぼした。
モーザンはサンドイッチで口をいっぱいにし、返事のかわりに怒り肩から不穏を放った。
熟れすぎたトマトのような不機嫌が部屋の中を流れた。
ララファンは焼き茄子のような呑気で不機嫌を払いのけ話しを続けた。
「あの映画・・『明日に向かって撃て』さ。ラストはあそこで急に終わったんだろ?」
サンドイッチを食べる手を止めたモーザンはやれやれという表情で答えた。
「あの先に起こることは誰でも分かるからカットしたんだろ」
「主人公の二人は助からない?」ララファンは煙草の煙を細く長く吹き出した。
「助かると思うか・・」モーザンはサンドイッチの皿を脇へよけテーブルを右拳で叩いた。
「奇跡は起きない?」
「だろうな・・・」
「今の俺たちは・・?」
「もっとやばいな」
「でも命まではとられないだろ?」
「あのな。連中との契約には・・失敗した場合の担保は腎臓二個って書いてあるんだ」
「それが?」
「知らないのか。人間はな腎臓を二個取られたら生きていられないんだ」
「たった二個で?」
「二個で全部だ」
「サーカス団へ売られた腎臓は練習をつんで空中ブランコ乗りになる。サーカス団の
花形スター”そら豆兄弟”の誕生だ」
「・・・・・」
「じゃあさ。こんなのはどう?
棚から落ちてきたぼた餅を拾って・・猫が持っている小判と交換して・・漁夫のリー君に
小判を渡して二人乗りの蜘蛛の糸を手配してもらって。
こんな町とは今日でおさらばさ。なんてのは?」
「黙れ!」
「それじゃシンプルにさ・・ヒーローが現れて助けてくれるとか?」
「ヒーローは・・口うるさい中年男を助けない」
「・・・それは差別だ」
「あのな。ヒーローが現れて一発逆転なんてのはな、めったに起きないんだ」
モーザンは立ち上がり冷蔵庫から新しい缶ビールを出して口へ運んだ。
「一発で無理なら三発打てば逆転できるかも」ララファンは落花生の皮を割るような
乾いた声でけろりと言った。
「いいか。こんなくそったれな状況に首までつかっているときに・・ふざけるな」
モーザンは声を投げつけた。
「サイコロを振ったのはあんただ」ララファンは苦い笑いをぽんっと放った。
「出た目に乗ったのはおまえだ」
「ああ。俺はあんたと遊ぶのが好きだからな」
「それが・・このざまだ。どこで状況が狂ったんだ?」モーザンはテーブルの脚を蹴った。
テーブルの上で跳ねたウイスキー・ソーダのグラスをすくいあげて飲むとララファンは
笑いながら言った。
「想定外のことは起きるものさ」
「この計画に破綻はなかったはずだ」
「十二時過ぎにガラスの靴を置き忘れる作戦をたてても、王子は興味がなかったかもしれない」
「準備にぬかりはなかった」
「あんたは欲張りなのさ。もっともっとと無茶なオプションを計画に盛り込む。
エスキモーに冷蔵庫を売ろうとするような無茶だ」
「貪欲はな・・現代の美徳なんだ。無欲で謙虚なんてのは砂漠の砂より価値がない」
モーザンはビールを飲み終え拳で缶を潰すと話を続けた。
「俺が貪欲ならお前はなんだ?いつも楽しけりゃいいっていういい加減な生き方だ」
「いい加減じゃない、良い加減だ。俺は良い湯加減のような人間なのさ。
いいか、人間の本質は嬉しい・楽しい・気持ちいいだ」
「お前が手を抜いたんだ。。だから完璧だった計画も実行段階でクラックがはいった」
「ほんとは人間の本質は水分60%だ。猫は水分70%で蜜柑は水分85%だ。
だから猫や蜜柑はみずみずしい存在なんだ」
「は?」
「だから。蜜柑のような存在は人間じゃくて、猫なんだ」
「そんなことはどうでもいい。おまえがガラスの靴に王子好みの香水をふりかけるのを
忘れたから計画にクラックがはいったんだ」
「クラックがはいってスタックして身動きできなくなったら抜け出す方法を考えりゃいい」
「どこだ・・この計画のどこに間違いがあったんだ?」
「間違った答えを添削するより、新しい解答を作っちゃえばいい」
「そんな簡単じゃないんだ!」
煙草の箱をつかんだモーザンはララファンの顔めがけて投げた。椅子を回転させてよけたララファンは向きなおると笑って言った。
「考えるのはあんただ。俺はそのアイデアに乗って楽しむ」
「・・・・・」
青いインクのような憂鬱を両手で振り払うと顔から笑いを消したララファンが喉を
ごくりと鳴らして低い声で言った。
「いいか。アイデア出しはあんただ。計画立案はあんたで、実行は俺だ。
命懸けで考えろ。そのあとは技術屋の俺にまかせろ。
このくそったれの泥沼からあんたを引きずり出してやる。命懸けでな」
そのときだ。部屋のなかに陽をたっぷり浴びた檸檬色の風が吹いた。
窓の隙間から一匹の猫が入ってきて蜜柑が転がるような軽やかさで床に飛びおりた。
サバトラ柄の毛並みのオス猫だった。
尻尾を上にたててゆっくりと歩く姿はふてぶてしくもあり老齢のおもむきだが緑の瞳は
美しく輝き背中から後ろ足へのラインが柳のようにしなやかに揺れた。
テーブル近くまで来ると歩くのをやめうずくまった。
身体を内側に丸めると後ろ足で首を掻きはじめた。
ひとしきり首を掻いておおきな欠伸をすると首輪から紙片が落ちた。木枝に結ぶおみくじ
のように畳んで折ってある紙片だった。
前足で紙片を前へ前へと押してララファンの足元まで運ぶと目を細めて笑っているような
顔になった。
紙片を拾い上げて見ているララファンにむかって「なんだよそれ?」モーザンが声を投げた。
ララファンは机の上に紙を広げて置いた。
紙には下手くそなひきつった(まるで爪で書いたような・・)平仮名でこう書かれていた。
『やりかたはみっつしかない
ただしいやりかた
まちがったやりかた
おまえのやりかただ』
二人はにやりと笑った。
数秒後。
笑いが爆発した。
「だ、そうだ!」笑いやんだララファンが言った。
「ああ。俺のやりかたでいくしかないんだな」モーザンはまだ笑っていた。
ゆらりと風が吹き周囲の景色が膨らんで見えた。
猫はまた大きな欠伸をすると後ろ足で首を掻き目を細めた。
檸檬色の風が背中の毛を波のように揺らした。
猫は身体を内側に曲げ丸くなり後ろ足だけ伸ばして眠っている。
大きな疑問符のような形になって眠っていた。
春とはいってもまだ風はまだ肌寒い。ララファンが大きな疑問符に毛布をかけると
モーザンが呟いた。
「こんなのはどうだ?」
「いいんじゃないか」にやりとララファンが笑った。
「まだ話してねえよ」ぐすりとモーザンが笑った。
寝返りをうった猫は身体の内側で前足と後ろ足を繋げて円をつくった。
「ほら。マル・・だってさ。猫もそれで良いって賛成してるぜ」ララファンが軽やかに言った。
「だから。まだ話してねえって」モーザンはまだ笑っていた。
猫が大きな欠伸をするとまた陽を浴びた檸檬色の風が部屋のなかを吹き渡った。
景色の輪郭と色がすこしにじんだ。
Chapter #2 so long
ここから始まる報告はフィクションではなく事実です。
(センスのない悪ふざけではなく……残念ながら事実です)
2016年03月16日夕刻のことです。
マルが旅立ちました。
我慢せず気ままに機嫌良く毎日を謳歌した17歳10ヶ月でした。
マルは2011年6月に糖尿病と診断され、それから朝・夕2回インスリンを注射してきました。
この1年で5.2キロの体重が3.9キロまで減りましたがマルは体重減少なぞどこ吹く風・・
『それがどうかしたか』とばかり、食べ・眠り・動き・食べ・眠りの機嫌の良い毎日でした。
2〜3ヶ月前から徐々に動く量が減ってきてもまあ寄る年波もあるのさと思っていました。
なんといっても旅立つ2日前でさえ朝には階段を昇り2階で眠る僕を起こしに来ましたし、
僕が座るソファへジャンプして登ってきたほどですから。
かつてはインスリンを朝3単位・夕3単位注射していのが徐々に減量し、昨年秋からは
朝・夕1単位となりました。
インスリンを減少していったのに今年2月初旬からは間歇的な低血糖発作に3回みまわれました。
インスリン製剤の変更や用量を減量調節することで対応し、2月下旬から2週間以上は発作が
なかったのですが……。
3月13日の発作はインスリン減量前の2月よりひどい発作で。それでも注射器で砂糖水を口へ
入れ飲ませると元気になりましたので安堵したのですが……。
15日には希釈インスリン0.33(1/3)単位という少量でも低血糖発作が出現し一旦は砂糖水
で回復したのですが……。同日入院し点滴もしましたが体調は回復せず翌16日夕刻に自宅で
見守るため退院となりました。
19時30分でした。マルはゆっくり呼吸を止めました。
僕のお腹の上で眠るのが好きで、妻の膝の上で休むのが好きな猫でした。
最後も妻のその膝の上で休んだまま眠りにつきました。
苦しそうなそぶりもみせず手早く身支度を整えた慌ただしい旅立ちでした。
マルらしいちょっと自分勝手で少しそっけのない幕引きでした。
Chapter #3 幕間のご挨拶
茜色の夕焼け雲が雑木林の上へながれてきたころ、2人は台所にいた。
モーザンは米を手早く研ぎ炊飯器にセットした。その中へ冷蔵庫で眠っていたサンマ蒲焼き缶詰を汁ごと全部入れ、さらには昆布茶と梅干しを入れた。炊飯器のスイッチを押すと、トマトジュースを飲んだ。
ララファンは大根とオクラをマヨネーズとカラシであえたサラダをつくった。
50分後。
炊き込みご飯を大皿へ盛るとその上にきざんだ青葱をのせた。互いに湯気をかき分け大皿から自分の小皿へ移した。
それを2人はビールを飲みながら無言で食べた。
猫のような速度と猫のような集中力で食べた。
食べ終えた二人は食後の運動代わりに始めるかというような雰囲気で言い合いを始めた。
「おまえは好き勝手やってばっかりのふざけたやつだ!」モーザンが声を張り上げた。
「そういうあんたは欲張りだ!」ララファンが声を張り上げ応じた。
窓際のラジオではボブ・ディランが『I shall be released』を歌っていた。
床に寝そべっていた猫が新玉葱のような甘えた声で鳴いた。
***
マルは我慢をしないで好き放題に行動する猫でした。いつでも朗らかで機嫌良く行動する
猫でした。
そして遊びにも食餌にも貪欲で欲張りな猫でした。手にしたいものにはすぐに立ち上がり
猫パンチを繰り出しました。
僕がマルから教わったこと。
良い機嫌で『とても楽しい(ララファン( lot of fun ))』と生きることが大切なんだってこと。
そして『もっともっと(モーザン( more than ))』と欲張りになること、
満足して立ち止まらないこと。
そしてそして『オレはオレのやり方でやる。お前はお前のやり方でやれ』でした。
ああ。マルはつくづくビートニクでロックな猫でした。
今回はマルの『幕引きのご挨拶』になるような物語にならないかなと思い書き始めました。
それでも書いているうちにこう思いました。
マルの新しい写真は載せることはもうできないけれど、物語の中になら何度でもマルは登場できる。
そこで。
今回は幕引きじゃなくて、マルからの『幕間のご挨拶』ってことにさせて頂くことと相成りました。
それでは。
マルからの幕間の挨拶です。
『おたのしみはこれからだ』

2016-02-11

2016-02-17

2016-02-28

2016-03-06

2016-03-09

2016-03-09
大滝詠一 『夢で逢えたら』

エブリシンゴナビィオーライッ

長らくの開店休業のありさまで・・いやはや汗顔の至りでございます。
天才詩人の真似をして「下ノ畑ニ居リマス」と黒板に書いて雲隠れしたつもりが・・
ふらふらとこうやって顔を出してしまいました。
それもフライングな年賀の挨拶という間抜けぶりでございます。
皆様の新年のご多幸をお祈り申し上げます!
『Evrything's gonna be alright』で機嫌よくいきたいと思っております。
***
【マルの薄皮日記(日めくりをくるように薄皮を剥ぐ日々)】
暑さのなごりもしぼんで消えた九月の中ごろだった。
ぼくの相棒サバトラ柄の雄猫マルの首に小豆のようなしこりが触れた。
10月22日 マルは全身麻酔をかけられて首右側の皮膚にできた腫瘍の摘出手術をうけた。
夕刻に病院から家に戻ると、二食分の食餌をペロリと食べボクの心配をサラリとかわし元気に歩いた。
やれやれ。
見た目は若いが十七歳の爺ちゃん猫だ、全身麻酔の手術に伴う合併症を主治医から説明されたときは随分迷ったものだが、手術していただいてよかった、そう思った。
そのときは。
23日 病院で朝から夕方まで点滴。自宅に戻ると夕食を食べず、動かなくなる。
24日 朝からなにも食べず、水も飲まなくなる。全く動かない。
ためしにマルを持ち上げてから床に置くと・・そのままへたり込む。まずいよ、これ。
顔の右側が腫れている。右前足も腫れている。手術した皮膚腫瘍は首の右側だ。腫れた顔と前足も右だ。これは術後出血による血腫じゃないのか?病院へ連れて行く。
血液検査の結果は赤血球の数値が少ない貧血だった。血小板も減少している。止血作用の血小板が消費されて減少しているのなら貧血の原因は出血だ。主治医に質問すると「手術中の出血はなかったのだし」との返答。
『術後の出血じゃないんですか?』
「可能性は低いですね」
『マルが動かなくなった原因は貧血じゃないんですか?』
「貧血の程度は重症じゃないですしね。動かなくなった原因ははっきりしないけど・・高齢だしね」
ボクはiPhoneの電卓アプリでヘマトクリットの数値を計算した。
ヘマトクリット:血液ドーピングで話題になる酸素を運ぶ赤血球の血液中の体積がヘマトクリットだ。
ボクはその数値を計算した。
手術翌日の23日のヘマトクリットは30.6だったのが、今日24日は22.0だ。
電卓で計算すると減少率は29%だ。
『ヘマトクリット22.0%が重症じゃなくたって、一日で約30%も減少したら動かなくなるんじゃないですか?』
「うーん、高齢だしね。様子をみましょう」
釈然とはしなかったが・・そのまま帰宅した。
25日 病院へ行き血液検査をするとヘマトクリットさらに減少し15.0と貧血は悪化。電卓で計算するまでもない、30.6が15.0になったんだ・・二日間の減少率は50%を超えた。
マルが動かない食べないの原因は貧血だ。
創部の再処置を依頼した。主治医は主治医が創部ステイプラーを外し 、創部を圧迫止血するように処置をした。
栄養チューブを鼻から挿入し食道へ留置してもらい、帰宅してから液体流動食の注入を開始。
排尿がないので搾乳ならぬ搾尿で排尿させる。
※8月に膀胱炎から腎不全になったマル。導尿カテーテルを膀胱へ留置しても何度も抜いてしまうマル。主治医から教えてもらって下腹部を圧迫して排尿する日々だった。今回こんな場面で搾尿技術が役立つとは。
『不幸中の幸い』 そっとつぶやいた。
『コップの水はまだ半分も残っている』 自分に言い聞かせる。
『五目焼きそばのウズラ卵はまだ残っている』 よく分からないが景気のいい(?)言葉を頭に並べる。
『まっ、最後に勝つのはオレたちさ』 マルの頭をそっと撫でた。
26日 よたよた歩きで約5メートル進む。
自力で水を飲んだ!
名前を呼ぶと尻尾を振った!
27日 ヘマトクリットは15.6。減少していない。創部の再処置で出血は止まったと判断していいのか?
主治医からは貧血が改善していないので輸血を勧められるが断る。
輸血の適応は・・貧血の数値は参考するが、あくまで赤血球の酸素運搬能力と心臓の赤血球運搬能力で判断するものだ。意識はある、つまり脳の重度酸欠なし。膀胱には尿がある、つまり心臓が腎臓へ血液を送り腎臓が尿を作っているから心臓と腎臓に重度酸欠なし。
なにより少しずつだが動くようになった。
マルは強い猫だと自分に言い聞かせる・・あるいは祈る。現時点で輸血副作用のリスクをおかす必要はない、マルの頑張りに期待する。
右顔面と右前足の腫れが引けてきた。
『ハンサムじゃないか、マル』 目に力が宿る。
『勝利はわれにありだ、マル』 頑張れ、マル。
28日 とぼとぼとトイレまで歩き自力で排尿した!
29日 うんこを出そうときばったが出ない。でも・・きばったぜ!
11月2日 ペースト状のフードを食べた!
4日 病院で摘便してもらう。
5日 猫缶1/4を食べる。流動食注入を減量。
前足で毛繕いする。
6日 食事をせがむ。通常のフード1/2を食べる。流動食注入さらに減量
7日 自力で排便。うんこの脇に定規を置いて写真に撮る。
8日 朝キッチンで皿にフードを盛っていると小走りで寄ってきた。
フード完食!
『コップの水はまだ半分も残っていた』 笑いがこみあげる。
『五目焼きそばの主役、ウズラの卵は残っていた』 涙がにじむ。
『まっ、最後に勝つのはオレたちさ』 マルの頭をそっと撫でた。


♪♪♪
【山下達郎薄皮の記(山下達郎途中退場の怪)】
12月25日18:30 山下達郎岩手県民会館大ホールに登場。
デビュー40周年ツアーのステージだ。
数曲演奏を終えたMCの達郎師匠「どうも喉にえへん虫がいるようで・・まあ、何十年もやっていればこんことが何度かあります。経験上ね、もうちょっとで良くなりますから。良くなったらまた頭からやりなおしてもいいですよ・・ふふっ」
それからも演奏は続いた。
「40周年なのでセットリストは明るい曲ばかりにしましたと言ったけど、一歩外に出ればけっして明るい世界じゃありません。パリの同時テロ、シリアの難民、ガザ地区の難民・・たくさんの悲惨さと隣り合わせの世界です。一曲だけ真面目な曲をやります」
こういって始めた『Dancer』 ベース伊藤広規先生のスラップが全身に刺さる。かっこいい。
『Dancer』の演奏が終わってからだ。袖に引っ込んだ達郎師匠が戻ってくるとステージのメンバーが全員去った。時間は20:00を少し回ったところだ。山下師匠が語り始めた。
「ちょうどここで半分です。あと半分の曲が残ってるとこです。えー・・どうしても一つの音が出ないんですよ。ライブを30年以上やってるけど、は30分たっても60分たっても声が戻らないなんてのは初めてです。どうしてもGが出ない。このまま歌い続けたってろくな結果になりません。暖かくなったら・・春になったら戻ってきます。
どうですか・・もし皆さんがよければ今日はここで止めます。
3月に戻ってきたらもう一度頭から全部やりますから・・どうですか?」
会場は拍手。「3月公演のお代はもちろんいただきませんから」笑顔の師匠にさらに大きな拍手。
「最後にやる予定だった曲を一曲だけやって終わりにします」
テレキャスターの弾き語りで歌ってくれたのは・・大瀧詠一『指切り』
ああ。シュガー・ベイブでもカバーしてたもんなあ。うるうる。
「Gか・・ソが出ないんだな」ぼくが隣に座っている連れに話すと
『ふーん。歌詞の”そ”が発音できないんだね、困ったもんだ』
「違う!」
この途中退場の顛末は・・
『山下達郎師匠G(ぐう)の音(ね)が出ない事件』
として長らく人々の記憶に残ることだろう。
♪♪♪
11月13日盛岡のライブハウス(ビル地下の小さなハコ)でクロマニヨンズに身体が揺れる。
ああ。甲本ヒロトの歌は応援歌なんだな。
12月12日仙台で斉藤和義にこころがはしる。
かずよしクンのギターを弾く姿にうっとり。ああ、路地裏のイエス様。
今夜もメロディと言葉がビンビン刺さるぜ。
3月盛岡公演のチケットもおさえてるよん、ふふっ。
12月25日盛岡公演で山下達郎師匠途中退場。
この日のチケット半券で3月の再公演が観られるもんな(笑)
♪♪♪♪♪
「知ってるか?
虹をつかみたきゃ雨を怖がっちゃだめだ」マルが話しけてきた。
「生きていくには希望が必要だ」
「必需品といってもいいくらいだ」
「うん。希望は冷蔵庫の中のほどよく冷えたマヨネーズのようだ」
「・・・・・」
『コップの水はまだ半分も残ってるもんな』 口元がゆるむ。
『五目焼きそばのウズラの卵は残っている』 笑いがこぼれる。
『サイコロをふり続けろ。どんな目が出たって最後に勝つのはオレたちさ』 手を叩く。
『エブリシンゴナビィオーライッ(Evrything's gonna be alright)』 にやりと笑ったマルがボブ・マーリーのレコードにあわせて歌いはじめた。
『大丈夫さ、大丈夫だよ』マルが笑いながら歌っている。
新年も楽しんで機嫌よくいきましょう。
Bob Marley 『 No Woman no cry』
【フムフム と ぐびぐび】
お久しぶりです。
以前何度かこのブログにイラストを描いてくれた金井真紀さんが本を出版しました。
初出版の縁起物です、どうか手にとってみてください。
縁起物です、表紙を撫でると御利益があるかも…。

『世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑』(金井真紀)
楽しくて愉快な本です。
どう楽しくて、どう愉快な本なんだ? 知りたいですよね、そりゃ。
どう説明したらいいんだろ?
ちょっと不思議な本なんですよ、これ。
表紙のコピーにはこう書いてあった。
「世の中には、いろんな人がいるなぁ。海女、牛飼い、落語家、プロ野球の監督…88人の達人に会って、88回キュンとした実録集。」
朝日新聞の読書欄「おすすめ」の記事はこうだった。
「前略・・仕事の達人88人から聞き取ったエピソード集。お笑い芸人や牛飼い、振付師など仕事のジャンルは様々。そしてその極意に思わず「フムフム」。・・後略」
うーん。この記事じゃ今一つこの本の面白さが伝わらないな。文字数に制限があったとはいえ通常の紹介文じゃ、この通常じゃ手に負えない面白さが伝わらない。
あっ、そうだ。著者略歴が面白いんだよな。
金井真紀(かない・まき)
1974 年、千葉県生まれ。うずまき堂代表(部下は猫2匹)。 ライター、イラストレ―ター、放送作家、書籍編集、酒場の ママなどを稼業とする。任務は「多様性をおもしろがること」。 1年間に人の話を聞くこと約100回、耳のそうじ約200回、 お酒を飲むこと約300回。
ねっ。この面白い「著者略歴」をさっと書きあげる技倆の持ち主の著者が、人好きで面白好きの著者が見そめた達人のエピソードを書き上げたのが本書なのです。
著者略歴を読んで人柄を想像すると、雑誌ダ・ヴィンチの書評がこの本の楽しさを伝えている気がしてくる。
「前略・・総勢88人の達人たち。彼らの口からこぼれた経験と実感に裏打ちされた珠玉の一言。それをすかさず手のひらで受け止め、フムフム袋にしまった作者は
、後で袋を広げ「ほら」と見せてくれる。・・後略」
そして。ここからは僕のレビュー。
多様な職業88人の達人たちの爽快、愉快、不思議なエピソードの数々が軽な文章で綴られている。
達人1人につき割かれてるのはたったの2たページなんだよこれが。その2ページに、のほほんイラストと短い軽妙文章。
だから。達人の全貌や、職業の詳細には触れられていない。書かれているのは達人が語った数分間程度のエピソードなんだろうな、これ。なのに不思議、短い文章で綴られた簡潔な描写から達人がひょいと浮き上がる。達人の顔や仕草まで見えるようで、ふふって嬉しくなる。
達人から勘所・つぼを選り分け切り取り量は少ないが美味しい素材を皿にしゅっと盛り付けたエピソードの数々。選り分け切り取る感性が面白く、皿に盛り付ける文章が楽しい。この西瓜は端が旨いとなったら端を切ってだす、この魚は焼くときの匂いが一番となったら団扇でパタパタと扇ぐ。達人が発するほんの一言なのにじわりと心に効くフムフムと、エピソードを美味しく皿に盛るシェフ金井の手際の両方が楽しめる本書。
あとがきに書かれた89人目のエピソードまで読みおわると、この本が面白い理由に気づく…「そりゃ世界は面白い人間でできているからさ」って。
最後にはメッセージがさらりと風に吹き払われ人間(達人)の面白みが残り、ふふっとなる読書の楽しみがそっと残った。
最後に。「これは茶柱本ですぞ!」と、大声で営業活動。新刊本の爽やかな香りを団扇でパタパタと扇ぎながら……。
【茶柱本】読むと縁起が良くなる本の意。
【効能】機嫌が良くなる、朗らかになる、勇気がわく、心にスイッチが入る
ビールが美味しくなる
http://www.amazon.co.jp/dp/4774406023?_encoding=UTF8&isInIframe=1&n=465392&ref_=dp_proddesc_0&s=books&showDetailProductDesc=1#iframe-wrapper
http://uzumakido.com/
そして金井真紀さん、初出版に引き続き今度は初個展。
『ぐびぐび俳画展』


***

靴を買った。
さあ夏だ。老いたりとはいえ男の子の夏は半ズボンだ。半ズボンになるなら足元はお気に入りの靴をはきたいところ。ああ靴が欲しい。
四角い大型スポーツ店の壁3面コの字型にずらりと並んだシューズの群れを端から見ていった。シューズの棚がどのジャンルかは確認しない。先入観をもたずに見ていき気に入ったデザイン・形のシューズを選ぶ作戦だ。
ああ…ボルダリングのシューズってソールが薄くてバレエ・シューズみたいでカッコイイんだよなあ。でもアレで歩いたら足の裏が痛いもんなあ…。
ある棚のアディダスのシューズに目が止まった。そばにいた女性店員に「運動以外の普段履きにもつかいたいんだけど、これの27cmはありますか?」と聞いた。
「これ普段は履けないですよ、アップ用です」の返事。
「・・・・・?」
「サッカーのアップ用です」
「・・・・・」
「ほら」と店員がシューズを裏返すとシューズの底に突起がついていた。
『この突起取れないの?』とは聞かない分別はあったから、笑顔でその場を離れ次の棚へと移動した。
あっ。かわいいデザインのナイキのシューズ!素材は何というのか…まあファブリックで…足首の部分がソックスのように盛り上がっている。というか、素材そのもがソックスみたいだ。うふふ、これに決めた。
手に取り念のため裏返しても突起はついていない。えへへ、やった-。
さっきと同じ店員に聞くと「これなら普段も履けますね」と笑っていた。
そこで初めてそこのジャンルを確認するとそこはランニング・シューズの棚で、手にしたシューズが置いてあった所の紙には「ベアフット・トレーニング用」と書かれていた。ほっほー。裸足で履くなら半ズボンのための靴のようなもんじゃないか。
むふふ。
そのシューズは上から見ると笹の葉のような細身のシルエットで、アウトソールも厚くない、全体にシャープな印象なのが気に入った。
普段ランニングのときはアシックスの初心者用シューズを履いている。分厚いクッションがついた幅広のシューズを履くと、どう見ても足だけが巨大だ。すれ違うランナーが履くエキスパート用の薄いシューズには憧れるが、あんなの履いて走ったら膝を痛めないか心配なのだし仕方がない。
『鉄腕アトムみたいだ』
道行く人たちがそう言わないかいつもヒヤヒヤする。
家に帰ると野菜を油で素揚げした。アスパラガス、茄子、パプリカ。油と熱で野菜の色は鮮やかになり、旨味は濃くなり、噛むとホクホクとした感触までが美味しい。冷えたビールがこれまたうまい!
1時間もすると足の甲の皮膚が突っ張るのを感じた。
ははー。大量のビールで足が浮腫んできたんだ。
床に投げ出していた裸足の足元を見た。
『鉄腕アトムみたいだ』
***
MANNISH BOYS(斉藤和義×中村達也) - 「GO! GO! Cherry Boy!」
斉藤和義「この曲はクロマニヨンズへのリスペクトやオマージュとかじゃなくて、もうクロマニヨンズなりたくて、パクリです」
そういえば。和義くんがカバーしている「雷雨決行」を教えてくれたのは
金井真紀さんだった。
「世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑」は面白いですぜ……パタパタパタ。
五里霧中
「今年も残りわずかだな」
「ああ」
「ちょっとさびしいな」
「そうか?」
男たち二人がボソボソと話している。
「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」大柄な男は
少し笑いながら言った。
「ハハハ。そのとおりだ。まだ手もつけちゃいない」小柄な男は喉をごくりと
鳴らし笑いを漏らした。
***
今思い出すと妙な日だった。
いつもはケチなおやじのたこ焼きのタコが大きかった。
テレビに映った気象予報士はいつもの自信家ぶりに似合わず明日の天気を断言
しなかった。
きまった時刻に食事をせがむ猫のマルが眠っていた。
大晦日の冬空なのにまるで夏のように青かった。
「どんな入浴剤つかってんだよ?」大柄な男は歩きながら空を見上げて隣の小
柄な男に言った。
二人の男が地元商店街のはずれにあるいきつけの食堂に入り、定食を食べはじ
めた時だ。電話の着信音が近くで鳴った。みるとテーブルの下の床にスマート
フォンが落ちていた。着信音を出しヴァイブで虫のように床の上で振動してい
るスマートフォンを大柄な男が手で拾いあげた。
***
「五里霧中だ」大柄な男は言う。
「・・・・・・?」小柄な男は返事をしないが大柄な男は話を続ける。
「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして
溶けてさ・・カレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。
あれってさあ・・」
「なんだよそれ?」
「分からなくなるよな」
「何が?」
「これはカレーなのか・・それともカレー風味のジャガイモ・ポタージュなの
か・・なんなのか分からなくなる」
「なんだよそれ?」
「困ったもんだ。これからどうしていいのか分からない。
方針も見込みも全くわからない」
「・・・・・・」
「五里霧中だ」
「今の俺たちだ」
* **
食堂の床から着信音を鳴らしているスマートフォンを大柄な男が拾い上げると
音は止み液晶画面にメッセージが浮かんだ。
『勇気はあるか?なあ運び屋の二人』
大柄な男は小柄な男にも液晶画面が見えるようにスマートフォンを机の上に置
いた。
『勇気だしてさ、オレの頼みを引き受けてくれ。』
小柄な男は一瞬だけ顔を険しくしたがすぐに鼻で笑って「こんなもん捨てちま
え」と言った。
『断ることなんかできぜねえぞ運び屋』
「ふざけんな!」小柄な男がスマートフォンに怒鳴った。
液晶画面に男たち二人の本名が浮かぶと消えた。それから次々と二人の過去の
仕事の記録が合法・非合法ないまぜになって液晶画面に浮かんでは消えた。
『どうだ?どんな相手かも分からない奴に自分のネタつかまれてる気分は?』
「ストーカーは犯罪だっての」困った顔で大柄な男は言い、小柄な男は無言で
液晶画面を睨んでいた。
『飯なんか食ってねえで店を出ろ。』
二人が座席のわきの窓から食堂の前を見ると黒いホンダのワゴン車が停まって
いる。
『車に乗るんだ』
二人が車を見ていると助手席のウインドウが下に降りて現れたのは短い髪の年
嵩の男だ。大きな鷲鼻の上に細い目がのっていた。
「悪党面だな」小柄な男が吐き捨てた。
「説明不要な人相の悪さだ。
大晦日の今日聞いてみたいくらいだ。
あなたは今年何回笑いましたか?笑顔の似合わないあなたが」大柄な男は笑
いながら言った。
小柄な男は黙って助手席の男を睨んでいたがコップの水を一口飲むとため息を
吐いた。
「新年の目標は『天真爛漫にしなさい』って教えてこようか?」
「相変わらずの悪党面のくそ野郎が」
「・・・・?」
「相変わらずふざけた登場の仕方しやがって」
「あの悪党面はおまえの出待ち?」大柄な男はまだ笑っていた。
「すまないが付き合ってくれ。
あのオヤジは黙って素通りできない相手なんだ」
「どんなヤツ?」
「怖いヤツだよ・・・」
机の上のスマートフォンが音を出して新しいメッセージが液晶画面に浮かんだ。
『急げ。急ぐんだ。
からすとうずら』
小柄な男はウッと唸り千円札を二枚机の上に置いて立ち上がった。
「顔文字も絵文字もないメールは冷たい感じだな」大柄な男は苦笑していた。
***
「五里霧中のときさ・・監督が言ったろ」
「なんの話しだ?」からすはうずらに聞いた。
「高校のときさ。サッカーの試合前に監督が言ったろ・・」
「・・・・・・」
「相手が俺たちじゃどうしようないくらい強いときさ。
まあ戦略なんかが通用する相手じゃないってくらい強いときさ・・。」
「今そんな話をしてる場合かよ」
「監督は笑顔で言ったんだ」
「・・・・・」
「『当たって砕けろだ』ってさ」万策尽き果てた監督のような笑顔でうずらは言
った。からすは渋面で黙っている。
「でも砕けるのは嫌だろ」うずらはまだ笑っていた。
「・・・・・」
「暗中模索だ。
シチューつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れし
て溶けてさ・・」
「黙れ!」
***
黒のワゴン車は企業が立ち退いてから塩漬けになったままの廃工場で停まり、
二人は運転手の若い男と年嵩の男に前後を挟まれ工場内の部屋に連れ込まれた。
からすは「ちょっとトイレに行ってくる。話はそれからだ」と言い残し部
屋を出ていき数分後に戻ってくるとうずらは男たちと笑いながら雑談にふけっ
ていた。
年嵩の男から依頼の話が始まるとからすが爆発した。
「無茶だ。そんな仕事が受けれるか!」
うずらは笑ったままで大きな身体を覆っているブカブカのフランス軍用コート
のポケットから小さなフリスクのケースを出して二粒を口へ放り込んで笑いな
がら年嵩の男へ向かって話しだした。
「俺たちは違法なことはやらないんだ。せいぜい脱法までだっての。
脱法だってけっこうヤバイんだけどな」
年嵩の男がニヤリと笑うとうずらが叫んだ「あっ、笑った。今年何回目?」
年嵩の男はうずらを無視してポケットから拳銃を出してからすに銃口を向ける
ともう一人の若い男も拳銃を取り出し銃口をうずらに向けた。からすは爆発を
しずめたがうずらは薄笑いのまま話し続けた。
「だからそれは違法だって。銃刀法違反だって」
「あのな。違法な仕事の中身を聞いて帰ってもらっちゃこっちは困るんだ」年
嵩の男は笑いを顔から消して低い声で言った。
「仕事を断られただけで相手を殺してちゃ事件になってアンタだってまずいだ
ろ。悪いことは言わない。死体の処理も面倒だぜ」からすが困った顔で言う
と年嵩の男は鼻でフンと笑って「そこまで心配すんな。後のことは俺に任せろ」と
面倒くさそうに言った。
「あのな。俺を殺すと後が面倒だぞ・・」
「・・・?」
「化けて出る」からすは言ってから恥ずかしそうに顔を赤くした。
「オマエな。ギャグのセンスは相変わらずだな。
どこの小学生だよ?」年嵩の男がゲラゲラ笑った。
「あっ。化ける化ける。こいつは『怪物くん』のファンだもん」うずらが無茶
を言うとからすは困った顔で「怪物と幽霊は違うんだって」とこぼした。
若い運転手が上着のポケットから黒い小さな箱のような物を出した。
「あのさあ。こいつは夏以外も出るよ。謹厳実直な働き者の幽霊だから年中出
るよ」話し続けるうずらの首筋に男が黒い箱を当てると先端の金属から青白
い光が出た。うずらは急に話を止め膝から崩れて前のめりに倒れて動かなくな
った。「おい。なにすんだよ?ちょっと待て」からすは叫んだが若い男は無表情
でスタンガンをからすの右肩に当てた。男が「次の人どうぞ」と言ったらまる
で予防接種の流れ作業のようだ。
「ウッ」と言うとからすも倒れて動かなくなった。
* **
目覚めたからすとうずらは・・・目覚めた?そう二人は殺されちゃいなかった。
でも二人は困っていた。相当に。
二人は床に尻をついて座っていた。コンクリート打ち放しの壁からむき出しに
なった太い金属パイプに結束バンドで手をパイプに縛り付けられていた。後ろ
手で。二人が背中合わせに。
「おい。起きてるか?」背中越しにからすが聞いた。
「ああ。生きてるな俺たち。ところでさ」
「なんだ?」
「オマエさ。ホントに化けられるの?」
「知らねえよ」
「えっ?」
「まだ死んだことねえもんな。試したことねえよ」
「試せるかも・・・」
「はあ?」
からすには位置関係のせいで見えないが・・背中合わせのうずらの前にタブレ
ットPCが置かれていた。液晶画面には『08:33:55』と表示され右端の数字
が刻々と減少している。そう。まさに刻々と。
「刻々と減ってるな・・」うずらが珍しく困った声で言った。
「なんのことだ?」いらついて大きな声をだしたからすへうずらは状況を説明
した。
「それでさ。タブレットPCから伸びたケーブルが黒い箱に繋がっててな。箱の
上にはな。灯油缶が乗ってるんだよ」
「・・・・・」
「暖房用の灯油かな。それともなんか燃やすのかな?」
「燃やすんだろうな・・」
「ところでさ」
「・・・」
「化けるの試してみる?」
「試したかねえよ」
「でもさ」
「・・・」
「あの液晶画面の数字さ。ハッピーニューイヤーのカウントダウンの可能性は
ないかな?」
「この状況で・・あるかよそんなこと」からすの声を無視してうずらは続けた。
「でさ。新年と同時に黒い箱からプレゼントが出てさ。
サプライ〜ズ・・とかさ」
「あのな。黒い箱が爆発して灯油が燃えてな。ここが火の海になったらな。
俺はかなりな・・・驚くぞ」
「ああ。やっぱサプライ〜ズじゃん」
「妙なこと言ってねえでどうすりゃいいのか考えろ!」
「五里霧中だ」うずらが言った。
「・・・・・・?」からすは返事をしないがうずらは話を続ける。
「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして
溶けてさカレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。
あれってさあ・・」
***
「監督が言ったろ。『当たって砕けろ』って」
「だから爆発で砕けるかもしれないんだって」
後ろ手に縛られたまま身動きできない二人。この状況をからすは罵りうずらは
笑う。
またうずらが話を始めた。
「やっぱあれだな」
「・・・」
「織田信長も最後は灯油で燃えて熱かったろうな」
「時代的に灯油じゃないだろうけどな」
「じゃ何油?」
「知るか!」
数分黙っていたうずらがまた話し始めた。
「あのさ」
「今度はなんだ?」
「キャットフードは人間の口には合わないもんだな。
まずいよアレ」
なんの良いアイデアも浮かばないからすはうずらの話を無視して結束バンドで
結ばれた手首を力任せに動かしたが金属パイプはびくともしない。
「あっ」声を出したうずらに向かってからすが「どうした?」と聞いた。
「あと6時間だ。ってことは今午後6時だ」
「・・・」
「マルの夕御飯の時間だ」
「こんなときに猫の飯の心配なんかしてんじゃねえ」いらついたからすが喚く
とうずらのブカブカ軍用コートの内ポケットからサバトラ柄の猫が顔を出した。
からすの耳に背中越しに猫の鳴き声が届く。それからドサッと床に着地する音
が響いた。
「マルなのか?マルがいるのか?」からすは大きな声をだした。
「だから夕御飯の時間なんだって」うずらがそれがどうしたというような声音
で言った。
身体が柔軟なうずらは右足のつま先でコートの内側を蹴ると外側のポケットから
フリスクのケースが床に落ちた。うずらは左足のかかとを振りおろすとケースが
壊れて中から茶色い粒状の猫用ドライフードが床に散らばった。
マルはゴロゴロと喉を鳴らして喜んだ。キャットフードを頬張るマルの音がか
らすの耳へ背中越しに届いた。ガツガツと。
「どうして・・」
「昼ごはん食べなかったろ。マルを家に置いとくの心配だから連れてきたんだ
よ。ご飯をせがんだらあげようと思ってさ。ほら。フリスクのケースに入
れてきた」
「早く言えよ」
「さっきキャットフード食べたらまずかったって?」
ガツガツとマルが頬張る音はまだ続いている。
「おい。何やってる?マルにこの結束バンドを噛み切らせるんだ」言ったからすに
うずらは呆れたような声で返答した。
「だから。夕御飯の時間なんだって」
「早く食べ終われよマル」
マルの食事の音が止んで数分たったが結束バンドを噛む音も感触もしない。
「マルはなにしてるんだ?」聞いたからすに「決まってるだろ」とうずらは言
うが「だからマルはなにしてるんだよ?」と再度からすが聞いた。
「眠ってるよ。食後だもん」
「おい!」
「黒い箱の上で眠ってるよ。ああ。あの箱さ。暖かいんだなきっと」
「・・・・・」
残り3時間とうずらが言うとカリカリという音がからすの耳に届いた。
「なんだ?」
「タブレットPCの液晶画面で爪とぎしてるよ」
「危ねえから止めさせろ!」からすが悲鳴にちかい声をだした。
からすの声を無視してうずらが暢気な声をだす。
「今年も残りわずかだな」
「・・・・・」
「ちょっとさびしいな」
「・・・・・」
「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」うずらは笑
いながら言った。
「ああ。ここを抜けだして新年に手を付けねえとな」からすは喉をごくりと鳴
らして答えるとマルにむかって「こっちだ。こっちに来いマル」と叫んだ。
マルが小走りに近寄ってくる音が響いた。トコトコと。
「そうだマル。こっちだ。こっちに来い」
音がする。カリカリ・・カリカリと。
「鉄パイプで爪とぎなんかしてんじゃねえよ」からすが言うとうずらは仕方ないよ
という声で「爪とぎしないと古い爪がかさぶたみたくなって困るんだって」と言った。
「・・・・・・」
***
「これからどうする?」
「これで終わりだ。もう連中には関わらねえ」言って廃工場の駐車場から背後
を振り返ったからすは200メートル向こうで紅く燃える工場と湧き上がる黒
煙を見つめた。
「本能寺みたいだな」ぼそっと呟くうずらへ「見たことあるのかよ?」とから
すが笑って言った。からすが続けた。
「・・連中は俺たちが死んだと思ってるだろ?」
「うん。多分な。
五里霧中で暗中模索の本能寺の変だって思ってるだろうな」
「オマエが変だっての」
「うん・・?」
「それにな。怖いヤツなんだよ・・あいつ。
もう関わらないほうがいい」
二人が歩いて工場の敷地から出ようとすると見覚えのある黒のワゴン車が
コンクリート塀の前に停まっている。近づいてみるとワゴン車はフロントが塀に
突っ込み潰れていた。
「どういうこと?」うずらはからすに向かって言って続けた。
「これやったのオマエだろ」
「・・・」
「なんで一人で遊ぶんだよ」うずらは悔しがって拗ねながら言う「なあ。なに
やったんだよ?」
「俺さ。食堂に行く前にさ。商店街で入浴剤を買ったんだ」
「なんのこと?」
「オマエが青空見上げて入浴剤かよ?って言ったからさ。
青空みたいな風呂に入りたくなってさ。入浴剤買ったんだよ」
「・・・・・」
「その入浴剤をさ。エンジンオイルの中に入れたんだ」
「おまえトイレに行くって言ってそんなことしてたのか・・」
「知ってるか・・水と入浴剤を混ぜて密閉すると・・」
「ああ。ペットボトル爆弾だな。
でもエンジンオイルじゃ・・」
「ああ。だから俺も半信半疑でさ」
「半信半疑か・・。
まあスタンガンで失神した後の五里霧中よりはずいぶんましだ」
「まあな。それで結果はワゴン車がコンクリート塀に・・」
「当たって砕けろだ」うずらがゲラゲラ笑いながら言うとからすもつられて笑
った。
通りにでて歩いていると商店街にさしかかった。
「おい。まだ蕎麦食ってないよ」うずらが情けない声をだした。
「冷えるしな。熱い海老天蕎麦でも食うか?」からすが弾んだ声で言う。
「駄目だって。
猫が甲殻類を食べると腰をぬかすんだって」うずらが毅然と言う。
「・・・・・」
「部屋に戻って酒でも飲むか?」からすは言うと「大晦日だしな熱燗で」とつ
けたした。
「八代亜紀の舟唄を聞きながら?」うずらはニヤニヤ笑った。
「ああ。オマエが倍賞千恵子なら抱きしめてるよ」
「高倉健は刑事の役だよ。オマエには似合わない」
「あのな。高倉健は日本の男なら全員憧れていいんだよ」
商店街を中程まで進むとスピーカーから除夜の鐘が鳴り出した。
「始まったな」からすはニヤニヤ笑っている。
「ああ。手つかずの新年がな」うずらもニヤニヤ笑う。
「今年もよろしくな」言ってからすは右手で拳をつくりうずらへ差し出した。
うずらは左拳でからすの拳をパンッと叩き今度はニコニコ笑ってこう言った。
「こちらこそ」
【蛇足】
長らくご無沙汰しているあいだに大晦日になってしまいました。
今回は年末のご挨拶がわりに慌てて書きました。
みなさん今年はどうもありがとうございました。
新しい年がみなさんにとって実り多い日々であることを願います。

「ああ」
「ちょっとさびしいな」
「そうか?」
男たち二人がボソボソと話している。
「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」大柄な男は
少し笑いながら言った。
「ハハハ。そのとおりだ。まだ手もつけちゃいない」小柄な男は喉をごくりと
鳴らし笑いを漏らした。
***
今思い出すと妙な日だった。
いつもはケチなおやじのたこ焼きのタコが大きかった。
テレビに映った気象予報士はいつもの自信家ぶりに似合わず明日の天気を断言
しなかった。
きまった時刻に食事をせがむ猫のマルが眠っていた。
大晦日の冬空なのにまるで夏のように青かった。
「どんな入浴剤つかってんだよ?」大柄な男は歩きながら空を見上げて隣の小
柄な男に言った。
二人の男が地元商店街のはずれにあるいきつけの食堂に入り、定食を食べはじ
めた時だ。電話の着信音が近くで鳴った。みるとテーブルの下の床にスマート
フォンが落ちていた。着信音を出しヴァイブで虫のように床の上で振動してい
るスマートフォンを大柄な男が手で拾いあげた。
***
「五里霧中だ」大柄な男は言う。
「・・・・・・?」小柄な男は返事をしないが大柄な男は話を続ける。
「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして
溶けてさ・・カレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。
あれってさあ・・」
「なんだよそれ?」
「分からなくなるよな」
「何が?」
「これはカレーなのか・・それともカレー風味のジャガイモ・ポタージュなの
か・・なんなのか分からなくなる」
「なんだよそれ?」
「困ったもんだ。これからどうしていいのか分からない。
方針も見込みも全くわからない」
「・・・・・・」
「五里霧中だ」
「今の俺たちだ」
* **
食堂の床から着信音を鳴らしているスマートフォンを大柄な男が拾い上げると
音は止み液晶画面にメッセージが浮かんだ。
『勇気はあるか?なあ運び屋の二人』
大柄な男は小柄な男にも液晶画面が見えるようにスマートフォンを机の上に置
いた。
『勇気だしてさ、オレの頼みを引き受けてくれ。』
小柄な男は一瞬だけ顔を険しくしたがすぐに鼻で笑って「こんなもん捨てちま
え」と言った。
『断ることなんかできぜねえぞ運び屋』
「ふざけんな!」小柄な男がスマートフォンに怒鳴った。
液晶画面に男たち二人の本名が浮かぶと消えた。それから次々と二人の過去の
仕事の記録が合法・非合法ないまぜになって液晶画面に浮かんでは消えた。
『どうだ?どんな相手かも分からない奴に自分のネタつかまれてる気分は?』
「ストーカーは犯罪だっての」困った顔で大柄な男は言い、小柄な男は無言で
液晶画面を睨んでいた。
『飯なんか食ってねえで店を出ろ。』
二人が座席のわきの窓から食堂の前を見ると黒いホンダのワゴン車が停まって
いる。
『車に乗るんだ』
二人が車を見ていると助手席のウインドウが下に降りて現れたのは短い髪の年
嵩の男だ。大きな鷲鼻の上に細い目がのっていた。
「悪党面だな」小柄な男が吐き捨てた。
「説明不要な人相の悪さだ。
大晦日の今日聞いてみたいくらいだ。
あなたは今年何回笑いましたか?笑顔の似合わないあなたが」大柄な男は笑
いながら言った。
小柄な男は黙って助手席の男を睨んでいたがコップの水を一口飲むとため息を
吐いた。
「新年の目標は『天真爛漫にしなさい』って教えてこようか?」
「相変わらずの悪党面のくそ野郎が」
「・・・・?」
「相変わらずふざけた登場の仕方しやがって」
「あの悪党面はおまえの出待ち?」大柄な男はまだ笑っていた。
「すまないが付き合ってくれ。
あのオヤジは黙って素通りできない相手なんだ」
「どんなヤツ?」
「怖いヤツだよ・・・」
机の上のスマートフォンが音を出して新しいメッセージが液晶画面に浮かんだ。
『急げ。急ぐんだ。
からすとうずら』
小柄な男はウッと唸り千円札を二枚机の上に置いて立ち上がった。
「顔文字も絵文字もないメールは冷たい感じだな」大柄な男は苦笑していた。
***
「五里霧中のときさ・・監督が言ったろ」
「なんの話しだ?」からすはうずらに聞いた。
「高校のときさ。サッカーの試合前に監督が言ったろ・・」
「・・・・・・」
「相手が俺たちじゃどうしようないくらい強いときさ。
まあ戦略なんかが通用する相手じゃないってくらい強いときさ・・。」
「今そんな話をしてる場合かよ」
「監督は笑顔で言ったんだ」
「・・・・・」
「『当たって砕けろだ』ってさ」万策尽き果てた監督のような笑顔でうずらは言
った。からすは渋面で黙っている。
「でも砕けるのは嫌だろ」うずらはまだ笑っていた。
「・・・・・」
「暗中模索だ。
シチューつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れし
て溶けてさ・・」
「黙れ!」
***
黒のワゴン車は企業が立ち退いてから塩漬けになったままの廃工場で停まり、
二人は運転手の若い男と年嵩の男に前後を挟まれ工場内の部屋に連れ込まれた。
からすは「ちょっとトイレに行ってくる。話はそれからだ」と言い残し部
屋を出ていき数分後に戻ってくるとうずらは男たちと笑いながら雑談にふけっ
ていた。
年嵩の男から依頼の話が始まるとからすが爆発した。
「無茶だ。そんな仕事が受けれるか!」
うずらは笑ったままで大きな身体を覆っているブカブカのフランス軍用コート
のポケットから小さなフリスクのケースを出して二粒を口へ放り込んで笑いな
がら年嵩の男へ向かって話しだした。
「俺たちは違法なことはやらないんだ。せいぜい脱法までだっての。
脱法だってけっこうヤバイんだけどな」
年嵩の男がニヤリと笑うとうずらが叫んだ「あっ、笑った。今年何回目?」
年嵩の男はうずらを無視してポケットから拳銃を出してからすに銃口を向ける
ともう一人の若い男も拳銃を取り出し銃口をうずらに向けた。からすは爆発を
しずめたがうずらは薄笑いのまま話し続けた。
「だからそれは違法だって。銃刀法違反だって」
「あのな。違法な仕事の中身を聞いて帰ってもらっちゃこっちは困るんだ」年
嵩の男は笑いを顔から消して低い声で言った。
「仕事を断られただけで相手を殺してちゃ事件になってアンタだってまずいだ
ろ。悪いことは言わない。死体の処理も面倒だぜ」からすが困った顔で言う
と年嵩の男は鼻でフンと笑って「そこまで心配すんな。後のことは俺に任せろ」と
面倒くさそうに言った。
「あのな。俺を殺すと後が面倒だぞ・・」
「・・・?」
「化けて出る」からすは言ってから恥ずかしそうに顔を赤くした。
「オマエな。ギャグのセンスは相変わらずだな。
どこの小学生だよ?」年嵩の男がゲラゲラ笑った。
「あっ。化ける化ける。こいつは『怪物くん』のファンだもん」うずらが無茶
を言うとからすは困った顔で「怪物と幽霊は違うんだって」とこぼした。
若い運転手が上着のポケットから黒い小さな箱のような物を出した。
「あのさあ。こいつは夏以外も出るよ。謹厳実直な働き者の幽霊だから年中出
るよ」話し続けるうずらの首筋に男が黒い箱を当てると先端の金属から青白
い光が出た。うずらは急に話を止め膝から崩れて前のめりに倒れて動かなくな
った。「おい。なにすんだよ?ちょっと待て」からすは叫んだが若い男は無表情
でスタンガンをからすの右肩に当てた。男が「次の人どうぞ」と言ったらまる
で予防接種の流れ作業のようだ。
「ウッ」と言うとからすも倒れて動かなくなった。
* **
目覚めたからすとうずらは・・・目覚めた?そう二人は殺されちゃいなかった。
でも二人は困っていた。相当に。
二人は床に尻をついて座っていた。コンクリート打ち放しの壁からむき出しに
なった太い金属パイプに結束バンドで手をパイプに縛り付けられていた。後ろ
手で。二人が背中合わせに。
「おい。起きてるか?」背中越しにからすが聞いた。
「ああ。生きてるな俺たち。ところでさ」
「なんだ?」
「オマエさ。ホントに化けられるの?」
「知らねえよ」
「えっ?」
「まだ死んだことねえもんな。試したことねえよ」
「試せるかも・・・」
「はあ?」
からすには位置関係のせいで見えないが・・背中合わせのうずらの前にタブレ
ットPCが置かれていた。液晶画面には『08:33:55』と表示され右端の数字
が刻々と減少している。そう。まさに刻々と。
「刻々と減ってるな・・」うずらが珍しく困った声で言った。
「なんのことだ?」いらついて大きな声をだしたからすへうずらは状況を説明
した。
「それでさ。タブレットPCから伸びたケーブルが黒い箱に繋がっててな。箱の
上にはな。灯油缶が乗ってるんだよ」
「・・・・・」
「暖房用の灯油かな。それともなんか燃やすのかな?」
「燃やすんだろうな・・」
「ところでさ」
「・・・」
「化けるの試してみる?」
「試したかねえよ」
「でもさ」
「・・・」
「あの液晶画面の数字さ。ハッピーニューイヤーのカウントダウンの可能性は
ないかな?」
「この状況で・・あるかよそんなこと」からすの声を無視してうずらは続けた。
「でさ。新年と同時に黒い箱からプレゼントが出てさ。
サプライ〜ズ・・とかさ」
「あのな。黒い箱が爆発して灯油が燃えてな。ここが火の海になったらな。
俺はかなりな・・・驚くぞ」
「ああ。やっぱサプライ〜ズじゃん」
「妙なこと言ってねえでどうすりゃいいのか考えろ!」
「五里霧中だ」うずらが言った。
「・・・・・・?」からすは返事をしないがうずらは話を続ける。
「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして
溶けてさカレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。
あれってさあ・・」
***
「監督が言ったろ。『当たって砕けろ』って」
「だから爆発で砕けるかもしれないんだって」
後ろ手に縛られたまま身動きできない二人。この状況をからすは罵りうずらは
笑う。
またうずらが話を始めた。
「やっぱあれだな」
「・・・」
「織田信長も最後は灯油で燃えて熱かったろうな」
「時代的に灯油じゃないだろうけどな」
「じゃ何油?」
「知るか!」
数分黙っていたうずらがまた話し始めた。
「あのさ」
「今度はなんだ?」
「キャットフードは人間の口には合わないもんだな。
まずいよアレ」
なんの良いアイデアも浮かばないからすはうずらの話を無視して結束バンドで
結ばれた手首を力任せに動かしたが金属パイプはびくともしない。
「あっ」声を出したうずらに向かってからすが「どうした?」と聞いた。
「あと6時間だ。ってことは今午後6時だ」
「・・・」
「マルの夕御飯の時間だ」
「こんなときに猫の飯の心配なんかしてんじゃねえ」いらついたからすが喚く
とうずらのブカブカ軍用コートの内ポケットからサバトラ柄の猫が顔を出した。
からすの耳に背中越しに猫の鳴き声が届く。それからドサッと床に着地する音
が響いた。
「マルなのか?マルがいるのか?」からすは大きな声をだした。
「だから夕御飯の時間なんだって」うずらがそれがどうしたというような声音
で言った。
身体が柔軟なうずらは右足のつま先でコートの内側を蹴ると外側のポケットから
フリスクのケースが床に落ちた。うずらは左足のかかとを振りおろすとケースが
壊れて中から茶色い粒状の猫用ドライフードが床に散らばった。
マルはゴロゴロと喉を鳴らして喜んだ。キャットフードを頬張るマルの音がか
らすの耳へ背中越しに届いた。ガツガツと。
「どうして・・」
「昼ごはん食べなかったろ。マルを家に置いとくの心配だから連れてきたんだ
よ。ご飯をせがんだらあげようと思ってさ。ほら。フリスクのケースに入
れてきた」
「早く言えよ」
「さっきキャットフード食べたらまずかったって?」
ガツガツとマルが頬張る音はまだ続いている。
「おい。何やってる?マルにこの結束バンドを噛み切らせるんだ」言ったからすに
うずらは呆れたような声で返答した。
「だから。夕御飯の時間なんだって」
「早く食べ終われよマル」
マルの食事の音が止んで数分たったが結束バンドを噛む音も感触もしない。
「マルはなにしてるんだ?」聞いたからすに「決まってるだろ」とうずらは言
うが「だからマルはなにしてるんだよ?」と再度からすが聞いた。
「眠ってるよ。食後だもん」
「おい!」
「黒い箱の上で眠ってるよ。ああ。あの箱さ。暖かいんだなきっと」
「・・・・・」
残り3時間とうずらが言うとカリカリという音がからすの耳に届いた。
「なんだ?」
「タブレットPCの液晶画面で爪とぎしてるよ」
「危ねえから止めさせろ!」からすが悲鳴にちかい声をだした。
からすの声を無視してうずらが暢気な声をだす。
「今年も残りわずかだな」
「・・・・・」
「ちょっとさびしいな」
「・・・・・」
「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」うずらは笑
いながら言った。
「ああ。ここを抜けだして新年に手を付けねえとな」からすは喉をごくりと鳴
らして答えるとマルにむかって「こっちだ。こっちに来いマル」と叫んだ。
マルが小走りに近寄ってくる音が響いた。トコトコと。
「そうだマル。こっちだ。こっちに来い」
音がする。カリカリ・・カリカリと。
「鉄パイプで爪とぎなんかしてんじゃねえよ」からすが言うとうずらは仕方ないよ
という声で「爪とぎしないと古い爪がかさぶたみたくなって困るんだって」と言った。
「・・・・・・」
***
「これからどうする?」
「これで終わりだ。もう連中には関わらねえ」言って廃工場の駐車場から背後
を振り返ったからすは200メートル向こうで紅く燃える工場と湧き上がる黒
煙を見つめた。
「本能寺みたいだな」ぼそっと呟くうずらへ「見たことあるのかよ?」とから
すが笑って言った。からすが続けた。
「・・連中は俺たちが死んだと思ってるだろ?」
「うん。多分な。
五里霧中で暗中模索の本能寺の変だって思ってるだろうな」
「オマエが変だっての」
「うん・・?」
「それにな。怖いヤツなんだよ・・あいつ。
もう関わらないほうがいい」
二人が歩いて工場の敷地から出ようとすると見覚えのある黒のワゴン車が
コンクリート塀の前に停まっている。近づいてみるとワゴン車はフロントが塀に
突っ込み潰れていた。
「どういうこと?」うずらはからすに向かって言って続けた。
「これやったのオマエだろ」
「・・・」
「なんで一人で遊ぶんだよ」うずらは悔しがって拗ねながら言う「なあ。なに
やったんだよ?」
「俺さ。食堂に行く前にさ。商店街で入浴剤を買ったんだ」
「なんのこと?」
「オマエが青空見上げて入浴剤かよ?って言ったからさ。
青空みたいな風呂に入りたくなってさ。入浴剤買ったんだよ」
「・・・・・」
「その入浴剤をさ。エンジンオイルの中に入れたんだ」
「おまえトイレに行くって言ってそんなことしてたのか・・」
「知ってるか・・水と入浴剤を混ぜて密閉すると・・」
「ああ。ペットボトル爆弾だな。
でもエンジンオイルじゃ・・」
「ああ。だから俺も半信半疑でさ」
「半信半疑か・・。
まあスタンガンで失神した後の五里霧中よりはずいぶんましだ」
「まあな。それで結果はワゴン車がコンクリート塀に・・」
「当たって砕けろだ」うずらがゲラゲラ笑いながら言うとからすもつられて笑
った。
通りにでて歩いていると商店街にさしかかった。
「おい。まだ蕎麦食ってないよ」うずらが情けない声をだした。
「冷えるしな。熱い海老天蕎麦でも食うか?」からすが弾んだ声で言う。
「駄目だって。
猫が甲殻類を食べると腰をぬかすんだって」うずらが毅然と言う。
「・・・・・」
「部屋に戻って酒でも飲むか?」からすは言うと「大晦日だしな熱燗で」とつ
けたした。
「八代亜紀の舟唄を聞きながら?」うずらはニヤニヤ笑った。
「ああ。オマエが倍賞千恵子なら抱きしめてるよ」
「高倉健は刑事の役だよ。オマエには似合わない」
「あのな。高倉健は日本の男なら全員憧れていいんだよ」
商店街を中程まで進むとスピーカーから除夜の鐘が鳴り出した。
「始まったな」からすはニヤニヤ笑っている。
「ああ。手つかずの新年がな」うずらもニヤニヤ笑う。
「今年もよろしくな」言ってからすは右手で拳をつくりうずらへ差し出した。
うずらは左拳でからすの拳をパンッと叩き今度はニコニコ笑ってこう言った。
「こちらこそ」
【蛇足】
長らくご無沙汰しているあいだに大晦日になってしまいました。
今回は年末のご挨拶がわりに慌てて書きました。
みなさん今年はどうもありがとうございました。
新しい年がみなさんにとって実り多い日々であることを願います。

1=0.99999999・・・
青空に白い煙が昇っていった。秋晴れの上空へ真っ直ぐに昇っていった煙の先
端は雲に届いていた。
「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。
「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。
「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。
「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。
黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。
「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。
「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠
は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」
明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」
見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。
午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。
あの一本気な煙は源だ。
堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの
煙は源だ。四人ともそう感じていた。
眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。
源は自宅の屋根に降り積もった落ち葉を掃き下ろしていたときに屋根から地上
に落下した。すぐに病院に搬送され8階病棟(最上階)に入院したがほどなく
死んだ。そして今は煙になってはるか上空へ昇っている。
最後まで上り下りの激しい人生だった。
*******
苺が十四才の誕生日のときのことだ。父親と母親は「ちょっと出かけてくる」
といつものように言った。年に数回ちょっと出かけてくる両親だった。
数週間から数ヶ月のちょっとだった。一人娘の苺を残してふらりと出かける二
人だった。戻ってきた両親にむかって苺がどこに行って何をしていたかを聞い
ても父と母は「ちょっとね」と言うだけなのもいつものことだった。
『謎は謎のまま残り、新たな謎を生んだ』同じ町内の誠は言った。
誠・・通称マコちゃん六十二才、居酒屋店主でロック歌手、謎の多い不思議な
男だ。不思議な謎男がこう言う謎の両親は昨日まで十三才だった苺の理解をも
ちろん超えていた。
それはもちろん十四才になった今日も。
「今度のはちょっと・・ちょっと長いんだ」父が申し訳なそうに言った
「うん。長いんだよね、これが」母は嬉しそうに言った。
「だから・・・?」苺は両親の間に立ってニコニコ笑ってる男を指さした。
笑ってる男は源。苺の祖父だ。日本中を放浪して「流しの花火師」と「流しの
手品師」をやっていて、年に一度大晦日に帰ってきて正月二日には家を出て行
く源爺だった。マコちゃん同様謎の多い・・なぞなぞ男だ。
苺が十才のときのこと。イチゴを食べてる苺をカメラでバシャバシャ撮りなが
ら「苺の共食い写真だ。こりゃスクープだ」と何が楽しいのかはしゃいでいた
謎の祖父だ。
「これから俺はずっとこの家で苺と一緒に暮らすんだ」源爺は自慢げに言った。
「それじゃ父さんと母さんはずっと帰って来ないってこと?」苺が声を大きく
した。
「ちょっとな・・」両親と源爺は声を揃えて言った。
「・・・・・」
両親は午後の新幹線で出かけると言って中学へ行く苺を玄関で見送った。
苺は家を出て数分歩くと大きな橋のたもとについた。それから橋の欄干に沿っ
て川面を眺めながら歩いた。
「ちょっと・・かあ。でも源爺との二人暮らしがちょっとで済むわけないんだ
よね」
苺が生まれ育った所は市内中央を南北に川幅の大きな川が流れている。その川
を東西に跨ぐように架かる三つの橋がある。北から順に上ノ橋、中ノ橋、下ノ
橋と呼ばれていた。中の橋から東へ数キロメートル行くと昭和の初めから続く
仲町商店街があった。近くに大きなお寺があったためか戦中の空襲の時も焼夷
弾の投下から免れていた。苺の家はこの商店街の中に建っていた。
戦争の空襲から免れ、高度経済成長の波に洗われ小ぎれいになった商店街も、
昭和五十年以降近隣に出現した大きなスーパーマーケットやコンビニに客足を
奪われた。さらには、平成を迎え二十年近くなると郊外に次々と現れた巨大シ
ョッピングモールに壊滅的な打撃を加えられた。巨大ショッピングモールは市
の郊外を巨大な円陣で囲むように建ち・・まるで英国製の羽根なし円形扇風機
が送風の変わりに空気を吸い込むように市内各所の古い商店街から客足を奪っ
た。仲町商店街は地元住民が日々の生活用品を買い、壊れた家電や破れた衣類
の直しを依頼する「(商店街)住民の住民による住民のための」商店街として
皆が支え合ってなんとか成り立っていた。
しかし仲町商店街を覆う空気は意外なことに暢気だった。その暢気さを苺は愛
していた。そして暢気に能天気を上塗りしていたのが・・酒屋の修、文房具屋
の明、居酒屋の誠、そして源の幼馴染み四人だった。中学生にしては早熟な苺
はこの六十代の能天気どもを愛していた。そんな苺でも源と誠の無茶には迷惑
していた。
『無茶はどんどんやる。けどな。無理はしねえ。
無理するのはダセーだけだ』よく分からないことを源は苺に言う。
『三流の大人で一流の男ってことだ』誠も応じて胸を反らした。
仲町商店街と背中合わせに拡がった飲食店街がオリオン横丁だ。
オリオン横丁に誠が一人で切り盛りしている居酒屋があった。客が八人も入れ
ばいっぱいな小さな店で毎晩常連客が賑やかに話していた。店が混雑してくる
と苺も手伝わされた。
「あのさあ。わたしが手伝いに来たのに、マコちゃんがカウンターに座って飲
んでるってさあ・・なんかルール違反だよな」苺が眉間に皺をよせた。
「ルールその1『未成年の飲酒は禁じられています』」誠が笑顔で応じた。
「酒飲みたいなんて言ってない。働きなさいって言ってるの」眉間の皺が深く
なった。
「ルールその2『大人は子供を甘やかさない』」誠の隣に座った源が言った。
「大人は信じられない」やれやれという顔に苺はなった。
「貴方は神を信じますか?と同じくらいに、貴方は大人を信じますか?は出口
の見えない命題だ」源が混ぜっ返した。
「『大人は判ってくれない』フランソワ・トリュフォー」苺が応酬した。
誠は唇の端を曲げて笑うと・・ぼそぼそと低い声で歌うように話し始めた。
「『Don’t trust anyone over 30』よみ人知らず。
1960年代に三十以上の連中を信用するなって言っていたディランやストーン
ズだってもういい爺だ。物わかりの悪い正しい年寄りだ。
子供を甘やかすのは年寄りの悪い癖だ」
「でもミックは若い女に甘い」苺は手厳しい。
「・・・・」「・・・・・」
「源爺は上着のポケットからキャバクラのお姉ちゃんの名刺が出てきた。
マコちゃんは子供のような年齢の女と腕を組んで歩いていた」
苺はたたみかけた。
「年寄りを甘やかすのは子供の悪い癖だ。わたしは良き子供でありたい」
「・・・・・」「・・・・・」
*******
苺が十六才になった夏の宵。
仲町商店街の七夕祭りでのことだ。商店街を通る車道は通行止めにされ歩行者
天国になっている。夜になってやっと吹いてきた風にたくさんの色とりどりの
七夕飾りがゆらゆらと揺れていた。路上にはびっしりと露店が並びそこかしこ
から客引きの声が聞こえてくる。日中の暑気は通りに残り、風は出てきたが大
勢の人出で空気は動かず苺は団扇をひっきりなしに扇ぎながら歩いていた。
『もう暑いよ。盛り過ぎだって。大盛りだって今年の盛夏』
三十分前のことだ。苺は浴衣の着付けに手こずり八つ当たり気味に源に向かっ
て愚痴っていた。『先に行ってるぞ』と源は隣室へ声をかけ、愚痴が怒りに変わ
りそうな苺から逃げるように家を出て行った。
苺は七夕飾りを眺めながら源を探して通り歩いていると奇妙な露店を見つけた。
露店の幟には『言葉堂本舗』と書かれていた。大きな机が一つだけ置かれ、椅
子には男が一人座っていた。標語のような言葉が書かれた紙が机の前に何枚も
貼られていた。道行く人は感心がないのか足を止めずに素通りしていった。
男の話しを立ち止まって熱心に聞いているのは源と誠の二人だった。
男の物売り口上は淀みがなかった。
「言葉堂本舗でございます。
当店が扱っておりますのは、言葉でございます。
『世界は素敵な言葉であふれてる』
当店が取り扱っております言葉は、
名言、きめ台詞、キャッチコピー
短歌、俳句に川柳、どどいつ
自由律詩に壁の落書き、便所の哲学
謳い文句、殺し文句、歌の文句にセロニアス・モンク
心はなやぐ言葉の数々。
『美辞に麗句にお世辞にヨイショ!』
貴方の気持ちをぐいっとアゲてみせましょう。
『羽を持たない心だってな、空を飛ぶことができるんだ』
『そんなことができるの?』
『いいかいお嬢ちゃん。言葉使いのおじさんに出来ないことなんかないんだ』
さあさあ。心浮き立つ言葉の数々。
ユーモアはあるが冷笑はありません。
ウイットはあるが皮肉はありません。
当店は、貴方にお似合いの言葉を探します。
貴方を励ます、貴方に寄り添う、そんな言葉を探します。
言葉ソムリエです。
もしご希望でしたらオリジナル言葉の作成も承ります。
自分にフィットした言葉を呟くと・・・
元気が出ます。
勇気が湧きます。
アイデアが閃きます。
跳躍力が3%伸びます。
風呂あがりに湯冷めしません。
ビールが美味しくなります。
ブラボー。
さてお立ち会い。
手前ここに取りいだしたるは素敵な「言葉」の数々」
男は紙に書かれた古今東西の名言・至言・アフォリズムを次から次へと両手で
掲げて解説を始めた。男の解説を聞きながら「気に入った」とか「その通り」
とか相づちをうっているのは源と誠だった。その大げさなリアクションはどう
見ても露店のサクラだ。しかし二人をよく知る苺には分かる。あれは本気で
感心しているんだ。
言葉堂本舗の男の口上に熱がこもった。
「それでは…ここからは当店オリジナルの科白を。
『すべての男は本末転倒と役立たずの先に存在する』
ほら。気持ちが軽くなるでしょ。男ってのはね。そんなもん。
じたばたしても、それ以上でも以下でもない。
それじゃ次。これは強烈。
『すべての女は慈悲と理不尽のないまぜでできている』
ほら。はなから、男は女に敵わいって分かって気分が楽になるでしょ。
優しくて不合理・・勝てる相手じゃないんだって。うんうん。」
源と誠の二人も「うんうん」と頷いている。
言葉堂本舗のシステムはこうだった。男が客をカウンセリングして客にフィッ
トした言葉を古今東西の名言から選ぶ。もしくは男がオリジナルの言葉を考え
る。それから机の上のパソコンで男が文字をデザインして紙へ印刷する。
「おい。自分で考えた言葉もデザインして印刷してくれるか?」源が声を張り
上げた。
「いいよ。それが希望なら」男は笑顔で頷いた。
すると不敵な笑みを浮かべたのは源の隣に立っていた誠だった。
「俺も自分で考えるぞ!」誠が言うと源は「じゃあ勝負だな」と誠を睨んだ。
苺は口のなかで呟いて立ち去った。
『この二人の男は役立たずの中にだけ存在する』
********
三日間の七夕祭りが終わった翌日の夜。
台所の冷蔵庫のドアを開けた源が「ビールが入ってねえ」と怒鳴った。
「仕方ない。行こう」苺の言葉に「よし行くぜ」と応じて源は笑った。
急ぎ足で誠の居酒屋へ着いた二人は店に入った。早い時間のせいか客は他にい
なかった。カウンターに置いてあるビールの入ったコップは誠のものだろう。
「冷えたビール」「冷えた麦茶」二人はカウンター席に座る前に言った。
誠は手作りの麦茶を冷蔵庫から出してコップに注ぎカウンターに置き、それか
ら瓶ビールの栓を抜きコップと一緒に麦茶の隣に置いた。
誠は注文も聞かずに冷蔵庫からズッキーニを三本取り出して厚めに切った。
フライパンを火にかけオリーブオイルでニンニクを香りが出るまで炒めると、
そこへ切ったズッキーニと手でちぎった鷹の爪を入れニンニクの香りが移った
オリーブオイルを絡めるように炒めた。最後に塩を一振りかけてから皿に盛り
つけカウンターに置いた。
「美味しい。マコちゃんこれ美味しいよ」苺が目を輝かせた。
「・・・マコ、ちょっと厨房借りるぞ」
「なんだよ源?」
「俺の料理ほうが美味い」
「源爺なに張り合ってんの」
「コイツは苺が美味いって言ったとき鼻を鳴らしたんだ。
『当然だ』って言うように」
「普通鳴らさないか・・鼻。当然だっていうときゃ鳴らすだろ鼻を」
「こいつはガキの頃から謙虚じゃねえんだ」
「どの口が言う?」
「あのな。人間は謙虚が大事なんだ。『実るほど頭を垂れる稲穂かな』だ。
それをなんだ、料理を褒めてもらって鼻ふん当然ってのは」
「あのな。実って頭下げられちゃな・・
『実ってねえのにふんぞり返っててすみません』って恐縮してる不憫な稲穂
が可哀想だろうよ」
「はあ?なんだその屁理屈は。
だいたいな胡瓜の油炒めなんてな、河童も喰わねえよ」
「ズッキーニ。これは胡瓜じゃないの。ズッキーニ」
「なんだ苺。オマエがマコに味方するってどういいうことだ?」
「へへん。ズッキーニはな胡瓜の仲間だ」誠が得意げに言った。
「ズッキーニは胡瓜に似てるけどカボチャの仲間」
「なんだよ。苺はどっちの味方なんだよ?」
「どっちの味方でもないよ。だいたいね、六十過ぎのいい大人がさあ・・・
高校一年女子に向かって『どっちの味方だ?』ってさあ。
恥ずかしくないわけ?」
「全然」「何が?」源と誠は同時に答えた。
「だからね。孫みたいな年の子供の前でね・・実際隣の男の孫だしね。
マコちゃんは孫同然のわたしに、源爺は孫そのもののわたしにさ、
『どっちの味方だ?』とか大きな声出してさ。
恥ずかしくないのって」
「ない」「ない」源と誠はまた同時に答えた。
「・・・・・」
二人の口論を無視して麦茶を飲みながらテレビの野球中継を見ていた苺は
テレビの横の壁にかけてあった色紙に目がいった。
「なにアレ?」
「ん・・?」
「テレビの横のアレはなんなのって聞いてんの」
「あっ。あれか。あれはほら・・言葉堂本舗で作った色紙だ」
苺の声につられて色紙をみた源がゲラゲラ笑い出した。
「だーかーら。なんなのアレって聞いてんの。
あの言葉はなんなのって、わたしは聞いてるの」
「人間はな、引込みじあんはいけねえなって…」
「・・・・・」
「自分の得意技をバンバン出してドカドカ賑やかにいくぞって」
「・・・・・」
「もう出し惜しみなしだぞって」
「・・・・・・」
壁に掛かっていた色紙には『能ある鷹の爪』と書いてあった。
顔を真っ赤にして笑っていた源は鞄から色紙を取り出すとカウンターの上に置
いた。色紙の文字を読んだ誠は飲んでいたビールを吹き出してゲラゲラ笑い出
した。苺は口の中の麦茶を飲み下すと大きな溜め息を吐いた。
『自我自賛』と色紙には書いてあった。
「自分の精神をさ・・俺のハートをさ、自ら褒めるんだ。
もっと自信をもって堂々と生きようぜってな・・」
苺が源の話しを途中で切った。
「あのさ。二人とも子供の頃から謙虚じゃないってのが今よーく分かった。
あのね二人はね仲良しじゃない同じなんだ。
源爺とマコちゃんはね精神的双生児だよ」
「・・・・・」「・・・・・」
「オレがオレがの自己主張ばっかのオレオレ色紙だ」
ふいに店の戸が開く音が聞こえた。入ってきたのは言葉堂本舗の男だった。
顎と首の区別かつかないくらい太った、映画「紅の豚」のポルコ・ロッソのよ
うな男だった。太った風貌だけじゃない。白い麻の三つ揃いスーツに赤いネク
タイを締め丸い黒サングラスにパナマ帽を被ったところはポルコそのものだっ
た。男はカウンター席に座わりパナマ帽をとりサングラスを外して禿頭を右手
で掻いた。源は慌てて色紙を鞄にしまい、誠はそそくさと色紙を壁から外した。
照れる・恥ずかしがる心は二人にもあることを確認して苺は笑った。
「ミントジュレップをくれ。砂糖は少なめに。控えてるんだ」男は言ってゲラ
ゲラ笑った。
誠はグラスを出し砂糖とソーダを入れ、スプーンで潰して香りを出したミント
を加えてよくかき混ぜた。布でくるんだ氷を麺棒で叩いて砕いた。バーボンを
注いだグラスに砕いた氷を入れ手早くステアしてカウンターに置いた。
「面白い商売だな」誠は瓶ごとビールを飲みながら言った。
「まあな。人間の言葉に興味があるんだ。
人を傷つけもするが救うこともする言葉にな。
それと美味い酒が好きなんだ。これは良い出来のミントジュレップだ」
男が源と苺の皿を見て、オレにも同じものをくれというので誠は作ってだした。
「それはズッキーニだ。胡瓜じゃないぞ」源が自慢気に言った。
「知ってるけど」男は怪訝な顔で源に頷いてから苺に話しかけた。
「お嬢ちゃん。アンタは幸せだ。この二人は良い男たちだ。
シンプルな言葉を吐くシンプルな男たちだ」
源と誠はしまった色紙を出そうとした。
「もう。出さなくていい。
この二人はね・・複雑が苦手なだけなの」
「お嬢ちゃん。言葉も音楽も生き方も・・シンプルが一番だぜ」
「いい。『ここではあなたのお国より、人生がもうちょっと複雑なの』」
苺は映画「紅の豚」のジーナの科白をさらりと言った。
男はそれを聞いてゲラゲラ笑って言った。
「『飛ばねえ豚は、ただの豚だ』
お嬢ちゃんはいつか・・空を飛ぶかもしれない」
「ええっ。空を飛ぶ前に豚になっちゃうのは嫌だ」
源が満面の笑顔で男に話しかけた。
「アンタ良いヤツだな。
ジブリの映画を観ろ!これが、オレの教育方針だ」
「ロックを聴け!苺にいつも言ってるんだ」誠も負けずに言った。
「なんてシンプルな教育だ。お嬢ちゃんはやっぱり幸せものだ」男のゲラゲラ
笑いは止まらなかった。
「アンタ手品が得意なんだってな」笑いやむと男は隣の源に言った。
「ん・・。まあな」
男は「こんなのはどうだ」と言うと、ポケットから五百円硬貨を出してカウン
ターの上に置いた。そして硬貨の上に空のグラスを置いた。
と、その瞬間に硬貨はグラスの中へ移動した。しかも硬貨は裏返っていた。
誠と苺が感心して「ほう」と言うと、男は照れくさそうに笑った。
五分後に男は会計をして店を出て行った。
「見事な手品だった。でもあれくらいはなあ・・」誠の言葉に苺がかぶせた。
「源爺の手品のほうがもっと凄いよ」
男の手品を見てから黙っていた源が話し始めた。
「アイツのは手品じゃねえ」
「はあ・・じゃあなんだって言うんだ?」
「アイツは種も仕掛けも使ってなかった。
あれはトリックなしのマジックなんだ・・と思う。
魔法っていうかさ・・」
「えっ?」苺と誠が同時に声をあげたが源は答えず誠に言った。
「マコ。さっきしまった色紙を出してみろ」
誠は色紙を見て声をあげた「おお!」
色紙には手書きの文字が書き加えられていた「ロック」と。
源が出した色紙には「ジブリ」と書かれていた。
二枚の色紙どちらにも手書きのアルファベットが書いてあった「M」と。
「凄い!」苺が歓声をあげ、誠が「やるじぇねえか」と笑った。
源はまた黙ってしまった。
店を出た源と苺はオリオン横丁を並んで歩いた。
「苺。空を見ろ」言うと源は空にかかる月を頭上に伸ばした右の掌で覆った。
「いいか・・見てろよ」
源の右掌がスーッと前方に動くと頭上の月が消え、右掌を横に動かすとそこに
月が現れた。
「あのな。今苺が見たのはな・・実はトリックなしのマジックなんだ」
「・・・・・」
********
苺十六才、秋の夜。
食卓で苺は源がつくったカレーを食べていた。向かいに座った源は福神漬けと
ラッキョでビールを飲んでいた。
苺が浮かない顔でカレーを食べているのが気になって誠が聞いた。
「どうした・・まずいか?」
「ううん。ちょっと辛いけど大丈夫・・美味しい」
食べ終わると苺は学校の出来事を話した。
今日のクラスルームは映画のディスカッションだった。教師から指名された苺
が自分の推薦する映画について語り質疑に応答し、以後はフリートークとなった。
苺の推薦映画は「風の谷のナウシカ」だった。
担任の男性教師は熱烈な宮﨑駿ファンだ。
プロジェクターにつないだラップトップ・パソコンからキー・シーンを選んで
上映しながらプレゼンテンショーンした。
苺が話すのを中断し映像を流していたときのことだ。
数人の男子生徒が小声だがこう言ったのが苺の耳に届いた。
「ウゼー」
最初にナウシカを観たのが何歳なのか記憶がないくらいに幼い頃から観てきて、
共感し、楽しんできた苺は動揺した。
教師は目にうっすらと涙をためた。
「あのな苺。そいつがウゼーって思ったんなら、映画はそいつに届いたんだ。
けどな・・化学反応がおきなかったんだな」
「・・・・・」
「俺はこのカレーに隠し味としてニンニク、バター、唐辛子、砂糖、和風だし
を入れた。いいか。いくら隠し味を入れても苺の身体や心と化学反応しなか
ったらオマエはこのカレーを美味しいと感じない」
「味覚は個人によって違う」
「まあ・・本当に美味しいものは多くの人にとっても美味しいんだけどな」
「うん」
「それとな。映像は個人の心理も影響するんだ」
「・・・・・」
「人は見たいモノを見る。人は見たいように見る。」
「うん?」
「そして。人は見たいモノが見える。聞きたいモノが聞こえる」
「うん・・?」
「『心理のバイアス(偏向)』っていうんだけどな。
物事をネガティブに悲観的に捉える傾向の人っているだろ。
逆に何でも楽観的にポジティブに考える人もいるよな」
「いるね」
「いいか。映画の戦闘シーンでは視聴者の感情が揺れるだろ。
主人公が敵に勝つ爽快感や、戦闘の虚無感や、暴力の愚かさや・・
それぞれ個人によって違うだろ」
「うんうん。それなら分かる」
「それと個々とは別に多くの人に共通する心理のバイアスもあるんだ」
「偏向が共通するってある?」
「いいか。苺はこのカレーを食べたときどんな味に感じた?」
「カレー味だよ。そりゃカレーだもん」
「つまり多くの人が期待するカレー味にすると美味しく感じる。
カレーと感じたいカレーを食べると満足する。
甘いカレーは・・辛いのが苦手な人でもカレー味としては満足しない」
「なるほどね!」
「手品はこの多くの人に共通する心理バイアスをついてるんだ。
多くの人が見たいモノを見たいように見せてるのが手品だ。
多くの人は見たいようにみてるだけ。
つまり多くの人はトリックに気づきたくないんだ」
「ふんふん」
「詐欺は個人の心理バイアスに応じて攻めると騙せる。
電話のオレオレ詐欺は元々悲観的な心理バイアスを持つ人の不安感を大きく
煽って騙すんだ。だから逆に騙されない人もいる」
「カレー好きのわたしはカレカレ詐欺に気をつけないと」
源はビールを飲みながら苺に紙と鉛筆を持ってくるように言った。
「人は見たいモノを見る・・とは違うんだけどな。
1/3はいくつだ?紙に書いてみろ」
そんなの計算しなくても分かると苺は言ったが、源はいいから書けと言った。
苺は紙に書いて源にみせた。
『1/3=0.33333・・・・・・』
源はビールを一口飲むと「それじゃ。両辺に3を掛けてみろ。ほら」と言った。
「ん・・?」
「ほら」
「あっ!」苺は小さく叫んだ。
『1=0.99999・・・・・』
「1は1じゃないの?」
「数学的なことは俺には分からないがな。
1は1じゃない。この式じゃ1は0.99999・・・・・なんだ」
「ふーん。不思議な感じ」
「いいか。1は数字だけど・・概念でもある。単一とか孤立とか。
1はイメージでもある。
1とか単一とか聞いた人は誰もさ。
『0.99999・・・・・』をイメージしないだろ」
「人はイメージしたいようにイメージする・・とか?」
「いや。俺が言いたいのはな。
1がだぞ、誰だって単一とイメージしてる1だって複雑なんだ。
だから世界は面白いんだ」
「そうかなあ・・『1=0.99999・・・・・』ってさあ。
小数点以下の9がずっと続くでしょ。際限なく続くでしょ。
いつまでたっても完全な1には辿り着かない。
なんか切ないなあ」
「そうか。俺はそう思わないけどな。
俺はな・・ちょっと嬉しくなるんだ」
「・・・・・?」
********
苺十七才、春の宵。
午後から商店街に近い公園で始まった町内会の花見は夕方にははねて、いつも
のメンバーで誠の居酒屋に集まった。修、明、源、苺がカウンター席に座り乾
杯をした。厨房に入った誠はツブ貝と胡瓜を切って三杯酢で和えて出し、木串
に刺した肉を焼いた。
修が酔いのまわった顔で焼き鳥を囓りながら「半人半獣のケンタウロスってい
るだろ?」と言った。
「いねえ」誠はにべもなかった。
修が続けた「上半身が人間で下半身が馬のやつ」
「だから、いねえんだ。ケンタウロスは神話だ」
修はコップ酒を飲みながら話を止めない「なあ。半魚人っているだろ?」
「それも、いねえ」誠は言い放った。
修が続けた「半魚人ってよ、半分人間で半分魚ってことだろ。
だけどありゃ、どう見ても人間でも魚でもねえよな」
「だから、いねえんだ。半魚人はアメリカの怪奇映画の作りもんだ」
「えっ。そうなの?」明が驚いた顔をして
「うちにフィギュアがあるんだけど・・」と怪訝な顔をして呟いた。
「あのなあ。なんでもかんでも信じるな。電話がきたらどうする?」誠が言う。
「爺ちゃん・・オレオレ半魚人」と言って源が笑った。
「オレオレ半漁人詐欺だ。気をつけないと」苺がクスクス笑った。
「じゃあ。こんなのはどうだ。信じるか?」源が話し始めた。
「太陽は実は移動している。しかも移動速度は時速7万キロメートルだ。
どうしてかって?宇宙全体は加速膨張してるだろ。その膨張につれて太陽も移
動している。だから太陽の周囲を公転する惑星は円運動じゃなくてさ、円運動
しながら前へ進んでるんだ。だから惑星は螺旋状に回転しながら進んでる。
つまり地球も螺旋回転しながら太陽と一緒に時速時速7万キロメートルで進ん
でるんだ」
「時速7万キロメートルだあ?」明は大きな声で叫んだ。
「地球は螺旋回転しながら宇宙を進んでるって・・」修の声はしぼんだ。
カウンターの内側に立っていた誠は「うっ」と唸ると厨房の柱に両手でつかま
り両足を踏ん張った。
修は椅子に座ったままカウンターの出っ張りを両手で握った。
「この椅子はシートベルトないよなあ」明は不安げな顔をした。
源と苺はジェットコースターに乗った客のように両手をこれみよがしに頭上に
挙げて笑った。
「いいか。光の速度は時速108億キロメートル・・」源は誠から電卓を借りて計算し始めた。
「うん。太陽の進行する時速7万キロメートルは光速の約1/1億5千万だな。
そして・・宇宙の膨張速度は光速の3倍なんだ。だからさ、時速7万キロメ
ートルなんて微々たるもんだ」
三人の男はホッと安堵の息をはいた。
「でな」源がまた話し始めた。
「螺旋回転で進行してる地球の遠心力と太陽の引力がつりあってるから俺たち
はシートベルトがいらないわけだ。けどな。太陽が膨張して引力が大きくなっ
たら地球は太陽に・・」
「太陽に・・?」三人は同時に言って源の言葉を待った。
「太陽に地球は突っ込む。
だからな。空に見える太陽が大きくなったらヤバいんだ」
「あっ、さっき見た夕陽が大きかった」言うと苺はペロッと舌を出して笑った。
三人の男は同時にギャッと言ってテーブルをつかんで足を踏ん張った。
「源ちゃんの話しは半魚人より怖い」修が言った。
自分も怖がったのに照れ笑いを浮かべて誠が言った「太陽が簡単に膨張するかよ。
なんでもすぐに信じると電話がかかってくるぞ」
「爺ちゃん・・オレオレ太陽、膨張して太っちゃってさ」と言って源が笑った。
「オレオレ太陽詐欺だ。六十過ぎたら気をつけないと」苺がクスクス笑った。
苺はマコちゃんが煎れた緑茶を飲みながら山菜の天麩羅を食べた。
源爺、マコちゃん、明おじさん、修くん。気持ちの良い幼なじみの男たち。
四人がいるからわたしは寂しくない。
四人はわたしのシートベルトだ。
誠はテレキャスターをアンプにつながずに弾き始めた。
ローリング・ストーンズ『スタート・ミー・アップ』のイントロだ。
キースのように気怠げにためをつくったリズムのカッティングだ。
「地球はロック&ロールだな。
キースは言ったんだ。
『ロックをやるバンドはくさるほどいる。
だけどな。ロールしてる連中が見あたらねえ』ってな。
地球は螺旋状にロールしてる本物のロックなんだな」
苺は思った『マコちゃんはシートベルトじゃなくて・・アクセルだ』
誠が突然大きな声をだした「あっ。俺な、中学のとき神社の宵宮でな・・・
テキ屋の兄ちゃんが夜店で半漁人を売ってたの見たことあるぞ」
苺は思った『源爺はシートベルトじゃない。効きの悪いブレーキだ』
源が誠へ話しかけた。
「今日なネットで『正義の味方』を検索したら俺がでてきたよ」
「奇遇だな」
「何が?」
「俺も『正義の味方』を検索したら俺がでてきたよ」
ふいにマコちゃんと源爺が苺に顔を向けるとニッと笑って自慢げに言った。
「俺たち最強だろ」
苺は声に出さずに口の中で呟いた。
『アクセルと効きの悪いブレーキのコンビって・・最悪だ』
********
苺十八才、夏の日盛りの午後。
市内中央を流れる大きな川に架かった橋のたもとの川原へ降りるコンクリート
の幅広の階段に苺と源は座っていた。街路樹が日陰をつくりコンクリートの階
段は座ってもそれほど熱くなかった。
源は『CAT or DIE』(猫さもなくば死を)とプリントされたTシャツを着ていた。
苺のTシャツには『NO CAT NO LIFE』(猫がいなきゃ人生じゃない)とプリ
ントされていた。
みんなが暮らす仲町商店街とオリオン横丁の界隈には「御稲荷さん」と呼ばれ
て親しまれている小さな神社がある。神主もいない小さな社と狐の石像が一体
だけの、由緒や縁起を知る人間は誰一人いない神社だった。
小さな境内にはベンチが置いてあって、そこは休憩したり日向ぼっこしたりす
る場所になっていた。
石の狐は右前足を石の玉の上に乗せている。狐の首にはイタリアACミランの
マフラーが巻かれていた。マフラーを巻いたのは誠だ。
「あの凛々しい狐顔はバレージだ。ACミランのフランコ・バレージだ。
右足をサッカーボールに乗っけてるんだから間違いない。
センター・バックのバレージがこの町内を守ってくれてるんだぜ。
チャオ、バレージ!」
その石像は狐顔の人間ではなく狐顔の狐だったが誠は「あれはバレージだ」
と言って譲らなかった。
その小さな神社の境内にはいつも十五匹くらいの野良猫が出入りしていた。
仲町商店街とオリオン横丁の連中は猫好きなのか無頓着なのか、それが
いつもの風景なんだと思ってるのか横丁の路地や神社にいる野良猫を気にしなかった。
いやむしろ可愛がってる連中のほうが多かった。
その野良猫たちのうち数匹が横丁から出て道路を挟んだ向こう側の住宅街に出入りし始めた。
住人の何人かは道路や壁が汚れると市役所へ苦情をいった。
すると市役所は野良猫排除の行政方針を出した。なんでもかんでもクリーン好
きの役人のやりそうなことだった。
猫好きの苺は「我儘だけど良い連中じゃないか」と怒った。
同じく猫好きの源は「権力の横暴だ。住民票を持たない猫に市役所が介入する
とはどういう料簡だ」と怒った。
「権力」という言葉に過剰に反応する「反権力・反骨」が信条の誠も怒った。
修と明もつられて・・・怒った。
猫排除反対の署名を町内で集めて市役所に持っていったが対応した役人は「検
討させて頂きます」と、明らかに検討する気のない顔つきと尊大さで答えた。
苺は「里親を探そう。SNSで呼びかけよう」と提案したが源が反対した。
「野良猫はフリーランスが信条だ。連中は誰にもどこにも属さない。
どこへ行くのもどんな夢をみるのも自由だ」路地に寝そべる猫を見て源が続
けた「やつらの自由さかげんを見ろ。俺は生まれ変わったら野良猫になる」
「源爺の自由とおおらかさを野良猫も讃えてるよ」苺が笑った。
誠は『反骨音頭』というレゲエ・リズムの曲を作った。ほどよく歪んだ音を出
すテレキャスターをかき鳴らし「野良猫排除反対集会」で歌った。
しかしその歌は野良猫排除反対を訴えるというより誠の反権力・反骨の心情を
歌ったものだった。「でも曲の出来は良いよ」苺が拳の親指を突き上げて笑った。
そろいのTシャツを着たみんなが踊っていた。
「マコちゃんのしゃがれてるけど伸びのある声イイよね」苺が笑顔で言った。
『長いものには巻かれない それ
多数決には屈しない それ
きれい事には騙されねえ それ
それそれそれそれ
反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう
偉いヤツには屈しない それ
大樹の陰には近寄らねえ それ
ウマイ話は嘘だらけ それ
それそれそれそれ
反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう
背中を丸めて歩かない 反れ
猫背の野良にも注意する 反れ
重い荷物はしんどいぜ それ
登り坂はきついけど それ
坂の上には雲がある それ
それそれそれそれ
反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう』
その日は午前十時から「野良猫排除派」と「野良猫容認派」の意見交換会が公
民館で行われた。お互いの意見は平行線のまま交じらず、互いの胸に届かず、
当然化学反応も起こさず、落としどころもないまま会は正午前に散会した。
源と苺は野良猫排除派の論理に呆れ、役所の事なかれ主義に腹が立ち怒りで頭
も身体も火照ってしまったので冷やし中華とかき氷を食べた。
食堂を出て歩いた二人は二十分後には川原へ降りる階段に座って話した。
「苺はいくつになった?」
「十八才。そろそろ十代も終わる。
さよなら十代、こんにちは二十代・・」
「さよなら讃岐うどん、こんにちは長崎ちゃんぽん」
「十代と二十代はそんなに違わないでしょ?
こんにちは名古屋きしめん・・くらいかな」
「覚悟しろ、かなり違う。期待しろ、かなり面白い」
「源爺の二十代はどんなだった?」
「青春だ」
「何才までが青春だった?」
「俺は小学校に入学して以来今までずっと青春だ」
「ギネス青春記録だ」
「苺は今まで会った人よりもっと多くの人に出会う。
いろんな考えやいろんな思いに出会う。
それは。時には自分とは違う意見だったりする」
「今日も自分と違う意見の人たちに会ったもんね」
「そうだ。俺たちと向こうの連中の意見は違った」
「役所はどうするんだろうね?やっぱ排除かな」
「排除だろうな。まあ。その前に野良猫の救済計画をたてよう」
「うんうん。なんとか救けよう。
それにしたって排除だなんてね。
あれだね。正義はたいてい負けるって本当だね」
「『ヒーローはどこにでもいる』ってバッドマンは言ったけどな・・」
「ああ。『ダークナイト・ライジング』のあの科白ね。
『ヒーローはどこにでもいる。
それは上着を少年にかけ、世界の終わりではないと励ますような男だ』」
「ヒーローはどこにでもなんかいない。
ゴートン刑事はあの映画の重要な登場人物だ」
「どこにもなんている人間じゃない」
「まあ。ヒーローはどこにもなんかいないってことだ。
だけど。
正義はどこにでもあるんだ」
「・・・?」
「いいか苺。
正義も不義も。善も悪も。その時代とか、個人の立ち位置や都合で変わる。
だから・・正義も善もどこにでもごろごろある。
実際なにが正義でどれが善なのかはよくわからないことのほうが多い」
「ややこしくって困ったもんだ」
「例えばグリーン・パラドックスだ」
「なにそれ?」
「ヨーロッパの或る国では脱原発へ舵を切り再生可能エネルギーでの
発電量を増やした」
「いいねえ」
「当然電力量は高騰した。だから企業は安い電力を求めて隣国へ工場を移転し
た。すると隣国は火力発電を増やし大気汚染が悪化した」
「えー、良くないじゃん」
「だけど隣国は雇用が増えGDPは上昇した」
「うーん難しい。世界はパラドックスに満ちている」
「一難去ってまた一難だ」
「さよなら讃岐うどん、こんにちは長崎ちゃんぽん・・だ」
「どっちも美味しいから俺はウエルカムだ」
「わたしもどっちも好きだ」
「だからな苺。よーく考えてな、そして思い切ってな。
ときには物事を善悪で判断しないで好きか嫌いで判断したっていいんだ。
面白いか面白くないかで判断するのだって場合によっちゃな・・・ありだ」
「うん」
「大事なのは自分の判断に責任をもつことだ」
「うん」
二人は立ち上がり階段を降りて川原に立った。陽射しが川面で跳ね踊っていた。
苺が顔を源に向けて聞いてきた。
「どうして源爺はわたしの前ではいつも笑ってるの?」
「いつも笑ってるか俺?」
「そうだよ。いつでも笑ってる。
それってさ。もしかしてさ。わたしの前じゃかっこつけてるわけ?」
「大人が笑ってればな・・子供は伸び伸びするんだ。
やせ我慢でもな、大人がかっこつけてれば・・子供だって踏ん張るんだ」
「・・ありがとね。源爺」
「俺は苺が好きだ。苺が面白い。だから苺は俺にとって善で正義だ」
「わたしは源爺の善で正義・・」
「もちろん俺は苺の味方だ。
つまり。俺は正義の味方だ」
「ふふっ」
「夏の午後ヒーローは川原に立っていた。
それは少女に、世界の終わりではないと励ますような男だ」
「その男は太陽が膨張し世界は終わると友人を騙した男だ」
「・・・・・」
********
苺十八才、秋の昼下がり。
柔らかな黄金色の陽射しがあたりに降りそそいでいた。
家の縁側に座って本を読んでいるとガサッと音がして大量の落ち葉が庭へ落ち
てきた。何事かと庭に降りて上を見上げると二階の屋根に立った源が竹箒で落
ち葉を掃いていた。隣の家は古い大きなお屋敷で、そこの庭の落葉樹から大量
の落ち葉が苺の家の屋根に降り積もり時に雨樋を塞いでしまう。それで時々源
は屋根に登って落ち葉を掃いた。
まあ面倒くさいけどな、隣にあんな立派な樹があるから紅葉を楽しめるんだし
な、と源は落ち葉を気にしてなかった。
源は庭に立っている苺へ屋根から声をかけた。
「おい。葉っぱを集めろ。焼き芋しよう。銀杏も焼こう。ビール飲もう」
「焼きビールは美味しくない」
「なに言ってる、ビールは焼かない」
「ビール解禁前十八才女子の前で美味そうにビールを飲むヤツへの罰だ。
焼きビールを飲ませてやる」
「・・・・・」
源は落ち葉払いが終わったのか手を動かさなくなった。じっと下を見ていた。
「源爺。竹箒を股に挟んで何やってんの?
屋根の端に立ってちゃ危ないって。落ちても知らないよ」
「ひょいとな・・飛ぼうかと思ってな」
「何言ってるの?空中浮遊のマジックなんか今やらなくていいから。
失敗したらどうするの・・ねえ降りなさいよ」
「しばらくやってねえからなあ・・」
「竹箒股に挟んで何をブツブツ言ってんの?
そんなことして飛べるわけないでしょ。魔法使いじゃないんだから」
急に吹いた風が鳴らした葉音に源の声はかき消され苺の耳には届かなかった。
「あのなあ。俺は・・実は・・・・・」
源は一旦屋根のてっぺんまで昇ると振り返り下をみた。ふうっと息を吐いた。
「源爺。何やってんの!」
源は竹箒を股に挟んだまま屋根の斜面を駆け下りた。
そのまま助走し屋根の先端から足を離した。
「あれ?」
なさけない声を出して源はそのまま庭に落下した。
苺が集めていた落ち葉の山へ激突して源は仰向けになった。衝撃で辺りへ飛び
散った紅色と黄色の落ち葉が目の前を舞った。日差しで葉脈が透けて見える葉
の群舞が綺麗で一瞬見とれたがあまりの痛さに顔をしかめた。
「源爺ぃ。なにやってんのお!」
落ち葉がクッションになったが衝撃を完全に吸収されたわけじゃなかった。
源の足は外側へ変な角度で曲がっていた。その足を見た苺は小さく悲鳴をあげ
泣き顔になった。源は仰向けのまま苺を見上げて言った。
「おい。落ち着け苺。あのな。この足だけどな。
チャールストン踊ってるみたいだろ?」
苺は怒った顔でクスリとも笑わなかった。
源は苦痛に顔を歪めたまま恥ずかしそうに笑った。
救急車で搬送された源はそのまま入院となった。
苺は担当医から説明を受け、病室に戻ると診断書を源に見せた。
「『両側大腿骨複雑骨折』ってなんだ?」誠は興味なさそうに言った。
「中華料理の名前みたいだ。
甘酢あんかけがのって出てきそうだ」と苺は困った顔をした。
「びっくりさせたな苺。
ちょいと油断するとな電線にとまってる雀だって落ちるかもしれないんだ」
「『猿も木から落ちる』ってこと?」
「『弘法も筆に謝る』だな」
「なんなのそれ。ふざけないでちゃんと謝りなさいよ」
源のベッドの上半身部分はを斜めに起き、両足はギプスで固定されている。
ベッドサイドの椅子に座る苺に右手を握らせ、源はその上に自分の右掌を数秒
間乗せて離した。
ほら手を開いてみろと言われた苺は、なんの手品かと思い掌を広げたがそこに
は何もなかった。
「なんにも無いけど・・」と苺は言った。
「そうだな。なんにも無いな」
苺が怪訝な顔をすると源が話し始めた。
「ところで覚えてるか・・1/3はいつくだ?」
「エッ・・もしかして前におしえてくれたやつ?」
苺は鞄からメモ帳を取り出すとボールペンで書いた。
『1/3=0.33333・・・・・・』
「今度はこの両辺に3を掛けるんでしょ」言って苺は数式の下にもう一つ数式
を書いた。
『1=0.99999・・・・・』
「小数点以下の9がずっと続く。際限なくずっと9が続いて完全な1には辿り
つかない」苺は言った。
「そうだ。最初にこの数式をみたときも苺はそう言ったんだ。
そして・・辿りつかないこの数式は切ないって言った」
「うん。言った」
「それじゃな、左辺の1から右辺の0.99999・・・・・を引いてみろ」
「え・・?」
「左辺と右辺はイコールで結ばれてるから、その差は0(ゼロ)だろ」
「あっ!」
『0=0.00000・・・・・1』
「ほら。ゼロは無じゃないだろ。
ゼロ・ピリオドの次からゼロが気が遠くなるほど続くけど、その先には必ず1
がある。なっ。ゼロは無じゃない」
「・・・・・・」
「ゼロはスタート地点じゃない、もうなにかが始まってるんだ」
「・・・・・」
「まだ何にも始まってねえってこぼすよりはな、
もう何かはじまってるのかもしれねえぞって思う方がさ・・
気分が楽になるだろ?」
「まだよく分からないけどね・・・先に気分だけ軽くなっちゃった」
「もう一度掌を見てみろ」
苺はじっと掌をみつめたがそこにはやっぱり何もなかった。
源は眠くなったからもう帰れと苺に言った。苺は個室の病室をでるとき「缶コ
ーヒー飲んだらまた戻って来るから眠ってるんだよ」と声をかけた。
源は返事をせず目を閉じたまま右手で拳をつくりすっと上にあげると親指を突き上げる。
苺は笑顔で病室を出て行った。
源の様態が急変したのは三時間後のことだった。
駆けつけた誠、修、明。そして苺が見守るなか源は二度と目を覚まさなかった。
ピッピッピッと鳴っていた心電図の脈の間隔がどんどん長くなりついには止ま
った。定規で線を引いたような心電図は源の時間が止まったと告げていた。
「すみません」頭を下げた三十代の若い医者は誠の居酒屋の常連客で源によくなついていた男だ。
その医者が「えっ・・?」と声をあげた。
誠と苺が源の脇の下をくすぐっていた。「源はふざけてるのかもしれねえ」
「源爺。ふざけてるなら目を開けないと怒るよ。わたし本気で怒るよ」
修と明は慌てて脇腹をくすぐった。若い医者も足の裏を必死にくすぐり泣いて
いた。
「源爺、あんまりふざけるともう口きかないからね!」苺は目に涙をためて頬をくすぐった。
「もういい。もういいよ苺」誠はそう言うと黙った。
手を止めた修と彰は嗚咽をもらしている。
若い医者は諦めきれないように足の裏をくすぐり肩を震わせていた。
苺は源の額と頬を撫でていた。
********
青空に白い煙が昇っていった。秋晴れの上空へ真っ直ぐに昇っていった煙の先
端は雲に届いていた。
「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。
「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。
「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。
「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。
黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。
「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。
「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠
は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」
明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」
見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。
午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。
あの一本気な煙は源だ。
堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの
煙は源だ。四人ともそう感じていた。
眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。
「太くて真っ直ぐな煙が天に昇っていく」
「ロケットを打ち上げた時の煙のようだ」
苺が右手をマイクのように口元に持っていき言った。
「こちらヒューストン。打ち上げは成功だ。
君の旅立ちを祝福する」最後は涙声になっていた。
「アポロ11号で月へ行ったオルドリンが言ったんだ。
『あのでかいロケットを打ち上げる動力は人間の魂だ』って」そう呟いた誠
の声を聞いた苺が続ける。
「源爺の魂が天へ昇って行った・・」
葬祭場に戻るとちょっとした事件(?)が起きた。
火葬釜から出てきた台を見て参列者はざわついた。
台の上には・・何もなかった。
骨どころか灰さへも無い台がそこにあった。
きれいに拭いたキッチンの天板のように何も載っていない金属が窓から射す陽
射しを跳ね返して光っていた。
最初に台が出てきた時、係員は「ええっ」と言ったまま動きを止めた。
参列者はマジックショーの瞬間移動を見たときのように「おお」と声をあげ、
何人かは思わず拍手をしてからバツが悪そうに俯いた。
「おい」誠が三人をうながしてその場を離れ中庭へ出た。
煙突から離れていく太い煙を見て思ったことは四人とも同じだ。
源の身体が燃えて無くなったと思っているヤツはいない。
苺が口を開いた。「源爺が消えた」
「ああ。源の野郎消えやがった」誠の言葉に修が応じた。
「源ちゃん・・本当に空へ飛んでったのかな」
「源ちゃんさあ。釜に入るとき棺の中で右拳の親指を突き上げてたかもしれな
い『行ってくるぜ』って」明がとぼけたことを言うと苺が応じた。
「宇宙飛行士のように・・」
やがて煙が消え空には白い雲だけが残った。
秋の柔らかな陽射しに温められた空気が風になってスーッと髪をすくように吹いた。
「どこに行ったんだ。源の野郎」誠は名残惜しそうにまた空を見上げる。
「なあ」と言って誠は続けた。「今日が源の第二章の始まりかもしれない・・」
いきなりだった。葬祭場のスピーカーから大きな音のかたまりが出てきた。
一瞬なにかが破裂する音かと思ったが・・・それはエレキギターをかき鳴らす
音だった。
キース・リチャーズ独特の気怠いためをつくったリズムのカッティングだ。
ミック・ジャガーのボーカルが曲をぐいぐい引っ張り軽快にドライブした。
ローリング・ストーンズの曲だった。
源の大好きな『スタート・ミー・アップ』だ。苺が小さく叫んだ。
「うん。間違いないね。今日が源爺第二章のスタートなんだ」
「そうだな」「うん」「スタートだ」三人も思いは同じだ。
苺が誇らしげな声で言った。
「こちらヒューストン。こちらヒューストン。打ち上げは成功だ。
君の新しい旅の始まりを我々は心から祝福する」
四人は眩しい陽射しに目を細め上空を見上げて・・笑っていた。
********
それから一週間が過ぎた。
気持ちの良い秋晴れの昼下がり。誠と苺は神社の境内で話していた。
誠はACミランのマフラーを巻いた石の狐に寄りかかり空を見上げていた。
「苺。どうだ。気持ち良いか?」誠は声を張り上げた。
「うん。すごーく気持ちイイ。秋空の奴きれいな青色になって張り切っている」
「そうだな、そんな感じだな。
ところでな苺、オマエと話してると首が痛くなってしょうがねえ。
なあ。もう降りてこい」
「マコちゃん・・それがさ。降り方がよく分かんないんだよね」
誠が見上げる上空で苺は竹箒に跨って浮いていた。
端は雲に届いていた。
「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。
「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。
「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。
「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。
黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。
「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。
「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠
は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」
明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」
見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。
午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。
あの一本気な煙は源だ。
堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの
煙は源だ。四人ともそう感じていた。
眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。
源は自宅の屋根に降り積もった落ち葉を掃き下ろしていたときに屋根から地上
に落下した。すぐに病院に搬送され8階病棟(最上階)に入院したがほどなく
死んだ。そして今は煙になってはるか上空へ昇っている。
最後まで上り下りの激しい人生だった。
*******
苺が十四才の誕生日のときのことだ。父親と母親は「ちょっと出かけてくる」
といつものように言った。年に数回ちょっと出かけてくる両親だった。
数週間から数ヶ月のちょっとだった。一人娘の苺を残してふらりと出かける二
人だった。戻ってきた両親にむかって苺がどこに行って何をしていたかを聞い
ても父と母は「ちょっとね」と言うだけなのもいつものことだった。
『謎は謎のまま残り、新たな謎を生んだ』同じ町内の誠は言った。
誠・・通称マコちゃん六十二才、居酒屋店主でロック歌手、謎の多い不思議な
男だ。不思議な謎男がこう言う謎の両親は昨日まで十三才だった苺の理解をも
ちろん超えていた。
それはもちろん十四才になった今日も。
「今度のはちょっと・・ちょっと長いんだ」父が申し訳なそうに言った
「うん。長いんだよね、これが」母は嬉しそうに言った。
「だから・・・?」苺は両親の間に立ってニコニコ笑ってる男を指さした。
笑ってる男は源。苺の祖父だ。日本中を放浪して「流しの花火師」と「流しの
手品師」をやっていて、年に一度大晦日に帰ってきて正月二日には家を出て行
く源爺だった。マコちゃん同様謎の多い・・なぞなぞ男だ。
苺が十才のときのこと。イチゴを食べてる苺をカメラでバシャバシャ撮りなが
ら「苺の共食い写真だ。こりゃスクープだ」と何が楽しいのかはしゃいでいた
謎の祖父だ。
「これから俺はずっとこの家で苺と一緒に暮らすんだ」源爺は自慢げに言った。
「それじゃ父さんと母さんはずっと帰って来ないってこと?」苺が声を大きく
した。
「ちょっとな・・」両親と源爺は声を揃えて言った。
「・・・・・」
両親は午後の新幹線で出かけると言って中学へ行く苺を玄関で見送った。
苺は家を出て数分歩くと大きな橋のたもとについた。それから橋の欄干に沿っ
て川面を眺めながら歩いた。
「ちょっと・・かあ。でも源爺との二人暮らしがちょっとで済むわけないんだ
よね」
苺が生まれ育った所は市内中央を南北に川幅の大きな川が流れている。その川
を東西に跨ぐように架かる三つの橋がある。北から順に上ノ橋、中ノ橋、下ノ
橋と呼ばれていた。中の橋から東へ数キロメートル行くと昭和の初めから続く
仲町商店街があった。近くに大きなお寺があったためか戦中の空襲の時も焼夷
弾の投下から免れていた。苺の家はこの商店街の中に建っていた。
戦争の空襲から免れ、高度経済成長の波に洗われ小ぎれいになった商店街も、
昭和五十年以降近隣に出現した大きなスーパーマーケットやコンビニに客足を
奪われた。さらには、平成を迎え二十年近くなると郊外に次々と現れた巨大シ
ョッピングモールに壊滅的な打撃を加えられた。巨大ショッピングモールは市
の郊外を巨大な円陣で囲むように建ち・・まるで英国製の羽根なし円形扇風機
が送風の変わりに空気を吸い込むように市内各所の古い商店街から客足を奪っ
た。仲町商店街は地元住民が日々の生活用品を買い、壊れた家電や破れた衣類
の直しを依頼する「(商店街)住民の住民による住民のための」商店街として
皆が支え合ってなんとか成り立っていた。
しかし仲町商店街を覆う空気は意外なことに暢気だった。その暢気さを苺は愛
していた。そして暢気に能天気を上塗りしていたのが・・酒屋の修、文房具屋
の明、居酒屋の誠、そして源の幼馴染み四人だった。中学生にしては早熟な苺
はこの六十代の能天気どもを愛していた。そんな苺でも源と誠の無茶には迷惑
していた。
『無茶はどんどんやる。けどな。無理はしねえ。
無理するのはダセーだけだ』よく分からないことを源は苺に言う。
『三流の大人で一流の男ってことだ』誠も応じて胸を反らした。
仲町商店街と背中合わせに拡がった飲食店街がオリオン横丁だ。
オリオン横丁に誠が一人で切り盛りしている居酒屋があった。客が八人も入れ
ばいっぱいな小さな店で毎晩常連客が賑やかに話していた。店が混雑してくる
と苺も手伝わされた。
「あのさあ。わたしが手伝いに来たのに、マコちゃんがカウンターに座って飲
んでるってさあ・・なんかルール違反だよな」苺が眉間に皺をよせた。
「ルールその1『未成年の飲酒は禁じられています』」誠が笑顔で応じた。
「酒飲みたいなんて言ってない。働きなさいって言ってるの」眉間の皺が深く
なった。
「ルールその2『大人は子供を甘やかさない』」誠の隣に座った源が言った。
「大人は信じられない」やれやれという顔に苺はなった。
「貴方は神を信じますか?と同じくらいに、貴方は大人を信じますか?は出口
の見えない命題だ」源が混ぜっ返した。
「『大人は判ってくれない』フランソワ・トリュフォー」苺が応酬した。
誠は唇の端を曲げて笑うと・・ぼそぼそと低い声で歌うように話し始めた。
「『Don’t trust anyone over 30』よみ人知らず。
1960年代に三十以上の連中を信用するなって言っていたディランやストーン
ズだってもういい爺だ。物わかりの悪い正しい年寄りだ。
子供を甘やかすのは年寄りの悪い癖だ」
「でもミックは若い女に甘い」苺は手厳しい。
「・・・・」「・・・・・」
「源爺は上着のポケットからキャバクラのお姉ちゃんの名刺が出てきた。
マコちゃんは子供のような年齢の女と腕を組んで歩いていた」
苺はたたみかけた。
「年寄りを甘やかすのは子供の悪い癖だ。わたしは良き子供でありたい」
「・・・・・」「・・・・・」
*******
苺が十六才になった夏の宵。
仲町商店街の七夕祭りでのことだ。商店街を通る車道は通行止めにされ歩行者
天国になっている。夜になってやっと吹いてきた風にたくさんの色とりどりの
七夕飾りがゆらゆらと揺れていた。路上にはびっしりと露店が並びそこかしこ
から客引きの声が聞こえてくる。日中の暑気は通りに残り、風は出てきたが大
勢の人出で空気は動かず苺は団扇をひっきりなしに扇ぎながら歩いていた。
『もう暑いよ。盛り過ぎだって。大盛りだって今年の盛夏』
三十分前のことだ。苺は浴衣の着付けに手こずり八つ当たり気味に源に向かっ
て愚痴っていた。『先に行ってるぞ』と源は隣室へ声をかけ、愚痴が怒りに変わ
りそうな苺から逃げるように家を出て行った。
苺は七夕飾りを眺めながら源を探して通り歩いていると奇妙な露店を見つけた。
露店の幟には『言葉堂本舗』と書かれていた。大きな机が一つだけ置かれ、椅
子には男が一人座っていた。標語のような言葉が書かれた紙が机の前に何枚も
貼られていた。道行く人は感心がないのか足を止めずに素通りしていった。
男の話しを立ち止まって熱心に聞いているのは源と誠の二人だった。
男の物売り口上は淀みがなかった。
「言葉堂本舗でございます。
当店が扱っておりますのは、言葉でございます。
『世界は素敵な言葉であふれてる』
当店が取り扱っております言葉は、
名言、きめ台詞、キャッチコピー
短歌、俳句に川柳、どどいつ
自由律詩に壁の落書き、便所の哲学
謳い文句、殺し文句、歌の文句にセロニアス・モンク
心はなやぐ言葉の数々。
『美辞に麗句にお世辞にヨイショ!』
貴方の気持ちをぐいっとアゲてみせましょう。
『羽を持たない心だってな、空を飛ぶことができるんだ』
『そんなことができるの?』
『いいかいお嬢ちゃん。言葉使いのおじさんに出来ないことなんかないんだ』
さあさあ。心浮き立つ言葉の数々。
ユーモアはあるが冷笑はありません。
ウイットはあるが皮肉はありません。
当店は、貴方にお似合いの言葉を探します。
貴方を励ます、貴方に寄り添う、そんな言葉を探します。
言葉ソムリエです。
もしご希望でしたらオリジナル言葉の作成も承ります。
自分にフィットした言葉を呟くと・・・
元気が出ます。
勇気が湧きます。
アイデアが閃きます。
跳躍力が3%伸びます。
風呂あがりに湯冷めしません。
ビールが美味しくなります。
ブラボー。
さてお立ち会い。
手前ここに取りいだしたるは素敵な「言葉」の数々」
男は紙に書かれた古今東西の名言・至言・アフォリズムを次から次へと両手で
掲げて解説を始めた。男の解説を聞きながら「気に入った」とか「その通り」
とか相づちをうっているのは源と誠だった。その大げさなリアクションはどう
見ても露店のサクラだ。しかし二人をよく知る苺には分かる。あれは本気で
感心しているんだ。
言葉堂本舗の男の口上に熱がこもった。
「それでは…ここからは当店オリジナルの科白を。
『すべての男は本末転倒と役立たずの先に存在する』
ほら。気持ちが軽くなるでしょ。男ってのはね。そんなもん。
じたばたしても、それ以上でも以下でもない。
それじゃ次。これは強烈。
『すべての女は慈悲と理不尽のないまぜでできている』
ほら。はなから、男は女に敵わいって分かって気分が楽になるでしょ。
優しくて不合理・・勝てる相手じゃないんだって。うんうん。」
源と誠の二人も「うんうん」と頷いている。
言葉堂本舗のシステムはこうだった。男が客をカウンセリングして客にフィッ
トした言葉を古今東西の名言から選ぶ。もしくは男がオリジナルの言葉を考え
る。それから机の上のパソコンで男が文字をデザインして紙へ印刷する。
「おい。自分で考えた言葉もデザインして印刷してくれるか?」源が声を張り
上げた。
「いいよ。それが希望なら」男は笑顔で頷いた。
すると不敵な笑みを浮かべたのは源の隣に立っていた誠だった。
「俺も自分で考えるぞ!」誠が言うと源は「じゃあ勝負だな」と誠を睨んだ。
苺は口のなかで呟いて立ち去った。
『この二人の男は役立たずの中にだけ存在する』
********
三日間の七夕祭りが終わった翌日の夜。
台所の冷蔵庫のドアを開けた源が「ビールが入ってねえ」と怒鳴った。
「仕方ない。行こう」苺の言葉に「よし行くぜ」と応じて源は笑った。
急ぎ足で誠の居酒屋へ着いた二人は店に入った。早い時間のせいか客は他にい
なかった。カウンターに置いてあるビールの入ったコップは誠のものだろう。
「冷えたビール」「冷えた麦茶」二人はカウンター席に座る前に言った。
誠は手作りの麦茶を冷蔵庫から出してコップに注ぎカウンターに置き、それか
ら瓶ビールの栓を抜きコップと一緒に麦茶の隣に置いた。
誠は注文も聞かずに冷蔵庫からズッキーニを三本取り出して厚めに切った。
フライパンを火にかけオリーブオイルでニンニクを香りが出るまで炒めると、
そこへ切ったズッキーニと手でちぎった鷹の爪を入れニンニクの香りが移った
オリーブオイルを絡めるように炒めた。最後に塩を一振りかけてから皿に盛り
つけカウンターに置いた。
「美味しい。マコちゃんこれ美味しいよ」苺が目を輝かせた。
「・・・マコ、ちょっと厨房借りるぞ」
「なんだよ源?」
「俺の料理ほうが美味い」
「源爺なに張り合ってんの」
「コイツは苺が美味いって言ったとき鼻を鳴らしたんだ。
『当然だ』って言うように」
「普通鳴らさないか・・鼻。当然だっていうときゃ鳴らすだろ鼻を」
「こいつはガキの頃から謙虚じゃねえんだ」
「どの口が言う?」
「あのな。人間は謙虚が大事なんだ。『実るほど頭を垂れる稲穂かな』だ。
それをなんだ、料理を褒めてもらって鼻ふん当然ってのは」
「あのな。実って頭下げられちゃな・・
『実ってねえのにふんぞり返っててすみません』って恐縮してる不憫な稲穂
が可哀想だろうよ」
「はあ?なんだその屁理屈は。
だいたいな胡瓜の油炒めなんてな、河童も喰わねえよ」
「ズッキーニ。これは胡瓜じゃないの。ズッキーニ」
「なんだ苺。オマエがマコに味方するってどういいうことだ?」
「へへん。ズッキーニはな胡瓜の仲間だ」誠が得意げに言った。
「ズッキーニは胡瓜に似てるけどカボチャの仲間」
「なんだよ。苺はどっちの味方なんだよ?」
「どっちの味方でもないよ。だいたいね、六十過ぎのいい大人がさあ・・・
高校一年女子に向かって『どっちの味方だ?』ってさあ。
恥ずかしくないわけ?」
「全然」「何が?」源と誠は同時に答えた。
「だからね。孫みたいな年の子供の前でね・・実際隣の男の孫だしね。
マコちゃんは孫同然のわたしに、源爺は孫そのもののわたしにさ、
『どっちの味方だ?』とか大きな声出してさ。
恥ずかしくないのって」
「ない」「ない」源と誠はまた同時に答えた。
「・・・・・」
二人の口論を無視して麦茶を飲みながらテレビの野球中継を見ていた苺は
テレビの横の壁にかけてあった色紙に目がいった。
「なにアレ?」
「ん・・?」
「テレビの横のアレはなんなのって聞いてんの」
「あっ。あれか。あれはほら・・言葉堂本舗で作った色紙だ」
苺の声につられて色紙をみた源がゲラゲラ笑い出した。
「だーかーら。なんなのアレって聞いてんの。
あの言葉はなんなのって、わたしは聞いてるの」
「人間はな、引込みじあんはいけねえなって…」
「・・・・・」
「自分の得意技をバンバン出してドカドカ賑やかにいくぞって」
「・・・・・」
「もう出し惜しみなしだぞって」
「・・・・・・」
壁に掛かっていた色紙には『能ある鷹の爪』と書いてあった。
顔を真っ赤にして笑っていた源は鞄から色紙を取り出すとカウンターの上に置
いた。色紙の文字を読んだ誠は飲んでいたビールを吹き出してゲラゲラ笑い出
した。苺は口の中の麦茶を飲み下すと大きな溜め息を吐いた。
『自我自賛』と色紙には書いてあった。
「自分の精神をさ・・俺のハートをさ、自ら褒めるんだ。
もっと自信をもって堂々と生きようぜってな・・」
苺が源の話しを途中で切った。
「あのさ。二人とも子供の頃から謙虚じゃないってのが今よーく分かった。
あのね二人はね仲良しじゃない同じなんだ。
源爺とマコちゃんはね精神的双生児だよ」
「・・・・・」「・・・・・」
「オレがオレがの自己主張ばっかのオレオレ色紙だ」
ふいに店の戸が開く音が聞こえた。入ってきたのは言葉堂本舗の男だった。
顎と首の区別かつかないくらい太った、映画「紅の豚」のポルコ・ロッソのよ
うな男だった。太った風貌だけじゃない。白い麻の三つ揃いスーツに赤いネク
タイを締め丸い黒サングラスにパナマ帽を被ったところはポルコそのものだっ
た。男はカウンター席に座わりパナマ帽をとりサングラスを外して禿頭を右手
で掻いた。源は慌てて色紙を鞄にしまい、誠はそそくさと色紙を壁から外した。
照れる・恥ずかしがる心は二人にもあることを確認して苺は笑った。
「ミントジュレップをくれ。砂糖は少なめに。控えてるんだ」男は言ってゲラ
ゲラ笑った。
誠はグラスを出し砂糖とソーダを入れ、スプーンで潰して香りを出したミント
を加えてよくかき混ぜた。布でくるんだ氷を麺棒で叩いて砕いた。バーボンを
注いだグラスに砕いた氷を入れ手早くステアしてカウンターに置いた。
「面白い商売だな」誠は瓶ごとビールを飲みながら言った。
「まあな。人間の言葉に興味があるんだ。
人を傷つけもするが救うこともする言葉にな。
それと美味い酒が好きなんだ。これは良い出来のミントジュレップだ」
男が源と苺の皿を見て、オレにも同じものをくれというので誠は作ってだした。
「それはズッキーニだ。胡瓜じゃないぞ」源が自慢気に言った。
「知ってるけど」男は怪訝な顔で源に頷いてから苺に話しかけた。
「お嬢ちゃん。アンタは幸せだ。この二人は良い男たちだ。
シンプルな言葉を吐くシンプルな男たちだ」
源と誠はしまった色紙を出そうとした。
「もう。出さなくていい。
この二人はね・・複雑が苦手なだけなの」
「お嬢ちゃん。言葉も音楽も生き方も・・シンプルが一番だぜ」
「いい。『ここではあなたのお国より、人生がもうちょっと複雑なの』」
苺は映画「紅の豚」のジーナの科白をさらりと言った。
男はそれを聞いてゲラゲラ笑って言った。
「『飛ばねえ豚は、ただの豚だ』
お嬢ちゃんはいつか・・空を飛ぶかもしれない」
「ええっ。空を飛ぶ前に豚になっちゃうのは嫌だ」
源が満面の笑顔で男に話しかけた。
「アンタ良いヤツだな。
ジブリの映画を観ろ!これが、オレの教育方針だ」
「ロックを聴け!苺にいつも言ってるんだ」誠も負けずに言った。
「なんてシンプルな教育だ。お嬢ちゃんはやっぱり幸せものだ」男のゲラゲラ
笑いは止まらなかった。
「アンタ手品が得意なんだってな」笑いやむと男は隣の源に言った。
「ん・・。まあな」
男は「こんなのはどうだ」と言うと、ポケットから五百円硬貨を出してカウン
ターの上に置いた。そして硬貨の上に空のグラスを置いた。
と、その瞬間に硬貨はグラスの中へ移動した。しかも硬貨は裏返っていた。
誠と苺が感心して「ほう」と言うと、男は照れくさそうに笑った。
五分後に男は会計をして店を出て行った。
「見事な手品だった。でもあれくらいはなあ・・」誠の言葉に苺がかぶせた。
「源爺の手品のほうがもっと凄いよ」
男の手品を見てから黙っていた源が話し始めた。
「アイツのは手品じゃねえ」
「はあ・・じゃあなんだって言うんだ?」
「アイツは種も仕掛けも使ってなかった。
あれはトリックなしのマジックなんだ・・と思う。
魔法っていうかさ・・」
「えっ?」苺と誠が同時に声をあげたが源は答えず誠に言った。
「マコ。さっきしまった色紙を出してみろ」
誠は色紙を見て声をあげた「おお!」
色紙には手書きの文字が書き加えられていた「ロック」と。
源が出した色紙には「ジブリ」と書かれていた。
二枚の色紙どちらにも手書きのアルファベットが書いてあった「M」と。
「凄い!」苺が歓声をあげ、誠が「やるじぇねえか」と笑った。
源はまた黙ってしまった。
店を出た源と苺はオリオン横丁を並んで歩いた。
「苺。空を見ろ」言うと源は空にかかる月を頭上に伸ばした右の掌で覆った。
「いいか・・見てろよ」
源の右掌がスーッと前方に動くと頭上の月が消え、右掌を横に動かすとそこに
月が現れた。
「あのな。今苺が見たのはな・・実はトリックなしのマジックなんだ」
「・・・・・」
********
苺十六才、秋の夜。
食卓で苺は源がつくったカレーを食べていた。向かいに座った源は福神漬けと
ラッキョでビールを飲んでいた。
苺が浮かない顔でカレーを食べているのが気になって誠が聞いた。
「どうした・・まずいか?」
「ううん。ちょっと辛いけど大丈夫・・美味しい」
食べ終わると苺は学校の出来事を話した。
今日のクラスルームは映画のディスカッションだった。教師から指名された苺
が自分の推薦する映画について語り質疑に応答し、以後はフリートークとなった。
苺の推薦映画は「風の谷のナウシカ」だった。
担任の男性教師は熱烈な宮﨑駿ファンだ。
プロジェクターにつないだラップトップ・パソコンからキー・シーンを選んで
上映しながらプレゼンテンショーンした。
苺が話すのを中断し映像を流していたときのことだ。
数人の男子生徒が小声だがこう言ったのが苺の耳に届いた。
「ウゼー」
最初にナウシカを観たのが何歳なのか記憶がないくらいに幼い頃から観てきて、
共感し、楽しんできた苺は動揺した。
教師は目にうっすらと涙をためた。
「あのな苺。そいつがウゼーって思ったんなら、映画はそいつに届いたんだ。
けどな・・化学反応がおきなかったんだな」
「・・・・・」
「俺はこのカレーに隠し味としてニンニク、バター、唐辛子、砂糖、和風だし
を入れた。いいか。いくら隠し味を入れても苺の身体や心と化学反応しなか
ったらオマエはこのカレーを美味しいと感じない」
「味覚は個人によって違う」
「まあ・・本当に美味しいものは多くの人にとっても美味しいんだけどな」
「うん」
「それとな。映像は個人の心理も影響するんだ」
「・・・・・」
「人は見たいモノを見る。人は見たいように見る。」
「うん?」
「そして。人は見たいモノが見える。聞きたいモノが聞こえる」
「うん・・?」
「『心理のバイアス(偏向)』っていうんだけどな。
物事をネガティブに悲観的に捉える傾向の人っているだろ。
逆に何でも楽観的にポジティブに考える人もいるよな」
「いるね」
「いいか。映画の戦闘シーンでは視聴者の感情が揺れるだろ。
主人公が敵に勝つ爽快感や、戦闘の虚無感や、暴力の愚かさや・・
それぞれ個人によって違うだろ」
「うんうん。それなら分かる」
「それと個々とは別に多くの人に共通する心理のバイアスもあるんだ」
「偏向が共通するってある?」
「いいか。苺はこのカレーを食べたときどんな味に感じた?」
「カレー味だよ。そりゃカレーだもん」
「つまり多くの人が期待するカレー味にすると美味しく感じる。
カレーと感じたいカレーを食べると満足する。
甘いカレーは・・辛いのが苦手な人でもカレー味としては満足しない」
「なるほどね!」
「手品はこの多くの人に共通する心理バイアスをついてるんだ。
多くの人が見たいモノを見たいように見せてるのが手品だ。
多くの人は見たいようにみてるだけ。
つまり多くの人はトリックに気づきたくないんだ」
「ふんふん」
「詐欺は個人の心理バイアスに応じて攻めると騙せる。
電話のオレオレ詐欺は元々悲観的な心理バイアスを持つ人の不安感を大きく
煽って騙すんだ。だから逆に騙されない人もいる」
「カレー好きのわたしはカレカレ詐欺に気をつけないと」
源はビールを飲みながら苺に紙と鉛筆を持ってくるように言った。
「人は見たいモノを見る・・とは違うんだけどな。
1/3はいくつだ?紙に書いてみろ」
そんなの計算しなくても分かると苺は言ったが、源はいいから書けと言った。
苺は紙に書いて源にみせた。
『1/3=0.33333・・・・・・』
源はビールを一口飲むと「それじゃ。両辺に3を掛けてみろ。ほら」と言った。
「ん・・?」
「ほら」
「あっ!」苺は小さく叫んだ。
『1=0.99999・・・・・』
「1は1じゃないの?」
「数学的なことは俺には分からないがな。
1は1じゃない。この式じゃ1は0.99999・・・・・なんだ」
「ふーん。不思議な感じ」
「いいか。1は数字だけど・・概念でもある。単一とか孤立とか。
1はイメージでもある。
1とか単一とか聞いた人は誰もさ。
『0.99999・・・・・』をイメージしないだろ」
「人はイメージしたいようにイメージする・・とか?」
「いや。俺が言いたいのはな。
1がだぞ、誰だって単一とイメージしてる1だって複雑なんだ。
だから世界は面白いんだ」
「そうかなあ・・『1=0.99999・・・・・』ってさあ。
小数点以下の9がずっと続くでしょ。際限なく続くでしょ。
いつまでたっても完全な1には辿り着かない。
なんか切ないなあ」
「そうか。俺はそう思わないけどな。
俺はな・・ちょっと嬉しくなるんだ」
「・・・・・?」
********
苺十七才、春の宵。
午後から商店街に近い公園で始まった町内会の花見は夕方にははねて、いつも
のメンバーで誠の居酒屋に集まった。修、明、源、苺がカウンター席に座り乾
杯をした。厨房に入った誠はツブ貝と胡瓜を切って三杯酢で和えて出し、木串
に刺した肉を焼いた。
修が酔いのまわった顔で焼き鳥を囓りながら「半人半獣のケンタウロスってい
るだろ?」と言った。
「いねえ」誠はにべもなかった。
修が続けた「上半身が人間で下半身が馬のやつ」
「だから、いねえんだ。ケンタウロスは神話だ」
修はコップ酒を飲みながら話を止めない「なあ。半魚人っているだろ?」
「それも、いねえ」誠は言い放った。
修が続けた「半魚人ってよ、半分人間で半分魚ってことだろ。
だけどありゃ、どう見ても人間でも魚でもねえよな」
「だから、いねえんだ。半魚人はアメリカの怪奇映画の作りもんだ」
「えっ。そうなの?」明が驚いた顔をして
「うちにフィギュアがあるんだけど・・」と怪訝な顔をして呟いた。
「あのなあ。なんでもかんでも信じるな。電話がきたらどうする?」誠が言う。
「爺ちゃん・・オレオレ半魚人」と言って源が笑った。
「オレオレ半漁人詐欺だ。気をつけないと」苺がクスクス笑った。
「じゃあ。こんなのはどうだ。信じるか?」源が話し始めた。
「太陽は実は移動している。しかも移動速度は時速7万キロメートルだ。
どうしてかって?宇宙全体は加速膨張してるだろ。その膨張につれて太陽も移
動している。だから太陽の周囲を公転する惑星は円運動じゃなくてさ、円運動
しながら前へ進んでるんだ。だから惑星は螺旋状に回転しながら進んでる。
つまり地球も螺旋回転しながら太陽と一緒に時速時速7万キロメートルで進ん
でるんだ」
「時速7万キロメートルだあ?」明は大きな声で叫んだ。
「地球は螺旋回転しながら宇宙を進んでるって・・」修の声はしぼんだ。
カウンターの内側に立っていた誠は「うっ」と唸ると厨房の柱に両手でつかま
り両足を踏ん張った。
修は椅子に座ったままカウンターの出っ張りを両手で握った。
「この椅子はシートベルトないよなあ」明は不安げな顔をした。
源と苺はジェットコースターに乗った客のように両手をこれみよがしに頭上に
挙げて笑った。
「いいか。光の速度は時速108億キロメートル・・」源は誠から電卓を借りて計算し始めた。
「うん。太陽の進行する時速7万キロメートルは光速の約1/1億5千万だな。
そして・・宇宙の膨張速度は光速の3倍なんだ。だからさ、時速7万キロメ
ートルなんて微々たるもんだ」
三人の男はホッと安堵の息をはいた。
「でな」源がまた話し始めた。
「螺旋回転で進行してる地球の遠心力と太陽の引力がつりあってるから俺たち
はシートベルトがいらないわけだ。けどな。太陽が膨張して引力が大きくなっ
たら地球は太陽に・・」
「太陽に・・?」三人は同時に言って源の言葉を待った。
「太陽に地球は突っ込む。
だからな。空に見える太陽が大きくなったらヤバいんだ」
「あっ、さっき見た夕陽が大きかった」言うと苺はペロッと舌を出して笑った。
三人の男は同時にギャッと言ってテーブルをつかんで足を踏ん張った。
「源ちゃんの話しは半魚人より怖い」修が言った。
自分も怖がったのに照れ笑いを浮かべて誠が言った「太陽が簡単に膨張するかよ。
なんでもすぐに信じると電話がかかってくるぞ」
「爺ちゃん・・オレオレ太陽、膨張して太っちゃってさ」と言って源が笑った。
「オレオレ太陽詐欺だ。六十過ぎたら気をつけないと」苺がクスクス笑った。
苺はマコちゃんが煎れた緑茶を飲みながら山菜の天麩羅を食べた。
源爺、マコちゃん、明おじさん、修くん。気持ちの良い幼なじみの男たち。
四人がいるからわたしは寂しくない。
四人はわたしのシートベルトだ。
誠はテレキャスターをアンプにつながずに弾き始めた。
ローリング・ストーンズ『スタート・ミー・アップ』のイントロだ。
キースのように気怠げにためをつくったリズムのカッティングだ。
「地球はロック&ロールだな。
キースは言ったんだ。
『ロックをやるバンドはくさるほどいる。
だけどな。ロールしてる連中が見あたらねえ』ってな。
地球は螺旋状にロールしてる本物のロックなんだな」
苺は思った『マコちゃんはシートベルトじゃなくて・・アクセルだ』
誠が突然大きな声をだした「あっ。俺な、中学のとき神社の宵宮でな・・・
テキ屋の兄ちゃんが夜店で半漁人を売ってたの見たことあるぞ」
苺は思った『源爺はシートベルトじゃない。効きの悪いブレーキだ』
源が誠へ話しかけた。
「今日なネットで『正義の味方』を検索したら俺がでてきたよ」
「奇遇だな」
「何が?」
「俺も『正義の味方』を検索したら俺がでてきたよ」
ふいにマコちゃんと源爺が苺に顔を向けるとニッと笑って自慢げに言った。
「俺たち最強だろ」
苺は声に出さずに口の中で呟いた。
『アクセルと効きの悪いブレーキのコンビって・・最悪だ』
********
苺十八才、夏の日盛りの午後。
市内中央を流れる大きな川に架かった橋のたもとの川原へ降りるコンクリート
の幅広の階段に苺と源は座っていた。街路樹が日陰をつくりコンクリートの階
段は座ってもそれほど熱くなかった。
源は『CAT or DIE』(猫さもなくば死を)とプリントされたTシャツを着ていた。
苺のTシャツには『NO CAT NO LIFE』(猫がいなきゃ人生じゃない)とプリ
ントされていた。
みんなが暮らす仲町商店街とオリオン横丁の界隈には「御稲荷さん」と呼ばれ
て親しまれている小さな神社がある。神主もいない小さな社と狐の石像が一体
だけの、由緒や縁起を知る人間は誰一人いない神社だった。
小さな境内にはベンチが置いてあって、そこは休憩したり日向ぼっこしたりす
る場所になっていた。
石の狐は右前足を石の玉の上に乗せている。狐の首にはイタリアACミランの
マフラーが巻かれていた。マフラーを巻いたのは誠だ。
「あの凛々しい狐顔はバレージだ。ACミランのフランコ・バレージだ。
右足をサッカーボールに乗っけてるんだから間違いない。
センター・バックのバレージがこの町内を守ってくれてるんだぜ。
チャオ、バレージ!」
その石像は狐顔の人間ではなく狐顔の狐だったが誠は「あれはバレージだ」
と言って譲らなかった。
その小さな神社の境内にはいつも十五匹くらいの野良猫が出入りしていた。
仲町商店街とオリオン横丁の連中は猫好きなのか無頓着なのか、それが
いつもの風景なんだと思ってるのか横丁の路地や神社にいる野良猫を気にしなかった。
いやむしろ可愛がってる連中のほうが多かった。
その野良猫たちのうち数匹が横丁から出て道路を挟んだ向こう側の住宅街に出入りし始めた。
住人の何人かは道路や壁が汚れると市役所へ苦情をいった。
すると市役所は野良猫排除の行政方針を出した。なんでもかんでもクリーン好
きの役人のやりそうなことだった。
猫好きの苺は「我儘だけど良い連中じゃないか」と怒った。
同じく猫好きの源は「権力の横暴だ。住民票を持たない猫に市役所が介入する
とはどういう料簡だ」と怒った。
「権力」という言葉に過剰に反応する「反権力・反骨」が信条の誠も怒った。
修と明もつられて・・・怒った。
猫排除反対の署名を町内で集めて市役所に持っていったが対応した役人は「検
討させて頂きます」と、明らかに検討する気のない顔つきと尊大さで答えた。
苺は「里親を探そう。SNSで呼びかけよう」と提案したが源が反対した。
「野良猫はフリーランスが信条だ。連中は誰にもどこにも属さない。
どこへ行くのもどんな夢をみるのも自由だ」路地に寝そべる猫を見て源が続
けた「やつらの自由さかげんを見ろ。俺は生まれ変わったら野良猫になる」
「源爺の自由とおおらかさを野良猫も讃えてるよ」苺が笑った。
誠は『反骨音頭』というレゲエ・リズムの曲を作った。ほどよく歪んだ音を出
すテレキャスターをかき鳴らし「野良猫排除反対集会」で歌った。
しかしその歌は野良猫排除反対を訴えるというより誠の反権力・反骨の心情を
歌ったものだった。「でも曲の出来は良いよ」苺が拳の親指を突き上げて笑った。
そろいのTシャツを着たみんなが踊っていた。
「マコちゃんのしゃがれてるけど伸びのある声イイよね」苺が笑顔で言った。
『長いものには巻かれない それ
多数決には屈しない それ
きれい事には騙されねえ それ
それそれそれそれ
反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう
偉いヤツには屈しない それ
大樹の陰には近寄らねえ それ
ウマイ話は嘘だらけ それ
それそれそれそれ
反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう
背中を丸めて歩かない 反れ
猫背の野良にも注意する 反れ
重い荷物はしんどいぜ それ
登り坂はきついけど それ
坂の上には雲がある それ
それそれそれそれ
反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう』
その日は午前十時から「野良猫排除派」と「野良猫容認派」の意見交換会が公
民館で行われた。お互いの意見は平行線のまま交じらず、互いの胸に届かず、
当然化学反応も起こさず、落としどころもないまま会は正午前に散会した。
源と苺は野良猫排除派の論理に呆れ、役所の事なかれ主義に腹が立ち怒りで頭
も身体も火照ってしまったので冷やし中華とかき氷を食べた。
食堂を出て歩いた二人は二十分後には川原へ降りる階段に座って話した。
「苺はいくつになった?」
「十八才。そろそろ十代も終わる。
さよなら十代、こんにちは二十代・・」
「さよなら讃岐うどん、こんにちは長崎ちゃんぽん」
「十代と二十代はそんなに違わないでしょ?
こんにちは名古屋きしめん・・くらいかな」
「覚悟しろ、かなり違う。期待しろ、かなり面白い」
「源爺の二十代はどんなだった?」
「青春だ」
「何才までが青春だった?」
「俺は小学校に入学して以来今までずっと青春だ」
「ギネス青春記録だ」
「苺は今まで会った人よりもっと多くの人に出会う。
いろんな考えやいろんな思いに出会う。
それは。時には自分とは違う意見だったりする」
「今日も自分と違う意見の人たちに会ったもんね」
「そうだ。俺たちと向こうの連中の意見は違った」
「役所はどうするんだろうね?やっぱ排除かな」
「排除だろうな。まあ。その前に野良猫の救済計画をたてよう」
「うんうん。なんとか救けよう。
それにしたって排除だなんてね。
あれだね。正義はたいてい負けるって本当だね」
「『ヒーローはどこにでもいる』ってバッドマンは言ったけどな・・」
「ああ。『ダークナイト・ライジング』のあの科白ね。
『ヒーローはどこにでもいる。
それは上着を少年にかけ、世界の終わりではないと励ますような男だ』」
「ヒーローはどこにでもなんかいない。
ゴートン刑事はあの映画の重要な登場人物だ」
「どこにもなんている人間じゃない」
「まあ。ヒーローはどこにもなんかいないってことだ。
だけど。
正義はどこにでもあるんだ」
「・・・?」
「いいか苺。
正義も不義も。善も悪も。その時代とか、個人の立ち位置や都合で変わる。
だから・・正義も善もどこにでもごろごろある。
実際なにが正義でどれが善なのかはよくわからないことのほうが多い」
「ややこしくって困ったもんだ」
「例えばグリーン・パラドックスだ」
「なにそれ?」
「ヨーロッパの或る国では脱原発へ舵を切り再生可能エネルギーでの
発電量を増やした」
「いいねえ」
「当然電力量は高騰した。だから企業は安い電力を求めて隣国へ工場を移転し
た。すると隣国は火力発電を増やし大気汚染が悪化した」
「えー、良くないじゃん」
「だけど隣国は雇用が増えGDPは上昇した」
「うーん難しい。世界はパラドックスに満ちている」
「一難去ってまた一難だ」
「さよなら讃岐うどん、こんにちは長崎ちゃんぽん・・だ」
「どっちも美味しいから俺はウエルカムだ」
「わたしもどっちも好きだ」
「だからな苺。よーく考えてな、そして思い切ってな。
ときには物事を善悪で判断しないで好きか嫌いで判断したっていいんだ。
面白いか面白くないかで判断するのだって場合によっちゃな・・・ありだ」
「うん」
「大事なのは自分の判断に責任をもつことだ」
「うん」
二人は立ち上がり階段を降りて川原に立った。陽射しが川面で跳ね踊っていた。
苺が顔を源に向けて聞いてきた。
「どうして源爺はわたしの前ではいつも笑ってるの?」
「いつも笑ってるか俺?」
「そうだよ。いつでも笑ってる。
それってさ。もしかしてさ。わたしの前じゃかっこつけてるわけ?」
「大人が笑ってればな・・子供は伸び伸びするんだ。
やせ我慢でもな、大人がかっこつけてれば・・子供だって踏ん張るんだ」
「・・ありがとね。源爺」
「俺は苺が好きだ。苺が面白い。だから苺は俺にとって善で正義だ」
「わたしは源爺の善で正義・・」
「もちろん俺は苺の味方だ。
つまり。俺は正義の味方だ」
「ふふっ」
「夏の午後ヒーローは川原に立っていた。
それは少女に、世界の終わりではないと励ますような男だ」
「その男は太陽が膨張し世界は終わると友人を騙した男だ」
「・・・・・」
********
苺十八才、秋の昼下がり。
柔らかな黄金色の陽射しがあたりに降りそそいでいた。
家の縁側に座って本を読んでいるとガサッと音がして大量の落ち葉が庭へ落ち
てきた。何事かと庭に降りて上を見上げると二階の屋根に立った源が竹箒で落
ち葉を掃いていた。隣の家は古い大きなお屋敷で、そこの庭の落葉樹から大量
の落ち葉が苺の家の屋根に降り積もり時に雨樋を塞いでしまう。それで時々源
は屋根に登って落ち葉を掃いた。
まあ面倒くさいけどな、隣にあんな立派な樹があるから紅葉を楽しめるんだし
な、と源は落ち葉を気にしてなかった。
源は庭に立っている苺へ屋根から声をかけた。
「おい。葉っぱを集めろ。焼き芋しよう。銀杏も焼こう。ビール飲もう」
「焼きビールは美味しくない」
「なに言ってる、ビールは焼かない」
「ビール解禁前十八才女子の前で美味そうにビールを飲むヤツへの罰だ。
焼きビールを飲ませてやる」
「・・・・・」
源は落ち葉払いが終わったのか手を動かさなくなった。じっと下を見ていた。
「源爺。竹箒を股に挟んで何やってんの?
屋根の端に立ってちゃ危ないって。落ちても知らないよ」
「ひょいとな・・飛ぼうかと思ってな」
「何言ってるの?空中浮遊のマジックなんか今やらなくていいから。
失敗したらどうするの・・ねえ降りなさいよ」
「しばらくやってねえからなあ・・」
「竹箒股に挟んで何をブツブツ言ってんの?
そんなことして飛べるわけないでしょ。魔法使いじゃないんだから」
急に吹いた風が鳴らした葉音に源の声はかき消され苺の耳には届かなかった。
「あのなあ。俺は・・実は・・・・・」
源は一旦屋根のてっぺんまで昇ると振り返り下をみた。ふうっと息を吐いた。
「源爺。何やってんの!」
源は竹箒を股に挟んだまま屋根の斜面を駆け下りた。
そのまま助走し屋根の先端から足を離した。
「あれ?」
なさけない声を出して源はそのまま庭に落下した。
苺が集めていた落ち葉の山へ激突して源は仰向けになった。衝撃で辺りへ飛び
散った紅色と黄色の落ち葉が目の前を舞った。日差しで葉脈が透けて見える葉
の群舞が綺麗で一瞬見とれたがあまりの痛さに顔をしかめた。
「源爺ぃ。なにやってんのお!」
落ち葉がクッションになったが衝撃を完全に吸収されたわけじゃなかった。
源の足は外側へ変な角度で曲がっていた。その足を見た苺は小さく悲鳴をあげ
泣き顔になった。源は仰向けのまま苺を見上げて言った。
「おい。落ち着け苺。あのな。この足だけどな。
チャールストン踊ってるみたいだろ?」
苺は怒った顔でクスリとも笑わなかった。
源は苦痛に顔を歪めたまま恥ずかしそうに笑った。
救急車で搬送された源はそのまま入院となった。
苺は担当医から説明を受け、病室に戻ると診断書を源に見せた。
「『両側大腿骨複雑骨折』ってなんだ?」誠は興味なさそうに言った。
「中華料理の名前みたいだ。
甘酢あんかけがのって出てきそうだ」と苺は困った顔をした。
「びっくりさせたな苺。
ちょいと油断するとな電線にとまってる雀だって落ちるかもしれないんだ」
「『猿も木から落ちる』ってこと?」
「『弘法も筆に謝る』だな」
「なんなのそれ。ふざけないでちゃんと謝りなさいよ」
源のベッドの上半身部分はを斜めに起き、両足はギプスで固定されている。
ベッドサイドの椅子に座る苺に右手を握らせ、源はその上に自分の右掌を数秒
間乗せて離した。
ほら手を開いてみろと言われた苺は、なんの手品かと思い掌を広げたがそこに
は何もなかった。
「なんにも無いけど・・」と苺は言った。
「そうだな。なんにも無いな」
苺が怪訝な顔をすると源が話し始めた。
「ところで覚えてるか・・1/3はいつくだ?」
「エッ・・もしかして前におしえてくれたやつ?」
苺は鞄からメモ帳を取り出すとボールペンで書いた。
『1/3=0.33333・・・・・・』
「今度はこの両辺に3を掛けるんでしょ」言って苺は数式の下にもう一つ数式
を書いた。
『1=0.99999・・・・・』
「小数点以下の9がずっと続く。際限なくずっと9が続いて完全な1には辿り
つかない」苺は言った。
「そうだ。最初にこの数式をみたときも苺はそう言ったんだ。
そして・・辿りつかないこの数式は切ないって言った」
「うん。言った」
「それじゃな、左辺の1から右辺の0.99999・・・・・を引いてみろ」
「え・・?」
「左辺と右辺はイコールで結ばれてるから、その差は0(ゼロ)だろ」
「あっ!」
『0=0.00000・・・・・1』
「ほら。ゼロは無じゃないだろ。
ゼロ・ピリオドの次からゼロが気が遠くなるほど続くけど、その先には必ず1
がある。なっ。ゼロは無じゃない」
「・・・・・・」
「ゼロはスタート地点じゃない、もうなにかが始まってるんだ」
「・・・・・」
「まだ何にも始まってねえってこぼすよりはな、
もう何かはじまってるのかもしれねえぞって思う方がさ・・
気分が楽になるだろ?」
「まだよく分からないけどね・・・先に気分だけ軽くなっちゃった」
「もう一度掌を見てみろ」
苺はじっと掌をみつめたがそこにはやっぱり何もなかった。
源は眠くなったからもう帰れと苺に言った。苺は個室の病室をでるとき「缶コ
ーヒー飲んだらまた戻って来るから眠ってるんだよ」と声をかけた。
源は返事をせず目を閉じたまま右手で拳をつくりすっと上にあげると親指を突き上げる。
苺は笑顔で病室を出て行った。
源の様態が急変したのは三時間後のことだった。
駆けつけた誠、修、明。そして苺が見守るなか源は二度と目を覚まさなかった。
ピッピッピッと鳴っていた心電図の脈の間隔がどんどん長くなりついには止ま
った。定規で線を引いたような心電図は源の時間が止まったと告げていた。
「すみません」頭を下げた三十代の若い医者は誠の居酒屋の常連客で源によくなついていた男だ。
その医者が「えっ・・?」と声をあげた。
誠と苺が源の脇の下をくすぐっていた。「源はふざけてるのかもしれねえ」
「源爺。ふざけてるなら目を開けないと怒るよ。わたし本気で怒るよ」
修と明は慌てて脇腹をくすぐった。若い医者も足の裏を必死にくすぐり泣いて
いた。
「源爺、あんまりふざけるともう口きかないからね!」苺は目に涙をためて頬をくすぐった。
「もういい。もういいよ苺」誠はそう言うと黙った。
手を止めた修と彰は嗚咽をもらしている。
若い医者は諦めきれないように足の裏をくすぐり肩を震わせていた。
苺は源の額と頬を撫でていた。
********
青空に白い煙が昇っていった。秋晴れの上空へ真っ直ぐに昇っていった煙の先
端は雲に届いていた。
「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。
「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。
「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。
「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。
黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。
「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。
「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠
は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」
明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」
見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。
午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。
あの一本気な煙は源だ。
堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの
煙は源だ。四人ともそう感じていた。
眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。
「太くて真っ直ぐな煙が天に昇っていく」
「ロケットを打ち上げた時の煙のようだ」
苺が右手をマイクのように口元に持っていき言った。
「こちらヒューストン。打ち上げは成功だ。
君の旅立ちを祝福する」最後は涙声になっていた。
「アポロ11号で月へ行ったオルドリンが言ったんだ。
『あのでかいロケットを打ち上げる動力は人間の魂だ』って」そう呟いた誠
の声を聞いた苺が続ける。
「源爺の魂が天へ昇って行った・・」
葬祭場に戻るとちょっとした事件(?)が起きた。
火葬釜から出てきた台を見て参列者はざわついた。
台の上には・・何もなかった。
骨どころか灰さへも無い台がそこにあった。
きれいに拭いたキッチンの天板のように何も載っていない金属が窓から射す陽
射しを跳ね返して光っていた。
最初に台が出てきた時、係員は「ええっ」と言ったまま動きを止めた。
参列者はマジックショーの瞬間移動を見たときのように「おお」と声をあげ、
何人かは思わず拍手をしてからバツが悪そうに俯いた。
「おい」誠が三人をうながしてその場を離れ中庭へ出た。
煙突から離れていく太い煙を見て思ったことは四人とも同じだ。
源の身体が燃えて無くなったと思っているヤツはいない。
苺が口を開いた。「源爺が消えた」
「ああ。源の野郎消えやがった」誠の言葉に修が応じた。
「源ちゃん・・本当に空へ飛んでったのかな」
「源ちゃんさあ。釜に入るとき棺の中で右拳の親指を突き上げてたかもしれな
い『行ってくるぜ』って」明がとぼけたことを言うと苺が応じた。
「宇宙飛行士のように・・」
やがて煙が消え空には白い雲だけが残った。
秋の柔らかな陽射しに温められた空気が風になってスーッと髪をすくように吹いた。
「どこに行ったんだ。源の野郎」誠は名残惜しそうにまた空を見上げる。
「なあ」と言って誠は続けた。「今日が源の第二章の始まりかもしれない・・」
いきなりだった。葬祭場のスピーカーから大きな音のかたまりが出てきた。
一瞬なにかが破裂する音かと思ったが・・・それはエレキギターをかき鳴らす
音だった。
キース・リチャーズ独特の気怠いためをつくったリズムのカッティングだ。
ミック・ジャガーのボーカルが曲をぐいぐい引っ張り軽快にドライブした。
ローリング・ストーンズの曲だった。
源の大好きな『スタート・ミー・アップ』だ。苺が小さく叫んだ。
「うん。間違いないね。今日が源爺第二章のスタートなんだ」
「そうだな」「うん」「スタートだ」三人も思いは同じだ。
苺が誇らしげな声で言った。
「こちらヒューストン。こちらヒューストン。打ち上げは成功だ。
君の新しい旅の始まりを我々は心から祝福する」
四人は眩しい陽射しに目を細め上空を見上げて・・笑っていた。
********
それから一週間が過ぎた。
気持ちの良い秋晴れの昼下がり。誠と苺は神社の境内で話していた。
誠はACミランのマフラーを巻いた石の狐に寄りかかり空を見上げていた。
「苺。どうだ。気持ち良いか?」誠は声を張り上げた。
「うん。すごーく気持ちイイ。秋空の奴きれいな青色になって張り切っている」
「そうだな、そんな感じだな。
ところでな苺、オマエと話してると首が痛くなってしょうがねえ。
なあ。もう降りてこい」
「マコちゃん・・それがさ。降り方がよく分かんないんだよね」
誠が見上げる上空で苺は竹箒に跨って浮いていた。
予告(?)
拙作「からす と うずら」へのniceとコメントどうもありがとうございました。
さて。
ブログ掲載には長めの短編小説が次回で三作目になります。
高校1年の時のこと。担任の数学教師が「3」は大事な数字だと言いました。
「『三日坊主』、『石の上にも三年』って言うだろ。
3を目安に頑張るようにするんだ。
目標を決めたらまずは3日頑張る。次に3週間、その次に3ヶ月、
そして3年頑張って卒業だ」
「三振バッターアウト。3で終わった」ボクが言った。
「はあ?」
「スリーアウト。ほら、攻撃が終わちゃった。3は良い数字とばかりは言えない」
「3割30本30盗塁、ほら一流選手だ!」
「・・・・・」
「年俸3億3千3百33万3333円。どうだ、一流選手だ!」
数学教師は意地になって3を羅列して、さらに言った。
「円周率は大体3だし」
「大体って。数学教師が大体は良くない。
イコールの上下に点をつけて約って言わなきゃ」
「それにな。今の俺の奥さんは3人目なんだ」
「うん。その3は大切にしたほうが良いと思います」
***
高校1年の時、担任の数学教師が教えてくれた単純だけど不思議な数式が次回作に
はエピソードとして出てくる事を予告に変えて。
※ 数学的考察で謎を解くミステリーとかでは全くありません。
今回も短編小説くらいの分量ですので御安心・・いやいや御面倒をおかけします。
お時間に余裕のあるときに読んで頂ければ幸いです。
今回もまだタイトルが未決です。
脳をこね、揉む時間を数日頂戴いたしたいと思います。
それでは。
からす と うずら
7月も半ばを過ぎて暑い日が続いていた。
エアコンの効きが悪い車内は蒸し風呂のようだ。2人の男はクーラーボックスから出した
ペットボトルの水を飲むと、水と一緒に冷やしておいた目薬をさした。
少し頭がスッキリした。
夏の盛りの青空には積雲がいくつも浮かんでいた。
不機嫌な菓子職人がつくったいびつなシュークリームのような雲だ。
そんな青空の下をまっすぐ伸びる片側1車線の田舎道。
埃を巻き上げ白いフィアットの箱型バンが走っていた。
かれこれ2時間すれ違う車はなかった。
「おい知ってるか?」助手席の男が運転席の男に声をかけた。
「何を・・・」ハンドルを握り運転している男は気のない声をだした。
「北極でさ。白熊が地軸の傾きを調節しているって話」
「知らない」
「聞きたい?」
「話したい?」
助手席の大柄な男はうずら。運転している小柄な男はからす。2人とも40才だ。
うずらはラジオの音量をしぼり咳払いすると…からすへ話し始めた。
「あのさ。北極点には黒くて太い棒が突き刺さってるんだ・・・。
そう、勿論これが地軸だ。
この地軸をさ一定の傾きに調節してるのが、北極点地軸隊の白熊たちなんだ」
「・・・・・」
「硬い鋼のワイアを地軸に巻きつけてウインチで巻き上げるんだ。
白熊が物凄い腕力でワイアを巻き上げる。ギリ・ギリ・ギリって…。
そうして地軸の傾きを調整するんだ」
「・・・・・」からすはハンドルを軽く右に傾け前を走る自転車を迂回して追い越した。
うずらはラジオを消した。「おい。聞いてるのに!」からすはうずらの行為に異議を唱え
た。からすはラジオのスイッチへ手を伸ばした。うずらはからすの手を自分の手で遮り、
顔を横に振った。「オレの話を聞けよ」うずらはからすの異議を認めなかった。
「ポーラスターズの連中は・・」
「なんだよ。ポーラスターズって?」
「ポーラスターズは白熊北極点地軸隊のチーム名だ。
80匹の精鋭で編成されたチームだ」
「いいか。オマエのその話が事実だとしてさ。
そのポーラ白熊隊はどうして地軸の傾きを調節しているわけ?」
ふんっと鼻息を出すかわりに「フンッ」とうずらは声に出した。
「どうして地軸の傾きを調節するかだって・・・決まってるだろ!」
「オマエが『決まってるだろ』と言うときはな、大抵の物事はなにも決まっちゃいない」
からすは太陽がまぶしいのでサンバイザーを降ろしサングラスをかけた。
「いいか。彼らが地軸を引っ張って傾けなかったら地軸は真っ直ぐになってしまうんだ。
ワイアで引っ張って杭に縛り付けとかないと、ぴょんっと真っ直ぐになるんだ」
からすは「はあ?」と声をあげ「なんだよ。ぴょんっと真っ直ぐって・・」と言うとギア
を3速から2速へ落とし角を左へ曲がった。
「いいか。地軸が傾いてなかったら夏も冬もないんだぞ。
季節がなくなるんだぞ。オマエそれでいいのか!」
「『この素晴らしき世界(What a Wonderful World)』…彩りと多様性に溢れる地球に
なったのは季節があるからだ・・か?」
「そう。ワンダフルだ。色彩も音も季節があるから豊かになったんだろ。
地軸が傾くと地球にワンダフルが起きるんだ」
「じゃあ何か…美しい季節をつくるために地球が白熊に頼んだのか?
『なあ。地軸をそっちへ引っ張って傾けてくれ』って」
「あるいは。地球が白熊に言ったのかもしれない。
『真っ直ぐでいるより、ちょっと傾いてるほうが楽なんだ』・・」
白いフィアットのバンは岩手県一関市内に入った。
東京を出てから3日目。Nシステム(自動車ナンバー読み取り装置)カメラが設置されて
いる高速道路や主要国道を避けて走っていた。
***
江東区木場の貸倉庫の前に車が2台止まっていた。黒いトヨタのワゴンから男が1人出て
きた。男はカウボーイのような帽子を被っていた。もう1台の白いフィアットのバンから
出てきたのは2人の男だった。2人に向かって帽子の男が言った。
「オマエら2人が運び屋か?」
「履歴書を持って来たけどみせようか?」からすが無表情のまま言った。
「・・・・・」
「荷物を出してそっちの台の上に置いてくれ」うずらは言うと、口にガムを入れ男がワゴ
ンから大ぶりの木箱を運び出すのを眺めた。木箱を置いた台の上部にはカメラ装置が付い
ていた。
帽子の男は怪訝な顔をして「この機械はなんだ?」と言った。
「空港で荷物検査に使っているX線スキャン装置があるだろ、あれと原理は同じだ」
からすが言うと、うずらは機械を操作して木箱をスキャンした。
「どうして、こんなことをする?」帽子の男が言った。
「火気厳禁」からすが言った「オレたちのルールだ」
「勝手に燃えたり爆発したりするものはお断りなんだ」うずらがニッコリ笑った。
「だけど箱を開けて中はみない。オレたちは運ぶだけだ。荷物がなんなのかは知りたくも
ないし関わりたくないんだ」からすが無表情のまま言った。
からすが男から受け取った紙には青森市内の住所と貸倉庫の番号が書かれていた。
「1週間はかかる」からすが口元をゆるめて言った「急ぐと目立つんだ。マラソンでも
速い選手のほうが目立つだろ・・」
うずらがまたニッコリ笑って続けた「旅はのんびり行くほうが楽しい」うずらは口笛を吹
いた。レディオ・ヘッドの曲だった。口笛を止めるとうずらが言った。
「オレたちはクリープだ。曲がりながらそっと移動する」
帽子の男はそれには答えず、煙草をくわえライターで火をつけようとした。
からすとうずらが声を揃えた。
「火気厳禁!」
【運び屋】盗品・麻薬・密輸品などを運搬する役の者(国語辞典より)
からすとうずら2人の仕事も大筋では国語辞典に載っている【運び屋】とほぼ同じだ。
但し麻薬・密輸品の類で2人に依頼する人間は滅多にいない。料金が高すぎで赤字になる
からだ。そう彼らの料金は高い、しかも完全前払い、それでも多くはないが依頼主はいる。
どうしてか?物流は多くの場合、差出人の履歴が残る。それはリアルな物だけじゃない。
ファイルをネットで送信すると・・・勿論ネットにも履歴は残る。その「履歴は残る」を
嫌う人間が世の中にはいる・・だから2人のビジネスはなりたつ、ということだ。
実際過去にはUSBファイルだけの運搬や手紙だけの運搬を依頼されたこともある。
料金が高額だって差出人の履歴を残さず運びたい荷物を抱えてる連中がいるってことだ。
2人はX線スキャンで荷物を検査し、それがルール違反のものなら引き受けない。
スキャンするまでもなく「人を運んでくれ」は引き受けない。スキャンした荷物の中身が
「動かない人」だったら絶対に引き受けない。
もっともコーヒー・スプーン3杯ほどの倫理観しか持ち合わせない2人が断った荷物は
過去に5件だけだ。良心はないが好奇心ならたっぷりある。
それに2人は・・・旅が好きだった。
3人の男達が持ってきた木箱をX線スキャンした画像がモニタに表示された。
筒状の巻物だった。カーペット?
うずらが独りごちた。巻物とか・・?
「忍者が口にくわえるには大きすぎるよな・・・」
* **
一関市内のホテルの部屋に入ったのは辺りが暗くなり始めた頃だ。
荷物とスーパーマーケットのレジ袋を部屋に置くと2人は交互にシャワーを浴びた。
シンプルと殺風景の間に存在するような部屋だった。
長身のうずらが椅子の上に立ち天井の火災感知器を食品用のラップフィルムで覆った。
そこへ冷却スプレーを吹き付けた。これで感知器は煙と温度上昇に反応しないはずだ。
からすは窓を開けると鞄から出した物を次々とライティングテーブルへ置いた。
卓上IHクッキングヒーター、まな板、包丁・・。それからレジ袋から買ってきた食材を
取り出してベッドの上に並べた。
からすはフライパンでオリーブオイルを温め、粗く切った玉葱とニンニクを入れ炒めた。
そのフライパンへ大ぶりの腸詰めソーセージを3本入れ軽く炒めた。さらに続けてフライ
パンへ生米を洗わないまま入れ、米に焦げ目がつくように炒めた。そして、お湯で溶いた
固形ブイヨンのスープを入れ、ざく切りにしたキャベツで全体を覆いフライパンに蓋をし
て中火にセットした。
約15分炊いてから5分蒸らせばポルトガル風炊き込みご飯の出来上がりだ。
部屋は香ばしい幸福で満ちた。2人はフライパンから自分の皿に取り分け食べた。
オリーブオイルで炒めた玉葱・ニンニクから出た風味、腸詰めソーセージから出た塩けと
脂、そしてブイヨンスープ、すべてが米にからまり染み込み美味しく炊き上がっていた。
表面に焦げ目がついたご飯は場所によって少し芯が残っていたが、噛むとしみ込んだ食材
の香りが口に広がり思わず笑顔になる。キャベツの甘味と歯応えも心地よかった。
スーパーマーケットで買ったチリの赤ワインも美味かった。
量感豊かな炊き込みご飯には、すこし重めのカベルネ・ソーヴィニヨンがよく合った。
全部食べ終えると…うずらが叫んだ。
「美味い!」
「『美味い』はさ、普通は全部食べ終わる前に言わないか」
テレビにはサッカーの国際試合が映っていた…メキシコ対チリ。
うずらはラムをトマトジュースで割りそこへタバスコを大量に入れ飲みはじめた。
からすは赤ワインを飲み続けていた。
「どうしてそんなに真っ赤で辛いものを飲む?」
「だってメキシコ対チリだろ。激辛対決だぜ」
「南米チリの国名のチリは唐辛子じゃないぞ」
「えっ。そうなの?うん。たしかに国の名前が唐辛子ってのはちょっとだな・・
うんチリは唐辛子じゃないのかもしれないな」
「かもしれないじゃない。絶対違うに決まってる」
「『決まってる』と言うときは、大抵の物事はなにも決まっちゃいない」
「・・・・・」
「あれはなんだったんだ?」いきなりうずらが言い出した。
2人は同じ高校のサッカー部だった。うずらが言ったのは最後の地区大会2回戦のプレー
のことだ。1対0と相手にリードされた後半38分。相手ゴール前まで攻め上がったときの
ことだ。うずらは2トップのフォワードの1人、からすは2トップの下のミッドフィルダ
ー3人の1人だった。その時、からすは足下でボール動かしながらパスの出し所を探して
いた。
「オレは相手ゴール前でデフェンダー4人のうち3人を引き付けていた。もう1人のフォ
ワードの周囲にはスペースが空いていた。なのにオマエはオレにパスをよこした」
「アイツには決定力がなかった。そしてオレにはオマエの窮屈な足元へパスを収める自信
があった」
「パスを受けて前を向けてもシュートまでもってくのは難しかったぞ」
「それでも・・相手デフェンダーの足下へのファウルは誘えると思ったんだ。
そうすりゃゴール前でオレのフリーキックだ」
「じゃあなにか。自分のフリーキックのお膳立てにオレにパスを出したと。
そしてオレの足が削られファウルをもらえばいいと、考えたと」
「オレと同じ小柄な・・バルサのシャビも言っていた。
『サッカーは身体でやるんじゃない、頭でやるんだ』」
「オレの足のことも少しはいたわれ!」
「後半オレたちのチームは足が止まっていた。あとはセットプレーしかないだろ?」
「そしてあのときオマエの思惑通り相手デフェンダーはオレの足をタックルで削ってきた。
あれは明らかにファウルだ。なのに審判は笛を吹かなかった」
「いいか。オレは見ていた。審判は笛を口にくわえたんだ。
それなのに、どうして吹かなかった?
オマエが倒れなかったからだ」
「あのな。かなり痛かったさ、けどな倒れるより先にシュートが打ちたかったんだ」
「試合の後に病院へ行ったら骨にヒビが入ってたんだぞ。
骨折して倒れないってどんな足してるんだよ」
「オマエの作戦がいけないんだろ。結局ファウルはとれなかった」
「オマエがあんなに丈夫だってのが想定外だった。
そりゃ…いつもオマエの口癖は『大丈夫!』だった。
けどな。骨にヒビが入っても大丈夫なヤツだとは思わなかったよ」
サッカー中継が終わるとテレビを消して音楽をかけることにした。
からすはiPodを鞄から出した卓上小型スピーカーに接続した。
流れてきたのはローリング・ストーンズだった。
3曲目に流れてきたのは「ルビー・チューズディ」。ピアノ、リコーダー、チェロ、ドラ
ムスで構成されたミディアム・テンポのバラードだ。ブライアン・ジョーンズの吹くリコ
ーダーが幻想的で、ミック・ジャガーのボーカルは物憂げだ。
うずらが口を開いた。
「ルビー・チューズディってさ・・なんだろ?」
「曲にでてくれる『彼女』のニックネームだろ・・」
「宝石のルビーと火曜日…どんな意味なんだろ?」
「曲のなかで『誰がつけたんだい?』って聞いてるけど、彼女は答えない。
どんな意味かは曲のなかでは触れていない」
『彼女はどこからやって来たのか言わない
昨日はもう過ぎてしまったことだ、どうだっていい
太陽が輝いてる間、もしくは暗闇の夜に
彼女はやって来て、そして去って行くのを
誰も知らない
さよなら ルビー・チューズディ
だれが君にその名前をつけたんだい?
君が毎日毎日変化していくたび
そのたびに僕は君が恋しくなる』
曲が終わるとうずらがからすに言った。
あるいは、うずらは自分に向かい言ったのかもしれない。
「苺は・・どうしているんだろ?」
「・・・・・」
* **
5年前まで、からすとうずら2人は東京都町田市でバーを営業していた。
8席のカウンターと4人掛けのテーブル席が1つの小さなバーだった。
からすが料理担当(とても簡単な料理だけだが…)、うずらが接客担当(出鱈目な話を客
に話しかけるだけだが…)だった。
常連客が持ち込む厄介事への好奇心が抑えられないときや客への義理があるとき、2人は
臨時で探偵や便利屋のまねごともやっていた。
6年前の蒸し暑い8月の夜、バーに30代前半の女がやって来てカウンター席に座った。
一重まぶたの細い目が笑うと猫が目を瞑ったようになる愛嬌のある女だった。
頬から顎へのラインがシャープな女だった。長い黒髪を無造作にまとめアップして後頭部
にできた「髪の団子」にガラス細工が付いた木製のかんざしを刺していた。
身長はからすとほぼ同じ。女としては背が高いほうだ。
彼女がカウンター席に座るのが3度目になったとき、珍しくからすから話しかけた。
「君のことを『お客さん』以外で呼ぶときはなんて言えばいいのかな?」
「苺」
「いちご・・?」
「名前がね・・苺」
「変わった名前だねって言ってもいいのかな・・」
「そっちこそ。からすクン、うずらクンでしょ。もっと変わってるじゃない」
「オレたちは名前じゃなくて名字だからさ…そんなに変じゃないだろ」
「本気で言ってる?」
それから苺は毎週2人のバーにやって来るようになった。
好んで飲むのはルビー色のデリケートなピノ・ノワール、そしてやって来るのは決まって
火曜の夜だった。さらには。予想どおり苺はローリング・ストーンズが好きだった。
からすは誰にも(勿論うずらにも)言わなかったが、こう思っていた。
『彼女はどこからやって来たのか言わない
こんにちは ルビー・チューズディ
君にその名前をつけたのは この僕さ』
苺とからす、うずらはすぐに打ち解けた。
苺との会話は楽しかった。そして時に刺激的だった。
良い料理は箸で食べても、スプーンで食べても美味しい。朝食べても夜食べても美味
しい。そして同様に良い音楽はいつどこで聴いても心に伝わる。
苺との会話はまさしく美味しい料理や良い音楽のように楽しく時に刺激的だった。
あるいは冷蔵庫でほどよく冷やした目薬のように2人をリフレッシュした。
苺、からす、うずら…3人は親愛で結ばれ、親愛のパスを交換した。
しかし時が経つにつれ。
苺とからすの2人は船底から親愛のバラストを海へいくつも放り投げ捨てた。
喫水線が下降し波の上に現れた鋼の船体には大きな文字で『Intimacy(親密)』とペイン
トされていた。
2人は外でも逢うようになった。歩いたり(もちろん会話をしながら)、映画を観たり
(共通のフェイバリットは「バグダッド・カフェ」だった)、料理を食べた(バーで
からすがつくるものよりは複雑でデリケートな料理だ)。
恵比寿にあるレストランで2人が食事をしているときだった。
「聞いてもいいかな・・苺の仕事はなんなの?」からすは苺の返事を待たずに聞いた。
出会ってから3ヶ月がたっていた。
苺は首を左に傾けた。それが話すときの苺の癖だった。
「流しの花火師」
「ながしのはなびし」
「あるいは流しの手品師」
「ながしのはなびしあるいはながしのてじなし。よく分からないな・・・」
「もう少し時間をください。
待ってて。そのうちわたしのことをたっぷり聞いてもらうことになるから」
「・・・・・」
「わたしは・・からすクンの仕事は知ってるつもり・・でも、どんな人なのかは知らない」
「平凡で平板な・・多少の驚きと多少の落胆でできている人間だ。
時々スリーカードを引き当てるけど、フルハウスは経験したことがない」
「ねえいいかな。そんな面倒くさい話し方はやめたほうがいい。
それに。からすクンが平凡で平板な男なわけないと思う」
「平均的な平和を愛する平家物語に涙する男。『平』3連発の男」
「なにそれ・・ふふっ」
「ねえ。『流し』がキーワードってこと?」
「えっ。そこへ戻ったの・・」
「流し、流れ者、吹き流し、風来坊、巡礼者、ジプシー・・」
「ハハハッ!どうして巡礼者とかジプシーになるわけ。
わたしはね、まっすぐ前に進むのが苦手なんだよ、きっと。
それで風に吹かれて、流れるのかもしれない。
まっすぐよりさ、ちょっと曲がったりとか傾いたりのほうが楽でしょ」
苺はまた首を左へ傾けて照れくさそうにはにかんだ。
「苺の首が左へ傾むいて…傾いたほうへ歩いてきてこの町に辿り着いたなら、
オレはその傾きに感謝する」
「わたしはこの町が気に入っている。だからしばらくは出ていかない」
「だったら・・オレは嬉しい」
「ねえ。平均的な平和を愛するって・・イイよね」
「えっ。今度はそこへ戻るのか?」
「猫ってさ、温かいところを見つけて寝そべるでしょ。路地や塀の上や…家の中でも温か
いところをちゃんと知っている」
「・・・・・」
「腹這いになったり、身体を丸めたりして寝るよね。
それに、横向きになったりして背伸びするようにして寝るときもある。
あっ。猫ってこんなに長いんだって思うくらい背伸びして寝てるとき、あるでしょ?
目を瞑って、幸せそうな顔で寝てるでしょ」
「・・・・・」
「あれって良くないかな?」
「うん。良いよな」
「あれってさあ、『平均的な平和』とか『平均的な幸福』じゃないかな?」
「特別な平和とか高得点の幸福じゃあ・・ないな」
「猫はさ・・。
『諸君、平均的な平和と平均的な幸福こそが大切なんだぞ』ってさ・・
わたしたちに伝えているんじゃないかな?」
「オレはほどよく冷えた目薬をさすと平均的な過不足のない幸福を感じる」
「ねっ。ねこは平均的な平和と平均的な幸福の伝道師なんだよ」
「かもしれない。でもまずは・・この平均的な料理と平均的なワインを片付けよう」
「うんうん。今度はもっと美味しいお店に行こうね!」
苺は目を瞑った猫のような目になって微笑んだ。
それから3ヶ月後。苺は町からいなくなった。
携帯電話は何度かけてもつながらなかった。
ある種の失踪もしくは疾走とでもいうような足跡も残さない手品のような消え方だった。
それが5年前の4月のことだ、桜が満開だった。
夏空に綿菓子ような雲が浮かぶのを眺めながら、からすはバーを閉じることをうずらに告
げた。
それから。からすの口数は少なくなった。
* **
盛岡市内のホテルにチェックインすると2人は材木町へ向かった。
ホテルでロビー・ボーイに「盛岡には美味しいクラフト・ビールがあるって聞いたんだけ
ど、どこに行けば飲めるのかな?」と聞くと、彼はにっこり笑ってこう答えた。「今日
は土曜日です。『よ市』に行ってみるといいですよ」
「よ市」は盛岡市材木町で30年前から開かれている市だ。毎年4月から11月にかけて毎
週土曜日に開かれていた。
「よ市」は「夜の市」や余ったものを安く売る「余市」からつけた名前らしい。
350mほどの長さの道路をはさんで両側に古くからの商家が軒を並べ、店舗と道路の間の
歩道にずらりとさまざまな露店が連なっていた。商店街の両端には「よ市」と書かれた大
きな垂れ幕がひるがえっていて道路は歩行者天国になり多くの人で賑わっていた。
露店では農家の人達が、野菜、果物、山菜、生花を売っていた。しかし2人にとってこれ
らの露店は目に入らなかった。狙いは盛岡のクラフトビール会社が出店した露店、それと
食べ物だ。通りを歩きながら食べ物の露店をざっと見渡した。ラーメン、焼きそば、たこ
焼き、焼き鳥、焼トン、ツブ貝串焼き、モツ煮込み、牛スジ大根煮込み、鉄板焼き辛味噌
ホルモン、トンカツ、コロッケ、燻製(肉/チーズ)などなど。縁日の露店と違って「よ市」
の露店は殆どが市内に店舗をもつ飲食店の出張露店なので種類も豊富で味も本格的だった。
なかにはコーヒーやケーキの露店もあったりした。
2人は目指すクラフトビールの露店を探して歩いた。それはすぐにみつかった。
クラフトビールを買うための長い行列がとても目立っていたからだ。工場から瓶詰め前に
直送されたビール樽は3種類。樽をつないだサーバーからグラスへ注いで売っていた。
からすとうずらは話し合って分かれた。からすがビール担当で列に並んだ。うずらは食べ
物購入担当。からすはビールを4杯買って集合場所の通りに設置されたベンチへ来たが、
うずらはなかなか戻ってこなかった。2杯めのビールを半分飲んだ頃、うずらが戻ってき
た。殻付きのまま蒸した三陸の生牡蠣、玉こんにゃく、モツ煮込み・・なぜかシュークリ
ームも買ってきていた。
ドイツ風のクラフトビールは濃厚な飲み味なのに柔らかいフレイバーなので時間をかけて
飲み続けることができる美味しいビールだった。
うずらは満足そうに笑った。
「うん。こりゃ美味いビールだ。夕方の夏風に吹かれて飲むビールは格別だ」
「玉こんにゃくと牡蠣が美味い」からすは笑顔になった。
「モツ煮込みとシュークリームの組み合わせも乙なもんだな」
「・・・・・」
その日は材木町で酒買地蔵の祭りもやっていたので普段のよ市より人では多かった。
「・・苺は見あたらないな」うずらがビールを飲みながらつぶやいた。
盛岡出身の苺は2人によく言っていた。
『よ市は楽しいからさ、今度3人で行こう。すぐそばには北上川が流れてるんだよ・・
川の畔のベンチに座ってさ、盛岡の地ビールで昼酒だあ!』
材木町は宮澤賢治ゆかりの町だった。商店街には「注文の多い料理店」を出版した光原社
が今は喫茶店になって残っていた。歩道には賢治童話の世界をモチーフにした6つのモニ
ュメントが置かれていた。
苺はこんなことを言ったことがあった。
『宮澤賢治の「雨にも負けず」ってさ・・ちょっとオフビートでさパンクだよね。
「日照りの時は涙を流し 寒さの夏はおろおろ歩き みんなにでくのぼーと呼ばれ
褒められもせず 苦にもされず そういうものに わたしはなりたい」
ねっ?甲本ヒロトがジャンプしながら歌いそうじゃん。
「そういうものにぃ わたしはぁなりたい! イエーィッ」とか。ねっ。』
夕闇せまる「よ市」のベンチで、からすは風に吹かれぼそりと独りごちた。
「ぬるくなってから味わいが増す良いビールだ・・」
* **
フィアットは県境を越え青森県に入った。道路は舗装されているが両側は見渡す限りの畑
地だった。雲がない青空だった。
「スカイブルーだな」「そりゃ青空だからな」
陽差しは雲に遮られずに直接地上に降り注いでいた。エアコンのききが悪いフィアットの
車内が暑くなってきたので2人とも窓を全開にした。
助手席のうずらが運転しているからすに話しかけてきた。
「荷物の木箱の中身だけどさ・・オマエX線スキャン画像をみて『はんぷか?』ってぼそ
っと言ったろ?」
「えっ…」からすは戸惑った。うずらがまともな質問をしてきたからだ。
「あの巻物がはんぷなのか?」
「ああ。オマエにはそう見えなかったか?」
「はんぷってなんだ?」
「そこからかよ。帆布はな、厚手の布だ。亜麻とかで織った厚手の布だ」
「じゃあ、あれはカーペット?カーテン?」
「帆布はな…キャンバスとも言う」
「キャンバスって、あのキャンバスか?」
「ああ。油絵具を塗るのに使うキャンバスが帆布だ…」
「おい。じゃあ1週間前のあれ・・」
からすが言いたかったことは、東京都内の美術館で起きた絵画盗難事件だ。
うずらは溜め息を吐いて、からすへ言った。
「あのな。荷物を詮索するのはルール違反だ。オレ達は荷物を移動させるだけなんだ」
「おい。観てみないか?だってフェルメールの、青いターバンの……」
「黙れ!」からすは車の通らない田舎道で急ブレーキをかけた。うずらは身体が前に飛び
だし膝をフロントパネルで打ちつけ、「痛えよ」と文句を言った。
「いいか。このビジネスはな、信用が大事なんだ。信用を失えば危険がドアを叩く。
それに。いざというとき、荷の中身を知らないことがオレたちの身を守るんだ」
十和田湖へ向かう山間部の登り坂に入るとFMラジオは電波の受信状況が悪くなりノイズ
しか聞こえなくなった。仕方がないのでからすはラジオを消した。
「エンリコ・フェルミっていう物理学者がさ、『宇宙人はどこにいるんだ?』って言った
らしい」珍しくからすのほうから、しかも奇妙な話を始めた。
「ふんふん。なかなか見所がある物理学者だ。で?」案の定うずらは興味を示した。
「オマエに軽々しく評価されるようなヤツじゃない。いいか、ノーベル物理学賞をとって
るし、あのマンハッタン計画で核分裂反応の研究をしていた…バリバリの物理学者だ」
「物理学者の評価にバリバリってのはありか?」うずらは評価合戦をゆずらない。物理
学者の評価に「なかなか見所がある」と「バリバリ」のどちらが適切か……。
「オーケィ、なかなか見所があるでイイから話を先に進めるぞ。
宇宙が出来てから膨大な時間が流れた。そして宇宙には膨大な数の星が存在する。
ここまではいいな?
だったら。知的生命体も多数あるはずなのに、どうして地球に来た痕跡がないのか?
地球に来た宇宙人がいるべきだと考察した。そこでフェルミは言った…」
「宇宙人はここにいるんだ!」
「違う。宇宙人はどこにいるんだ?・・だ」からすは、ここまで説明したのが無駄だっ
たかと思い話を止めてラジオのスイッチをいれたがまだノイズなのですぐに消した。
「だから。宇宙人は地球に来たんだって」うずらは考えを曲げなかった。
「どうしてさ、そう簡単に断言できる?」
「いいか。猿と人類の違いはなんだ?」
「DNAだろ」
「違うな。パンツだ。地球に来た宇宙人が猿にパンツを穿かせたんだ。そしてパンツを穿
かないと恥ずかしいというDNAを猿に植え付けた。
するとどうだ、パンツを穿いた猿たちだけが進化を始めた」
「はあ?どうしてパンツを穿いただけで進化するんだよ」
「そりゃパンツを穿いただけじゃ猿が人間にはならないさ。いいかよく聞け」
「聞かなきゃいけないのか?」
「400万年の膨大な時をかけて猿は一念発起したんだ」
「猿がなんの一念発起だよ?」
「『人間らしく 生きたいな』ってさ」
「そりゃ何かの詩か?」
「違う。猿の一念発起の祈りだ」
「・・・・・」からすは眩暈がしてきた。
「それでな。困ったことが起きて宇宙人が悩んだ。パンツを穿かないと恥ずかしいという
DNAを植え付けられた猿たちは・・パンツを脱がなくなった」
「この話はまだ続くのか?」
「続く」
「・・・・・」
「それでな。宇宙人は『時には…パンツを脱ぐと嬉しい』という神話を残したんだ」
「・・・・・」
「間違いないぞ。だってパンツのことを『猿股』って言うだろ?」
* **
十和田湖には寄らずに子ノ口の駐車場でフィアットを止めた。2人は奥入瀬渓流の遊歩道
を歩いた。ずっと1人で運転してきた、からすの身体は強張っていた。からすはどうして
1人で運転を続けるのか。うずらの運転する助手席に乗るともっと身体強張るからだ。
うずらはどうして運転を代わると言わないのか。からすが運転好きだと思ってるからだ。
奥入瀬渓流はブナなど樹木の群生に覆われていた。それは深い森ではないが夏の強い陽差
しを程よく遮り、充分な木洩れ日で辺りは暗くはないが空気はひんやりとして心地良かっ
た。渓流を挟んだ両側は視界が尽きるまで緑色に染まった樹木や植物だった。樹木の葉の
緑の彩りも鮮やかだが、奥入瀬渓流は苔植物群が豊富な「苔の森」として知られるだけあ
り、樹木の幹、倒れた朽ち木、岩石、そして水が流れている渓流にある転石までもが満遍
なく苔生していた。
フゥーッ。息をつめて景色を観ていたのを忘れ思わず深呼吸するほどの美しさだった。
「イッツ・ア・グリーン・ワールドだな」うずらが言った。
「英語タイトルにしてもディズニーランドのように子供は集まらないだろうけどな」
からすは笑いながら言った。
うずらが昨日盛岡の「よ市」で買った胡瓜2本をポケットから取り出して、1本をからす
に渡した。
「喰うのか?」うずらの行動の意味が分からずからすは聞いた。
「河童に会ったらさ、胡瓜をあげようと思ってさ」
「あのな。奥入瀬渓流に河童伝説はないぞ」
「えっ・・じゃあ河童はいないのか?」うずらは傍からみても分かるほど落胆し口数が少
なくなった。仕方ないのでうずらが乗ってくる話題をからすはふった。
「河童はいないけど世界のどこかに宇宙人はいるかもしれない」
うずらはまるでドリンク剤のCMタレントのように傍からみても元気になった。どうや
ら河童より宇宙人に興味があるようだ。
「そりゃ勿論宇宙人は世界中にいて人間の町で生活しているんだ」
「いきなりそこまで言い切るか?」
「だってさあ。ちょっと人間じゃないよねコイツっていうヤツいるだろ?
ダ・ヴィンチとかアインシュタインとかさ」
「うん。確かにアイツは天才だからじゃ片付けられない…人間離れした才能のヤツはいる
よな」
「なっ。だから宇宙人は猿にパンツを穿かせて人類へ進化させただけじゃなく、自分たち
もそのまま地球に住んだんだ」
「宇宙人が町に住んでたら目立つだろ?」
「いいか。動物園に行ってさ、猿をみるとさ、自分に似てるか?似てないだろ。
宇宙人は自分たちに似るように進化させて人類にしたんだ」
「・・・・・」
「だから。ばれない。
けど年に数回顔色が緑とかエイリアン色に変わったり、耳が尖ったりするんだ。
スポック船長のように」
「スポックは船長じゃない」
「だから年に数日そのときだけは……」
「そのときだけ?」
「兎のぬいぐるみの頭を被る」
「はあ…?」
「ジョン・レノンは『マジカル・ミステリー・ツアー』で兎のぬいぐるみを着てたじゃな
いか」
「確かにジョンは人間離れしてるがな、兎のぬいぐるみはジョージだ。
ジョンが着ていたのはせいうちだ」
「『アイ・アム・ザ・ウォラス』かあ…。
でもオレのイメージじゃ宇宙人が被ってるのは兎なんだけどなあ・・・」
* **
奥入瀬渓流から戻りフィアットを走らせ10分位すると…
「この先、手打ち『名物・蟹うどん』」と書かれた看板が道路に立っていた。
こんな山の中で蟹うどん?十和田湖で淡水生息の蟹がとれるのか?まあいい。腹も空いて
いたことだし入ることにした。店は道沿いにあったのでほどなくみつかった。駐車場に
フィアットを停め2人は店に入った。
30分後。2人は笑顔で意気揚々と店から出てきた。満足だった。
うどんの上に乗ってきたのは淡水蟹ではなかった。たらば蟹のむき身がどーんと乗った、
贅沢な蟹うどんだった。麺もほどよい腰ともちもち感のある、見事な手打ち麺だった。
出汁に蟹の風味が効いて、つゆも上品な味わいだった。
駐車場のフィアットの隣に停まっている大きなトラックに2人の目は吸い寄せられた。
からすが「あーっ!」と叫びトラックを指さした。
ボディには大きな文字で『山崎水産 たらば風味蟹かまぼこ』と書かれていた。
からすは罵った
「クソッ!なんてこった」
「いいじゃないか。旨かったんだから」
「そういう問題じゃない。騙しやがって」
「だってさ。店の看板には生蟹って書いてないじゃん」
「名物と書いてある」
「名物の蟹かまぼこかもしれない」
そこへもう1台のトラックが駐車場に入ってきて止まった。
ボディには「及川製麺」と書かれていた。からすは両手で握り拳をつくりなじった。
「麺は手打ちじゃないのかよ!」
「製麺所が手打ちとか…」
「製麺所がそんな効率の悪いことするか」
2人の横をうどん麺の入ったケースを持った男が通っていった。その仕草がテキパキとし
ていて余計に腹がたった。すると他の男が続いた。手に持っていったダンボールには
「うどんスープ」と書かれてあった。動作がキビキビしていて余計に腹がたった。
からすが今度は泣き出しそうになって言った「出汁もつゆも手作りじゃないのかよ…」
車中でもからすは不機嫌のままだ。
「いいか。人間はな美味しいものを喰いたいっていう情熱が大切なんだ・・
それをあのうどん屋め・・オレの情熱を踏みにじりやがって」
「いいじゃないか旨かったんだから」
「いいやよくない。こそこそしやがって。
ああいうのはな・・ロックじゃねえ」
「時には・・不幸なこともおこるさ」
「それにしたってあんまりだ」
「地軸の傾きが足りなかったんだ。北極点の白熊隊が休憩中なんだ」
「何を言ってる?」
「地軸を傾けないと地球にワンダフルは起きないんだ」
「それで蟹かまぼこのうどん屋に入ってしまったって言うのか?」
「うん。それに・・奥入瀬渓流には河童がいなかった」
「・・・・・・」
十和田市から黒石市に入り、そこからさらに八甲田を通過して青森市に着いた時には夏の
太陽も傾いていた。目的地の貸倉庫に行く指定日は明日だ。つづら折りの山道を延々と運
転してきたからすの身体は強張り料理をつくる気は失せていた。2人はホテルの部屋に鞄
を放り込み夕食を求めて外の通りへ出た。
2人が落ち着いたのは郷土料理を出す居酒屋のカウンターだった。店は家族5人で切り盛
りしていた。酒蔵を改造した店内は落ち着いた雰囲気で好感がもてた。
ビールで乾杯した後は地元の酒「田酒」を冷やでもらった。カウンターの上に並んだ料理
はホタテと烏賊の刺身、じゃっぱ汁、貝焼きだった。どれも美味いが2人が特に気に入っ
たのは貝焼きだった。
「貝焼き(かやき)」はこんな料理だった。大ぶりのホタテの貝殻をそのまま火にかけて
調理する。そう。貝殻を鍋代わりに使った料理だ。ホタテ貝殻へ焼き干しでとった出汁を
入れて味噌を溶いたら火にかける。沸騰してきたらネギをあふれるくらいたっぷり入れ、
ネギが煮えてきたら最後に溶き卵を回しかける。卵が半熟になったら火からおろす。
これだけだ。これだけなのに旨い。半熟卵と汁も旨いが、ネギと焦げて貝にへばりついた
味噌がたまらない。焦げた味噌の風味が冷酒によく合った。
いい年をした大人2人が大声をあげ、のけぞって感動した。
「これはB級グルメなんかじゃない。もっと・・こう突き抜けている。
これは・・パンクだな」からすは絞り出すように言った。
「ジョー・ストラマーに食べさせたかったなあ」うずらは笑顔で言った。
「ジョーイ・ラモーンにも食べさせたかった」からすも笑っていた。
「パティ・スミスにも・・」
「パティ・スミスの好みじゃないと思うぜ」
「そうかなあ・・」
1時間が過ぎたころ、からすが立ち上がりトイレに行った。戻って来ると、すぐに誰とで
も打ち解けるうずらが隣の客と仲良く話していた。からすがトイレに立つ直前にうずらの
隣に座った客だった。その客にうずらは貝焼きを「食べてみてよ」と勧め、笑いながら話
しかけていた。
その客は2人より少し年かさの男だった。床にはバックパック、上は半袖Tシャツ、下
はクロップド・タイプのカーゴパンツ、足下はトレッキングシューズだった。
うずらは遠慮なく聞いていた。
「アンタ何してる人?」
「うん…うまく説明できないんだけど・・あちこち歩いてるんだ」
「あちこち?」
「そう。あちこち」
「流しの花火師かな?」
「・・・・・」
「あるいは流しの手品師とか?」
「花火を作ったことはないし、手品もやったことがない」
「でもさ…あちこちだろ?」
「そう。あちこち」
「じゃあやっぱりキーワードは流しだ」
「どっちかって言うと。キーワードは森なんだ」
「森・・?」
「僕は森を歩いてるんだ」
「流しの森林浴師とか?」
「いや。うまく説明できないんだけど。
森を歩く目的はそれほどクリアじゃないんだ」
その後1時間ほど男とうずらは噛み合わない話を続けた。からすは黙って飲んでいた。
男は「明日、白神山地へ行くつもりだ」と言って出ていった。
「今の人さ、話してみると良い人だったぜ」うずらは笑顔で言った。
「たださあ、津軽の郷土料理を食べながら飲むのが・・
バーボン・ソーダってのはなあ」
***
東京で会った依頼人から受け取った紙に書いてあった貸倉庫ナンバーの前に行くと、これ
も紙に書いてあった赤いサーブが停まっていた。
2人がフィアットから降りると、サーブの運転席が開き男(?)が降りてきた。
男(?)を見てからすは舌打ちして顔をしかめた。一方うずらは目を輝かせて嬉しそうに
していた。
恰幅のよいどっしり肥った、この暑い日にダークスーツを着た男(?)は・・・。
ソイツは白兎のぬいぐるみの頭をすっぽり被っていた。
「オマエたち2人が運び屋だな?」兎頭は言った。声は男だった。
「アンタは宇宙人なんだろ?」うずらが我慢しきれずに聞いた。
「は?オマエ何を言ってる?」
「だから地球に住む宇宙人なんだろ。だって兎の頭を被ってるじゃないか!」
「これは単なる変装だ。オレは素性の分からない人間には素顔をさらしたくないんだ。
おいそっちのヤツ、とにかくコイツを黙らせろ。
話はそれからだ」
からすが兎男に向かって冷えた声を出した。
「話はそれからだってなんだ。オレたちはここでアンタに荷物を渡したら消える。
それだけだ。それ以上も以下もない」
2人はフィアットのバンから木箱をさっさと出すと兎男の足下に置いた。
「追加の依頼があるんだ」
「断る」
「手紙を届けて欲しいんだ。
差出人履歴のない手紙を運ぶのがオマエたちの仕事だろ」
「ふざけるな」からすは冷えた声に怒気をにじませ言うと、うずらへ行こうと促した。
うずらは首をふった。からすは小さな声で言った。「行くぞ」「いやだ。オレは宇宙人と
話したい」「ふざけてる場合か!行くぞ」2人が言い合ってると兎男が声をかけてきた。
「2人がよく知っている女性へ手紙を届けて欲しいんだ。
からすとうずらが仲が良かった苺へ」
からすの声からは怒気が消え完全に冷えきった。
「オマエは誰だ?どうしてオレたちの名前を知っている?」
「彼女はオマエたち2人に会いたがっている」
「苺の知り合いなのか?」
「オレは彼女のことを知っている。だけど彼女はオレを知らない」
「おい。何を言ってる?」
「だからオレが彼女へ書いた手紙は差出人の名前が無い。
たとえ書いても彼女はオレを知らない」
「おい。質問に答えろ。オマエは何者なんだ?」
「オレは彼女へ贈る、花火と手品の種と仕掛けのアイデアを書いた。
そしてこの手紙を彼女へ届けるのはオマエたち2人だ」
「・・・・・」
「いいからこの手紙を宛先の住所へ届けろ」
「これはトラップか?」
「初対面のオマエたちを罠にはめる理由がオレにあると思うか?」
「・・・・・」
「それに。これがもし罠だとしても、苺に会えるかもしれないんだ。
オマエたちは行くだろ?」
「・・・・・」
「車は交換しよう。フィアットはオレが処分しておく。
そして。今日でこの仕事は最後にしろ。
ああ言っとくがな、荷物は盗品じゃないぞ。オレが描いた油絵だ」
「・・・・・」
「そろそろさ。平均的な平和と平均的な幸福を求めてみたらどうだ?」
「オマエは質問に答えてない。オマエはいったい何者なんだ?」
「だから宇宙人だって!」うずらが焦れったそうに言った。
「オマエは黙ってろ」
兎男はゲラゲラ笑って言った。
「オレに名前はないんだ。知り合いはオレをMと呼ぶけどな」
「それじゃ答えになってない」
「いいからこの住所の所へ行ってみればいい。
オレのやることはな・・・そつがないんだ」兎男はまたゲラゲラ笑いながら言った。
「さあ。2人とももう行け」
「オマエに関する情報が何もないのにこのまま行けるか!」
「うるさい。さっさと行け。
なあ頼む・・もう行ってくれ。
オレはもう限界なんだ!」
「・・・・・・?」
兎男が初めて怒気を含んだ声で言った。
「兎のぬいぐるみを被ってるとな・・・
暑いんだ!」
***
2人が乗った赤いサーブが東北自動車道の入口を目指し走り始めて10分位たったときだ。
うずらは「『あおもり犬』を観に行こう」と言い出した。
「あおもり犬?なんだそれ?」
「知らないのかよ。青森県立美術館にさ、奈良美智のでっかい犬のモニュメントがあるん
だぜ」
からすはこのまま行こう寄り道はなしだと言ったが、うずらは頑固に譲らなかった。
緑の芝生が敷き詰められた庭は、庭といより草原のような広さだった。芝生の草原の端に
白いL字型の美術館が建っていた。青い空と緑の芝生の間に白い美術館は建っていて、そ
れはまるで空と芝生と建築物でコラボレートした美術品のようだった。
「あおもり犬」は美術館に併設した壁囲いで青空天井になっている屋外トレンチに展示し
てあった。
高さ8.5mの白い犬が前足を床につけうつむいていた。奈良美智独特のなめらかな曲線で
造形された犬を観ていると心が軽くなった。
「なっ。観にきてよかったろ?」うずらはニッコリ笑った。うずらは照れくさそうに続け
た「実はさっき、兎男がオレにここへ行ってみろって言ったんだ」
「オマエがアイツの車に乗り込んだときに聞いたのか?」
「だって宇宙人と話したいじゃん」
「まだそんなこと言ってるのか・・」
「ここにくれば心が軽くなるから行ってみろって。心だけじゃない。身も心もだって。
ここは兎男の担当エリアなんだってさ・・」
「なんだ、担当エリアって・・?」
大きな犬のモニュメントの回りをたくさんの子供たちが走っていた。軽やかに跳ねていた。
うずらが言った「子供たちさ・・軽やかだろ?」
「ん・・?」
「いいか。兎男が言ってたことをやってみるぞ」うずらはポケットから100円硬貨を取り
出すと「見てろよ」と言い硬貨を真上に放り投げた。
落下してくる硬貨の「100」の文字がはっきり見える。小さな「平成20年」の文字もしっ
かり見えた。うずらは「兎男の言ったとおりだ」とはしゃいだ。
「えっ・・」と言ったからすに向かい「まっ。みたまんまだ」とうずらは言った。
「なっ。この屋外トレンチじゃ子供たちが軽やかなわけだ」うずらは笑った。
それから2時間後。2人が乗った赤のサーブは東北自動車道を南へ走っていた。
手紙の宛先は仙台市だった。
うずらが弾んだ声で言った「良かったなあ。苺に会える」
からすが不機嫌な声で応じた「オマエはアイツを信用するのか?」
「いいか。今日はワンダフルな日なんだ。北極点の白熊たちがぐいっと地軸を傾けて地球
にワンダフルがやってきたんだって」
「またそんなこと言ってるのか」
「オレもさ・・北極点地軸隊の・・白熊の夢を初めてみたときは半信半疑だった」
「それでも最初から半分は信じてたってことじゃないか。
おい。ちょっと待て。夢だって?その話は夢だったのか?」
「ああ」
「じゃあ何か。オマエは夢で見た話をオレに『知ってるか?』って聞いたのか!」
「そうだけど」
「そうだけどじゃない」
「だって何度も同じ夢を見るからさ、もしかしてみんな知ってるのかと思ってさ」
「ふざけるな」
うずらは大きな声で叫んだ「ワンダフルー!!」
目の前に岩手山が大きく迫っていた。岩手山を間近で観えるポイントが東北自動車道には
あった。岩手山は大きくてしかも優美だった。
それに、なんていうか・・気持ちの良いヤツだった。
岩手山を通り過ぎるとうずらは話を再開した。
「そっかあ。からすは北極点地軸隊の白熊たちのことは知らなかったのか…」
「誰が知るか・・」
「あっ。でもな、昨日の夜居酒屋で会った男に話したらさ、アイツは知ってたぞ」
「なんだって!」からすは思わずうずらの方をみた。ハンドルに力が入りサーブが右へ流
れた。からすは慌てて前を向いてハンドルを操作した。
うずらはサーブの蛇行にも無頓着で話し続けた。
「からすがトイレに行ってる時に話したんだ。
そしたらアイツは『ああ。その話なら知ってる』って」
「どうしてアイツは知ってたんだ?」
「聞いたことがあるらしい」
「誰から?」
「確かさ、『月男』とか・・言ってたぞ」
「・・・・・」
***
仙台市青葉区作並にある苺の家。彼女はテーブルに置いたスケッチブックに色鉛筆で花火
のデザイン画を描いていた。苺はコンピュータ・グラフィックでの花火デザインを避けて
いた。服のデザインも花火のデザインも同じだ。アイデアをラフスケッチするには脳と直
結した手描きじゃないと心が躍らない。
テーブルの上には写真が立ててあった。そこには花火師の祖父と幼い苺が写っていた。
苺は祖父と一緒に遊ぶのが好きだった。
源爺の口癖は『花火師は手品師であれ!』だった。
『いいか苺。夏の夜空に突然パッと咲いてパッと消える花火はな手品なんだ。
どっちも、おおすげえって驚くだろ。いいか大事なのはここなんだ。
花火も「すげえっ!」がなきゃなだめなんだ。「きれい」だけじゃだめなんだ』
『イリュージョンだね』
『・・?ああ・・そうだ。ロンドンの花火師イリュー・ジョンが1985年に・・』
『源爺。知ったかぶりして嘘ついたらもう遊ばないよ』
『うおっほん。だからな。イギリス人のイリュー・ジョンが驚くような花火を・・・』
『源爺!今後は会話の中で英語は禁止だからね』
『・・・・・』
『ところでね。源爺は知ってる?どうして猿が人間に進化したんだろ?』
『そんなことも知らないのか。
あのな。遠い遠い昔に…空からやって来た者たちが猿にパンツを穿かせたんだ』
『はあ…なにそれ?それとね。パンツは英語だよ』
『・・・・・』
花火のデザイン画を描き始めたけど・・これといったアイデアが出ない苺はふてくされた。
「ああ。もうっ」小さく叫んで苺は寝癖でとりちらかった長い髪を指で掻きむしった。
そんなときだ。
玄関のドアフォンが鳴るので、壁まで行きドアフォンの通話ボタンを押した。男の声で手
紙を届けにきたと言うので、苺は面倒くさそうに「郵便受けに入れて」と言った。すると
男の声が「受け取りのサインが必要なんだ」と返してきた。
苺は「ちょっと待って下さい」と言ってから溜息をついた。それから寝癖がついたままの
長い髪を無造作にまとめてアップにすると、後頭部にまとめた髪にかんざしの代わりにテ
ーブルに置いてあった色鉛筆を刺した。真上から垂直に色鉛筆を髪へ…すっと刺した。
苺が玄関ドアを開けると、そこにはからすとうずらが立っていた。
すぐには声が出ない3人。ややあって最初に口を開いたのはからすだった。
「やあ」からすはまるで昨日別れたみたいな気安さで言った。
「やあ」苺はさっきまで電話で話していたような親密さで答えた。
「雨が降りそうだな?」うずらは再会より空模様が気になっているようだった。
苺は両手を腰にあて、ずけずけと言った。
「ねえ。君たちさあ。わたしをみつけるまでいったい何年かかったと思ってるの」
「・・・・・」「・・・・・」
苺は目を瞑った猫のような目になって微笑んだ。それから。
両腕を胸の下で組んだ苺は5年前と同じ仕草で・・・首を左に傾けた。
「ほら見ろ!」うずらが小さく叫んだ。
「地軸が傾くとワンダフルが起きるんだ」
「・・・・・」
苺が顔を左に傾けると後頭部から頭上へ真っ直ぐ伸びていた色鉛筆も左へ・・・
地軸のように傾いていた。
予告(のようなもの)
拙作「そして僕はレシピを手にする」へのniceとコメントありがとうございました。
あたたかいコメントにとても励まされました。心から感謝いたします。
* **
実はですね。また書いてしまいました。
その分量が…もじもじ…またブログ掲載にはヘヴイな…
短編小説くらいの長さです。書き上げると偶然にも前作とほぼ同じ分量でした。
ここまで書いてきて…はたしてこれは予告か、と思ったのです。
分量だけを報告するのが…予告と言えるのか?
映画館のホールが暗くなり本編上映前の予告が始まった。
『「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」「ダージリン急行」の
奇才ウェス・アンダーソン監督最新作
「グランド・ブダペスト・ホテル」2014年6月公開!
上映時間:100分』
上映時間の情報だけで果たしてそれは予告か?
ボクは会社の近くにある食堂で日替わりランチのサバ味噌煮定食を食べ終えた。
明日の昼食もここに来ようかな…どうする?
顔なじみの女主人にボクは聞いた。
「おばちゃん。明日の日替わりランチは何?」
「総量で380g!」
この場合、分量は明らかに予告として機能していない。
しかし。内容を告げる予告が果たしてほんとうに良いのか?疑問も残る。
ボクの家に鶏がいるとしよう(実際に家にいるのはオスのサバトラ猫だが)。
彼は毎朝、1日の始まりを予告するように鳴く。
しかし、これからどのような1日になるのかは話さない。
もし彼が話すとしたら…どうだろう…。
「いいか、心を落ちつけるんだ。
これから始まる君の1日はかなりハードだ。
駅構内を歩いているとiPhoneにメールが届くことになる。
覚悟したほうがいい、心が折れるだけじゃすまいかもしれない」
朝からこんな話は聞きたくない。
「さっ。起きろ。今日はいつもより20分早く会社に着くんだ。
今年最大の幸福が君を待っている。おめでとう!
相手は『驚かせてごめんなさい』と言うだろう。でも君は驚かない。
だって今知ったから。そう君はノー・サプライズだ」
嬉しいかもしれないが心は踊らない。
今回も分量だけの予告(のようなもの)とさせて頂きます。
前作と殆ど同じで短編小説くらいの分量です。
お時間に余裕のあるときに読んで頂ければ幸いです。
また今回もタイトルが未決です。
「脳を揉む」時間を数日頂戴いたしたいと思います。
そして僕はレシピを手にする
なんにせよ奇妙な出来事に巡り逢うことはある。
森の蝉たちが鳴きやむように。木々をゆらす風が去るように。
それは不意にやってくる。
***
キリンが大きな瞳で僕をみていた。長い首を下げ僕の顔を正面からみていた。
3分ほどするとキリンは首をもとに戻して去っていった。
キリンは1度ふり返りニッと笑った。
横から笑顔の男が現れた。ダークなスーツを着た、額が後退した白髪の西洋人だった。
彼は満面の笑顔のままでこう言った。
『 Ready to suffer ?(キツいかも…大丈夫かな?)』
そんな夢だった。
それから僕は眠れなくなった。
正確には…1日に30分だけしか眠れなくなった。
* **
これは不眠症だ…。だって眠れないんだからきっとそうだ。
3日目にそう結論づけた。
5日目に総合病院の睡眠診療科を受診した。
検査結果に異常はなかった。
45才の男にしてはまだ充分に若い脳と肉体ですと担当医は言った。
「まあ君がロメインレタスだとしたらシーザーサラダに使うほど新鮮じゃないけど、
ハンバーガーには使うヘッドレタスくらいの新鮮さは保たれている」
睡眠診療科担当の50代前半の神経内科医は話を続けた。
「知ってるかい…シーザーサラダにヘッドレタスを使うレストランがあるんだ。
けしからん」
「それは初耳です…しかし僕が先生から聞きたいのはシーザーサラダのことじゃない」
「いいから聞きなさい。検査結果は異常ない、君は健康だ。ブラボーだ。
するとだ…不眠の原因は分からない。種も仕掛けもない不眠だ」
そう言って担当医は両手をヒラヒラと回した。
「原因不明の不眠がブラボーなもんか」
「いいかい。朝まで眠れなかったら精神は淀むかもしれない。
だから君は精神をフレッシュに保つために朝摘みのロメインレタスでつくったシーザー
サラダに思いを馳せて夜を過ごしなさい」
「・・・・・」
「かりかりのガーリック・クルトンに思いを馳せなさい…パルメザンチーズに、オリーブ
オイルに、塩胡椒に、白ワインビネガーに、ウスターソースに、半熟玉子に…思いを馳
せなさい…ほうら眠くなって…こない?」
「こない!」
処方された睡眠薬を飲んだが効果はなかった。
* **
幸いなことに30分だけの睡眠にも関わらず身体の調子に変化がなかった。
頭痛も倦怠感も疲労感も感じなかった。
困ったことは…30分の睡眠がなんの前触れもなく突然にやってくることだ。
僅か30分だけの突然やってきて突然去っていく睡眠は眠っていた記憶さへ残さなかった。
最初は会社のデスクでコンピュータの液晶画面に向かっている時、不意に睡眠が襲い睡眠
が去っていった。
液晶画面の時計が30分経過していたことに気づかなければ眠ったことにきづかなかった
筈だ。
数日すると周囲は慌てた。しばらくすると、突然動かなくなる男を周囲は持て余した。
その30分間の睡眠発作がいつ出現するか分からないからだ。
そしてそれが勤務中にやってきたときに周囲は慌て、持て余した。
困ったことがいくつもでてきた。
30分間の睡眠がいつ襲ってくるかが分からないのはやっかいなものだった。
車の運転は危険だった。エピソードを説明する必要もないだろう。
浴槽のお湯がもう少し多かったら溺れるところだった。以来シャワー浴だけにした。
会社のトイレは個室の洋式トイレに座ることにした。あまり人目を気にしない僕でも、
ペニスを出して眠りこける姿を同僚にみられるのは2度とごめんだ。
ある日の午後、デスクの内線電話にでると他の部署にいる同期の男からだった。
「おい。噂になってるぞ。オマエさ、ペニスを出すと失神する病気らしいな」
「明らかな誤解だ!しかし、内線電話で説明する気にはならない」
女友達とレストランで食事しているときだった。僕は突然前のめりにテーブルの上へ
うつ伏せに倒れ眠ってしまった。目覚めると彼女は興奮していた。
「びっくりした。私はあわてて君の背中をみたの。ほら映画でよくあるじゃない…
食事中の男が無言でテーブルに伏すと背中にナイフが刺さっているの。でも君の背中には
ナイフはなかった…」
別の女友達は僕が前のめりにテーブルの上の料理に倒れ眠ってしまうと帰ってしまった。
目覚めてから見たiPhoneメールで彼女は怒っていた。
「料理を台無しにしたことを怒っているんじゃないの。
私の話を聞いてるときに眠るのが許せないの」
さらに別の女友達との食事の時だ。僕はもう前に倒れるのは避けたいと思った。僕は椅子
に深くかけ重心を後ろへ傾け、反り返って座った。彼女は僕に言った
「今日はやけにエラそうね…」
困ったことはマーチングバンドのように集団で押し寄せてきた。
困ったことリストは順列組み合わせで増えていった。
トランペットが錆びたファンファーレを鳴らした。
* **
それから僕は夕食を自宅で1人で食べるようになった。
たいていは夜8時から9時には夕食をすませ音楽を聴いて本読んだ。
よく聞いたのはコールドプレイのアルバム『パラシューツ』だ。理由はとくにない。
きっと個人的なひそやかな長い夜にはこの1stアルバムがフィットしていたんだと思う。
みずみずしい朝摘みの野菜の歯触りと香りを思わせるこの曲達が。
音楽を聴き、本を読むときにはバーボンソーダを飲んだ。
酒を飲めばもちろん酔う、しかし眠くはならない。これがやっかいだった。
例えば…ハードリカーの重い酔いが脳を支配しても眠れないから飲み続ける。すると酔い
はますます重くなった。普段は物事を深く考えず処理して、悩んだりしない僕だが(言う
までもなく不眠には悩んでいたが)、重く深い酔いは脳の森に分け入り鬱屈を引きずり出
してきた。
僕は鬱屈の処理にはむいていない人間だったし、助けてくれる人もいなかった。
ボクシングのリングへマネージャーが投げるタオルのように、30分の睡眠がとんできて
眠れないかと思ったが…マネージャーも奇妙な不眠も追い詰められた選手の気持ちなんか
分かっちゃいない。眠れないまま鬱屈と対峙するのはやっかいだった。
「ああ。誰かこの試合を終わりにしてくれないか…」
その点、バーボンソーダの酔いは浅く軽い。酔っても眠れない45才の男には相応しい酒
だった。バーボンソーダの酔いは森に分け入ることがあっても鬱屈には出会わない。
バーボンソーダの酔いは浅く軽い。鬱屈には出会わないが…森の美女や賢者にも出会えな
かった。
僕は子供の頃から本を読むのも眺めるのも好きで良かったと今回はつくづく思った。
もし僕が本好きでなかったら、長い夜に精神が適応できずにイレギュラー・バウンドを起
こしたかもしれない。
以前まで睡眠にあてがわれていた7時間の夜を僕は読書で消費した。毎日7時間をかけ
て本を読んでいると7時間はけっして短くない時間であることに気づいた。7時間は職種
によっては1日の労働時間にも相当する長さだ。つまり僕は…「年齢・経験不問、但し読
書好きであること」という条件の仕事に就いたように毎日本を読んでいた。
勤勉な読書就労者だ。
もしその時間帯に睡眠が訪れても6時間30分の夜は残った。睡眠は読書勤務の短い休憩
にすぎない。
問題だったのは、7時間の時を忘れるくらいの面白い本を次々にストックしなければなら
ないことだった。
面白すぎる本に興奮して眠れなくなってしまったら…という心配は必要なかった。
深夜に本を読んでいると一緒に暮らしているオス猫が夜行性の親密さで話しかけてきた。
15才のキジトラ猫はしなやかさには欠けるが優美さをたたえた存在で、知恵と機知を併
せ持ったかっこうの話し相手だった。彼は会話には必ずジョークを挿入せずにはいられ
ない性格だった。
月は太陽がくれた光を謙虚に反射し夜を淡く照らし、ひかえめな口調で語りかけてきた。
45億才の月は昂揚や哄笑には無縁だが、内省と沈思が丁寧に紡いだ真理の言葉で僕の
部屋を優しく照らした。月は会話に愛をそそがずにはいられない性格だった。
しかし太陽が昇ると猫は眠り、月は消えた。
それでも僕の意識だけは残った。
猫と月との会話はもちろん観念的なものだ、ここで断るまでもなく。
不眠症が始まって1週間。幻覚がドアを開けて入ってくる気配さへなかった。
* **
僕は毎日本屋へ行き3冊の本を買った。ときに本は読んでいる途中で飽きたり失望したり
することがある、残念ながら。そこで1冊ではなく3冊にした。先発・中継ぎ・抑えだ。
しかしこの選択がなかなか難しい。運悪く先発・中継ぎ・抑えの出来が悪くてゲームが台
無しになるときがあった。つまりは3冊が3冊とも退屈で失望する出来のときだ。そん
なときは帯のキャッチコピーを「嘘つき」とののしった。立ち読みで読むであろう書き出
しの分量だけ面白い小説に遭遇したときは「この悪徳商法め」と呪った。
不眠が始まり2週間が経過したとき僕は書店で「睡眠学」、「不眠症」の本をまとめて
10冊買った。ついでに「シーザーサラダ」の本も1冊買った。
あの医者が言ったことを思いだしたからだ。
「眠れない夜は…シーザーサラダに思いを馳せて過ごしなさい」
うん。100匹の羊たちに思いを馳せるよりは、シーザーサラダの本を読むほうが楽しそう
だ。気まぐれに「羊飼い入門」というタイトルの本も買った。
午後9時に1杯目のバーボンソーダをつくり、「睡眠学」の本を開いた。学術的な専門
書ではなく、研究者が一般読者向けに書いた本だったが理解するのは困難だった。
3日前には…クルト・ゲーデル「不完全性定理」の入門書を読んだがまったく理解出来な
かった。半島の突端に1人取り残された気分になった。しかもそれが「抑え」の本だった
ので途方にくれて夜を過ごした。
「睡眠」の本を読んでみるとショートスリーパーという言葉が出てきた。世の中にはショ
ートスリーパーと呼ばれる短い睡眠時間でも健康が損なわれない人がいるらしい。ショー
トスリーパーはレム睡眠が圧倒的に少ないと書いてある。ほう。脳が活動している睡眠が
少ないなら夢をみることも少ないってことだな。ナポレオンの睡眠時間が3時間ってのは
聞いたことがあったが、レオナルド・ダ・ヴィンチは90分だったらしい。それでも
ダ・ヴィンチは僕の3倍の睡眠時間だ。それに僕のように睡眠が突然前ぶれもなく襲って
くることはなかったはずだ。
「不可解なスーパーショートスリーパー」なのか…僕は。
そして僕は夢をみなくなった。レム睡眠は立ち去り、ノンレム睡眠が残った…僕の30分
間の睡眠。
結局僕が読んだ本からは、この症状の問題解決の糸口はみつからなかった。
睡眠学の本は机に置いたままにして、シーザーサラダの本を開いた。
ローマ帝国のジュリアス・シーザーがこのサラダを好きだったという俗説があるがそれは
嘘だということだ。シーザーはこのサラダを作った料理人の名前だった。
メキシコにある人口140万人の都市ティファナ。アメリカとの国境沿いに位置する都市
だ。ティファナへはサンディエゴから車で15分、ロスアンゼルスからは車で3時間だっ
た。
1924年、ティファナで営業していたレストラン「シーザーズ・プレイス」のオーナー、
イタリア系移民のシーザー・カルディーニ、彼がシーザーサラダを作った男だった。
『・・・・・どういうことだ?』
その本にはページ半分の大きさのシーザー・カルディーニの写真が載っていた。
『おい。いったいどうなってるんだ・・・?』
5杯目のバーボンソーダをつくり一口飲んだ。
『本当にこの男がシーザー・カルディーニなのか?
彼がシーザーサラダを作った男なのか・・・?』
写真の中のシーザー・カルディーニは60代後半に見える男だった。ダークなスーツに
ドット柄のネクタイをしている男がフォークを左手に持ち木製のサラダボウルの前に立っ
ていた。
髪はサイドに白髪を残すだけで禿げあがっていた。黒く太い眉と大きな鼻の男は、目と頬
と口で笑顔をつくっていた。
忘れるもんか。
『 Ready to suffer ?(キツいぜ…覚悟はできてるか?)』
そう僕の夢の中で話しかけてきたあの男が写真の中で笑っていた。あのときと同じ笑顔で。
キリンが立ち去った後でふいに横から現れた男はシーザー・カルディーニだった。
キリンとシーザー・カルディーニが現れた夢をみてから僕の不眠症は始まった。
机の上に開いたままの睡眠学の本、左のページには表が載っていた。
それは動物の睡眠時間が記入された一覧表だった。
ヒト:6〜10時間
イヌ:10時間
ネコ:12〜13時間
ゾウ:3〜4時間
キリン:30分
僕は右ページの数行を読んで本を机に置いていた。つまり僕は表をみていなかった。
* **
僕は翌日病院へ行った。当然だ。シーザー・カルディーニが夢にでてきたあとに僕の不眠
症が始まった。僕が受診した睡眠診療科の神経内科医…たしか村木という50代の男だっ
た…村木は僕に言った「シーザーサラダに思いを馳せなさい」と。
いったいどういうことなんだ。
綜合病院のエントランスから中央ホールを横切り東棟1階の各科の外来診察室が並ぶ場所
へ歩いて行った。
しかしそこには睡眠診療科は…なかった。
僕はあわてて中央ホールに戻り総合受け付けの女性事務員に訊ねた。
彼女は小さい声だがきっぱりと言った。
「当院には神経内科はありますが、睡眠診療科という科はありません。
パソコンで職員名簿を検索してみましたが村木という医師は…いませんね」
僕はポケットから診察カードを出して彼女に渡した。そのカードを彼女はカードリーダで
読み込んだ。パソコンの画面に表示された情報をみて彼女は小さく首をふった。
ひかえめな声で彼女は言った。
「先週の受診記録はありませんね。3年前の整形外科の受診記録ならありますが・・」
睡眠診療科は元々ない…僕は先週どの科も受診していない。
ふう。
なにがおきているんだ?
奇妙なことがおきていることは確かだ。
それなのに僕は…睡眠診療科も僕を担当した医者も存在しないと聞いたとき、こう思った。
「やっぱりね」
やれやれ、どうやら僕は奇妙な物語に足を踏み入れたらしい。と、気づいたからだ。
奇妙な物語なら不思議なことが連続しておきるのだろう・・
そして今後もそれはおきるのだろう。
そのとき僕はまた少し慌てて溜め息まじりに、こう思うのだろう。
「やっぱりね」
* **
その日の夜11時、30分の睡眠が始まった。もちろん突然に。
カウチで横になり本を読んでいたときだったから突然意識がなくなっても問題はない。
当然のこと、突然意識が戻っても問題はない……はずだったのだが。
意識が戻ると、カウチと対面の壁に沿って置いたソファに男が座りウイスキーを飲んでい
た。
「23:00を過ぎたらウイスキーが美味しくなるのはなぜなんだ?」
男は大きな声で僕に話しかけてきた。それは質問にも聞こえるし、独り言にも聞こえた。
上下が白い麻のスーツを身につけた、でっぷりと肥った50代後半の男だった。
スーツ・ジャケットの下に黄色いYシャツを着ていたがネクタイはしていなかった。
髪は無かった。毛根さへ残らないスキンヘッドは、額と頭がシームレスに連続していた。
大きい目と太い鼻に薄い唇がついた顔は丸かった。それは生半可な丸さじゃない、顔の輪
郭ほぼ円形に近かった。それはほぼ破綻のない円だった。
奇妙な顔の男が、奇妙な出かたで僕の部屋に現れた。
僕はもう慌てることなく、溜め息もつかずに思った。
『やっぱりね』
男はウイスキーと大きな球形の氷が入ったグラスをテーブルに置き、キッチンにある冷蔵
庫からメーカーズマークの瓶を取り出した。
「オマエが眠ってる間にバーボンを冷蔵庫の中へ入れておいた。
いいか。バーボンソーダは氷で冷やすんじゃない、冷やしたバーボンで作るんだ。
氷で冷えるのを待っていたらソーダの炭酸が飛んで消えちまう」
「・・・・・」
「それからウイスキーグラスはだめだ。飲み口が広くて炭酸が逃げてしまう。
飲み口の小さいビールタンブラーにするんだ。
そして氷は最後に入れる。氷の上にソーダを注いだら炭酸が反射して飛んでいってしま
う。ほら。オレが作ったバーボンソーダを飲んでみろ」
「・・・・・」
僕は男が作ったバーボンソーダを飲んでみた。
バーボンとソーダの比率が寝起きの僕の身体に相応しい割合だった。
男が言うようにソーダの炭酸はフレッシュネスを損なわれていなかった。
「今まで飲んだバーボンソーダの中では、これがベストだ」
「当然だ」
「それじゃ、こういうことか。あなたはバーボンソーダ作りのプロフェッショナルで、
僕に美味しいバーボンソーダを飲ませるために僕が眠ってる間に家に入ってきたと」
「まさか。本気でいってるのか?」
「まさか!」
「だよな」
「あなたは何者なんだ?」
「オレか…オレは月だ」
ふう。『やっぱりね』と言うのはさすがに今回はためらわれた。
「確かに顔や体型は…満ちている。満月そのものだ。
それに…今夜は十五夜だ。
それじゃあ。あなたは日増しに欠けていくのか…損なわれていくのか?」
「バカ言え。いいか。月の満ち欠けは太陽との位置関係でそう見えるだけだ。
まあオレが月だって信じなくてもいいさ。
なあ。相談相手になってやるよ。1人で考えても解決がつかないときは年寄りに相談し
てみるもんだ」
「45億年分の経験と智恵を持つ年寄りに相談しろとでも……」
「ほう。オレが月だって理解したか」
「僕は理解する前に、大抵のことは受け入れるんだ」
「やっぱりね…と?」
「・・・・・」
「なあ。どうだ。一緒にメキシコへ行ってみようぜ」
「メキシコ…?」
「ティファナのシーザーズ・プレイスへ行ってみようぜ」
「あのシーザーズ・プレイスがまだ営業していることは本で読んだ。
だけどシーザー・カルディーニがシーザーサラダを作ったのは1924年だ。
今行っても彼に会えるわけがない」
「シーザー・カルディーニに会おうぜってオレが言ったか?」
「それじゃ何しにティファナへ行くんだ?」
「決まってる。美味しいシーザーサラダを食べるためさ」
「・・・・・」
「困ったときはくよくよ悩まないで美味いものを食べるにかぎる」
「あなたは相談相手になるために来たと言ったじゃないか?」
「いいか。困ったときは美味いもの食べて、満腹になって…ぐっすり眠ればいい。
朝になったら悩みなんか…」
「眠れない」
「・・・・・」
「僕は眠れないんだ」
「ゲラゲラ。そうだった。まあいいじゃないか。
シーザーズ・プレイスのシーザーサラダを食べにティファナへ行こうぜ」
「・・・・・」
「いいか。シーザーズ・プレイスじゃ料理人が客のテーブルの前でシーザーサラダを作っ
てくれるんだ。
大きな木製ボウルへ、にんにく、オリーブオイル、塩、胡椒、レモン汁、卵黄、
ワインビネガー、ウスターソースを入れてソースを作る。
そこへロメインレタスを入れてソースとからめる。
皿に盛りつけたら、かりかりのガーリッククルトンをのせ、チーズカッターから摺り
おろしたパルメザンチーズをふりかける。最後に半熟玉子をのせる。
大きなロメインレタスをナイフとフォークで切って口に運ぶ。
よく冷えたカリフォルニア・シャブリを飲む…どうだ?」
「・・・・・」
「うん…食べたくないのか?
分かった。オマエはバーボンソーダを飲んでいいぞ」
「いや僕はよく冷えたビールを飲むとしよう」
「じゃあ決まりだな」
「これから…あなたをなんて呼べばいい?名前をおしえてくれ」
「だからオレは月だ。そうだな…月と呼ぶのに抵抗があるならMと呼んでくれ。
オレはオマエをこれからもオマエと呼ぶことにする」
Mはニヤリと笑うと言った。
「How does it feel ?」(どんな気分だ?)
「極度の不眠症と突然やってくる睡眠発作。
夢にでてきたシーザー・カルディーニ。
シーザーサラダを思いなさいと言って消えた睡眠専門医。
僕の家に登場した月男。
やれやれ。
それで僕は今どんな気分かなだって?
まあ奇妙な物語のようではあるけれど…それでも、
ひとりぼっちの帰る家もなくした誰にも知られることのない…
転がる石になった気分じゃないな」
「ゲラゲラ。やっぱりオマエはボブ・ディランが好きだと思ってたんだ。
ひねくれ者だろオマエ、なあ」
「“ライク・ア・ローリング・ストーン”は僕が15才のときに撃たれた曲だ」
僕はMにつられて低い声で笑った。
Mが言った。
「1965年、ボブ・ディランは夢と現実を交換したんだ」
「夢と現実を…交換した…?」
Mは言った。1週間以内にメキシコへ飛べ。オマエはティファナのホテルで待っていろ、
オレがオマエの部屋へ行く。どのホテルでもオレにはすぐに分かる。オレは月だからな。
もちろんメキシコだろうがどこだろうがオレは道に迷うことはない。
「じゃあ今日はこれで帰る」
と言ったMの姿はおぼろに滲み部屋の景色に溶けて…消えた。
消えたMが数秒後にまた現れて言った。
「オマエさあ。キリンの睡眠時間を知ってるか?
たったの30分なんだぜ」
そう言い残してMは消えた。
キリンの睡眠時間は30分…。
『やっぱりね』
* **
見知らぬ町を歩いてる時に突然意識を失うことは避けたい。それでもホテルの部屋にこも
ってばかりいるのはいくらなんでもごめんだ。
シャワーを浴び、白いTシャツとグレーのカーゴパンツに着替え通りに出た。パンツの
ポケットに入れた紙にはホテルの電話番号とスペイン語でこう書かれていた。
『慌てないで。僕は眠っているだけなんだ。ほら。息をしている、脈も強く拍動してい
る。なにより血色が良い。30分すると目覚めるから心配はいらない。
愛を込めて』
ティファナ…時間を1/2世紀ほど遡上し時が停止したような建物の街並みの、アメリカと
の国境にあるメキシコの町。青い空に白い雲が羊の放牧のように群れていた。
通りを歩く外国人も多く特にアメリカ人の多さが目立った。調べてみると、アメリカ側の
国境の町サンイシドロまではサンディエゴから路面電車が出ていた。サンイシドロから国
境ゲートを通過しメキシコのティファナへ入国するには入国審査がない。メキシコはドル
をいつでもウエルカムということだ。ティファナからサンイシドロへ行くときは審査があ
る。アメリカはペソと一緒に持ち込まれる可能性のある物がウエルカムじゃないというこ
とだ。
ティファナの街中には薬局や歯医者が多い。通りすがりのアメリカ人の男は言った。アメ
リカで薬を買ったり治療を受けるより安いのさ。男はニヤリと笑った。多くのアメリカ人
がティファナを歩いてるのも頷けた。
ホテルへ戻り、部屋のベッドに座りテレビでサッカーの試合ををみていた。ふと気づくと
2つのチームがサイド・チェンジをしていた。30分眠ったらしい。物音に振り向くとM
が立っていた。時計をみると午後5時30分。月の登場には相応しい時間だ。赤基調の派
手な半袖開襟シャツと青いデニムのパンツ、黒いサングラスをかけた月は笑って立ってい
た。
レストラン「シーザーズ・プレイス」。
横に長く造られた建物の内部は白黒格子柄の床が長く伸び、白いクロスでおおわれた茶色
の木製テーブルが1列に並んでいた。とても長く。テーブルの列と平行にカウンター席が
あった。とても長いカウンターだ。古いレストランにしては照明が明るかった。サラダを
食べるには好感がもてる照明だ。
Mは予約をとっていた。
「月はそつがないんだ」と言ってククッと笑った。
店の人間に案内され僕とMはテーブル席にについた。
白Yシャツに黒のチョッキとネクタイ、腰から下は白エプロンの男がカートを押して僕
たちのテーブルに現れた。簡単な挨拶をすると男は大きな木製ボウルでシーザーサラダを
作った。そしてサラダを皿に盛りつけると男は去っていった。
僕は大きなロメインレタスをフォクークとナイフを使って切り分け口へ運んだ。
そうか、そういうことか。おろしたにんにくをサラダソースにつかっているのに、男は皿
に盛りつける前におろしにんにくを皿に塗りこんでいた。にんにくの香りが鼻腔を刺激し
軽く興奮した。
「・・・・・」
もう1度ロメインレタスを口へ運び、冷えた白ワインを飲んだ。良い出来のカリフォルニ
アシャブリだった。
「・・・・・」
Mもサラダと白ワインを交互に口へ運んでいた。時おり目をつぶりながら。
「・・・・・」
食べ終えるまで僕とMは一言も言葉を発しなかった。勤勉な機織りのような食事だった。
「・・・・・」
「・・・・・」
僕とMはほぼ同時に食べ終えるとゲラゲラ笑った。
美味しいサラダとワインのおかげで僕たちの脳は無防備に服を脱ぎすて開放されたらしい。
笑いは数分たってもおさまらなかった。
笑いが止むとMが聞いてきた。
「おい。この店のサラダを食べてみてどうだった?」
「素晴らしい。僕のサラダ歴の中ではベスト・オブ・ベストだね」
「そうじゃない。オマエの夢にでてきたシーザー・カルディーニの店でだ…ヤツが考案し
たサラダを食べたんだぞ」
「もちろんオリジナルにも興味はあるけど今食べたサラダは素晴らしかった」
「そうじゃない。今オマエに起きてる奇妙なことの謎に迫る何かを思い出さないのか?」
「ない。何も思い出さないし、何も思い浮かばない」
それからピノ・ノワールの瓶を開けた。チーズと干し葡萄をかじりながらルビー色のワイ
ンを僕たちは飲んだ。
「オマエはどうして奇妙な出来事に出会っても慌てないんだ?」
「じゅうぶん慌てているけど」
「オレにはそうみえない。
オレは毎晩オマエを空から観察していた。
本と音楽とバーボンソーダ。それだけだ。
慌てない、嘆きも怒りもない。
せいぜい溜め息くらいのもんだ。
次の夜も、また次の夜も…本と音楽とバーボンソーダ。それだけだ」
Mは両切りの煙草に火をつけ一息吸うと大きく煙を吐き出した。
「奇妙な出来事もオマエはそのまま受け止めて、あわてない。
やっぱりね…なんて思ってる。そうだろ?」
「僕の祖父はタイのゴム農園で働いていたことがる」
「・・うん?」
「ゴムの反発係数は小さい、石や木や金属と比べるとね」
「何を言ってる?」
「反発係数が限りなく0(ゼロ)に近い非弾性ゴムがある」
「・・・・・」
「衝突したモノを跳ね返さない」
「・・・・・」
「受け入れるんだ」
「じゃあ何か…オマエの心はゴムなみの反発係数で奇妙なことも受け入れるのか?」
「まさか。僕の心はゴムじゃない。
それでも僕は子供のころからあまりにもムチャなことに出会うと…」
「出会うと・・・」
「ああ運命かもしれないと思うところがあった」
「ふん。そんなことだと思ったぜ」
次に太陽がぎっしり詰まったような100%シラーの瓶を開けた。濃赤色のワインの酔いは
さざ波のように寄せてきたけど眠くはならない。月はもちろん眠らない。
「僕の眠りを何者かが持ち去った…あるいは僕の眠りは自律的に立ち去った」
「自律的に立ち去った眠り…不思議なことだ」
「でも僕にとって最も不思議なことは…月とワインを飲みながら話していることだ」
「夢かもしれない」
「まさか」
「だよな。眠れないんじゃ夢はみれない」
「・・・・・」
「自律的に立ち去った眠りか…オマエに失望して立ち去った友人のように」
「・・・・・」
「もしくはオマエが退屈な友人から立ち去ったときのように」
「僕が眠りは自律的に立ち去った…退屈だから、もしくは失望したから?」
***
昨夜Mはこう言い残して消えた。
「マヤの遺跡を訪ねてみろ」
「どうして?」
「旅に必要なものはなんだ?」
「・・・・・」
「ロマンだ!」
Mは赤ワインのタンニンが着色した歯を剥き出してゲラゲラ笑っていた。
朝になると僕は荷物をまとめてティファナのホテルを出た。バスで国境ゲートへ向かい、
入国審査をすませアメリカ側の国境の町サンイシドロへ入った。そこから路面電車に乗り
サンディエゴの街に入るとタクシーをつかまえサンディエゴ国際空港へ向かった。ティフ
ァナからサンディエゴの空港まではわずか24kmだった。
目的地はメキシコ南部ユカタン州のウシュマル遺跡。
サンディエゴ国際空港で運良くエアロメキシコのキャンセルチケットを手に入れ、ユカタ
ン州メリダへ飛んだ。さらに運が良かったのは飛行機に乗り込むまで眠りがやってこなか
ったことだ。しかし、5時間50分の飛行時間の間に消化したかった眠りはメリダ国際空
港に着くまで残念ながらやってこなかった。ここからウシュマルまではレンタカーだ。空
港内で眠りをやり過ごすほかなかった。
僕は空港ロビーのベンチに座り眠りをじっと待った。やがて眠りは訪れ30分後に去って
いった。
オーケイ、23時間30分の1日の始まりだ。
レンタカーに乗り込み国道261号線に入った。ここからウシュマルまで110km、もう目
の前だ。1時間30分後にウシュマルに入り最初に目についたホテルに飛び込みでチェッ
クインした。
ユカタン州ウシュマル、人口2万5千人の町。
ユカタンはマヤ語で「お前の言っていることは解らない」らしい。
やれやれ、わからないことだらけだ。
ウシュマルはマヤ語で「3度にわたり建てられた町」。
時代に押しやられたこの町に4度目はなかった。
荷物を部屋に放り込み、タクシーで「魔法使いのピラミッド」へ向かった。
腕時計の液晶表示は15:30だった。
魔法使いのピラミッド。
魔法使いの老婆が温めた卵から生まれた小人が1夜のうちに創ったという伝説があった。
楕円形の土台に建てられた巨大なピラミッドだ。頂点には神殿を戴いていた。
高さ36m、およそ12階建のマンションと同じ高さだ。
ピラミッド土台の楕円形の幅は高さと同じ36m、長さは73mもあった。
果てなくどこまでも広がる青い空の下、白い石組のピラミッドが緑の草地の上に建ってい
た。
ピラミッド近づいてみると、それは精巧に切り取られた石を組み合わせて造られていた。
斜面全体には凹凸が殆どないように整えられ、楕円形の4つ角は破綻のない見事な曲面を
描いていた。
思わず息をのむそれは、約1200年前のマヤの人々が建てた神話だ。
ピラミッドの斜面しつらえられた118段の階段は、遠くから見るのと違い実際に昇り始
めると気が遠くなるような急傾斜で壁をよじ登るような勾配だった。
夕刻に近づいても太陽は容赦なく照りつけ、僕は汗を拭うのも息を整えるのも面倒くさく
なりただただ黙々と昇った。この階段を昇り始めたことを心底後悔したころに頂上にある
神殿の断片が見えてきた。
神殿にたどり着いたときには陽が傾き始めていた。
そこには予想通りMが立っていた。
Mは瓶ビールを2本持っていて、蓋を開けて待っていた。それはよく冷えたコロナビー
ルで瓶の中にはカットしたライムまで入っていた。
ふう。月のやることは…そつがない。
軽いテイストの冷えたビールを飲みながら180度に広がる地平線を眺めているとMが話
しかけてきた。
「知ってるか…マヤは“時間・周期”という意味だ。つまり彼らは自らを、“時の民”と呼ん
でいたんだ」
「・・・・・」
「金属を持たない石の文明、農耕は単純な焼き畑だ。それなのに高等数学を使い天文学を
操っていたとされる。なんといっても0(ゼロ)の概念を発明したんだからな」
「・・・・・」
「いいか。彼らは20進法を操り1年が350日の暦を作り、9世紀には月や火星や金星の
軌道も計算していたんだぞ」
Mはポケットからメモ帳を取り出すと3つの記号を書いた。
睫毛のない仏像の目のようなもの、丸い点、横棒。
「これは記号じゃない数字だ。
マヤの20進法は、0と1と5で表現する。丸い点が1だ。横棒は5だ。
0から19の20進法で…19はこう表す」
Mは手帳に丸い点を横並びに4つ書き、4つの丸点の下に横棒を3本書いた。
「これが19だ」
「この…目のような記号は?」
「これは0(ゼロ)だ。それにな、これは目じゃない。月だ。
数学の起点のゼロは…月なんだ」
そう言ってMはニヤリと笑った。
「起点は…月?
時の民が操った天文学、それを支えた数学の起点が…月だって?」
Mはそれには答えずゲラゲラ笑った。
夕空には星々の明りがまたたいていた。Mはこうきりだした。
「どうしてマヤの民は星々の運行を観察し暦をつくったんだ?」
「・・・・・」
「どうして自らを“時の民”と呼んだんだ?」
「・・・・・」
「この世界で不変なものは時間だと知っていたんじゃないか。
一定の速度で移動する普遍なものが時間だと気づいていたんじゃないか」
「月の満ち欠け…」
「そうだ。月の満ち欠けはサイン(象徴)じゃない、時間の移動だと気づいたんだ」
「時間の起点は月…月は0(ゼロ)」
「うん。オレもそう思う。月のオレだってそう思う」
Mはゲラゲラと長く笑った。
「なあ。単純に考えないか。
オマエの内部で意識の“時間”がちょっと移動しただけなんだ。眠りから覚醒へ。
オマエの暦が書き換わったんだ」
「・・・・・」
「オマエは眠りが立ち去ったと思ってるけどな…こうは考えられないか。
覚醒した意識の時間がやって来たんだ」
「・・・・・?」
「眠りと覚醒の2進法だ」
「眠りが0で、覚醒が1の2進法。
0と1で書かれた脳のプログラム・コードの中の1が増加した。
そして0は…月」
「そりゃあ、人間が眠るときは月の出番だからな。ゲラゲラ」
「・・・・・」
「眠りは無意識の意識だ。
無意識より覚醒した意識のほうが面白いに決まっている。
なあ。眠りを取り戻すことなんか忘れてしまえ!」
***
成田から自宅に戻りソファに座ると同時に眠りがやってきた。
僕は夢をみた。確信はないがそれはおそらく夢だ。
不眠症になってから初めてみる夢だ。
僕は森を歩いていた。
僕が生まれた町の神社に連なる大きな森だ。
僕が子供の頃に、よく1人で遊んでいた森だ。
でもこれは夢だ。
現実と違い、それは大きく深い森でどこまで歩いても森は終わらなかった。どこまでも。
木洩れ陽の指す方角が東だとみきわめ、一定方向へ向かって歩き続けたが森は尽きなかっ
た。
鳥のさえずりが聞こえる。虫の声も聞こえる。緑に染まった空気が漂っている。
樹木の翳から栗鼠が出てきて立ち止まり僕をじっと見ていた。
歩き疲れた僕は下生えの草の上に寝転んだ。
頬をチクチク刺激する草の感触と匂いが心地よかった。
どれくらい眠っただろう。
目覚めると樹木の間から5年前に亡くなった父親が出てきた。
乱暴で口数が多く(しかも口うるさい)、そのくせ息子思いの父親だった。
僕が油断するとしっぺ返しにあう、取り扱いに注意を要する面倒な父親だった。
そして僕は父親が好きだった。
「おい。こんな所で眠ってるんじゃねえ、ほら、起きろ」
「・・・・・」
「久しぶりに会ったからってな、オマエと話すことなんかオレにはねえ。
ほら、とっとと行け」
そこにMが現れ父親の隣に立った。
「おい月!オマエは余計なことをコイツに言うんじゃねえぞ。
月はなんでも知ってるそうじゃねえか。いいか、コイツに入れ知恵するな!
コイツは自分で考えんなきゃいけないんだ」
Mはゲラゲラ笑い出したが父親は構わず話し続けた。
「おい月!ありがとな。コイツが世話になった。
コイツは森に来なきゃいけなかったんだ。
コイツは森を歩かなきゃいけない。そうしないと何も始まらない」
Mはニヤニヤ笑うだけで何も話さなかった。
「おい眠ってなんかいないで考えろ。
眠ってなんかいないで森を前に進め。
森をただ歩くんじゃない。森をイメージしろ。
目を閉じるな。足を動かせ。森を歩くんだ。考えるんだ。
イメージしろ」
「・・・・・」
「そうすりゃ、オマエはなにかに出会い、なにかを手にする」
「・・・・・」
「おい月!コイツは1人で行かなきゃいけない。オマエもオレも一緒には行けない。
コイツは1人で歩かなきゃいけないんだ。
おい月!オマエはここに残ってオレの話し相手になれ。ギャハハ」
僕はそれからしばらく森の中を歩いた。森をイメージして森を歩いた。
1時間くらい経つと父親は僕の頭の中へ直接話しかけてきた。
父親は森の住人となった今でも話好きなのは変わっていなかった。
『いいか。人間に生まれて面白いことはなんだ?前に向かって歩くことだ。
人間やってて楽しいことはなんだ?考えることだ。
眠れねえなんて上等じゃあねえか。
歩く時間と考える時間が増えたってことだ。
森を前へ進むんだ。そして…考えるんだ
そうすりゃ、オマエはなにかに出会い、なにかを手にする』
遠くに見える木洩れ日の光量が急に大きくなった。
***
翌日僕は本屋へ行き、森に関する本を買ってきた。
森林は、草原など他の植物群落よりはるかに多い動物が住む。地上生物のあらゆる型のも
のが森林には生息する…。と、書いてあった。
森とは…あらゆる形態の生物を保持する世界。
数学では…閉路を持たない無向グラフを「森」という。
なんのことだ?本では鉄道路線図のイラストを使って解説されていたが僕には理解できな
かった。
僕には…その路線図のイラストが枝々を伸ばした木に見える、ということだった。
森なるものは閉路をもたない無向なもの…そして、あらゆる形態の生物を保持する。
よくは分からないが、それはもう構わないと思った。
僕は森へ行こうと思った。森なるものへ向かおうと思った。
あらゆる形態の生物が生息する世界をイメージした。
閉じないフィールドをイメージした。
***
この数週間のうちに僕が巡り逢った奇妙なことを思った。
夢に現れたキリンとシーザーサラダを作った男。
自律的に立ち去った僕の眠り。
シーザーサラダを語る睡眠専門医。
本の写真で見たシーザーサラダを作った男。
消えた睡眠診療科と睡眠専門医。
部屋に現れた、月だと名乗る男。
そして。マヤ文明が編み出した数学の起点の0(ゼロ)は月。
「始まりは月。
全ては君の手配したことなんだね」
目の前のソファの上にMが現れ座っていた。
「・・そう。全てはオレの仕業だ。月のやることには…そつがない」
「やっぱりね」
「分かってたんだろ?」
「うん。
たくさんの不思議なことも大抵の場合は1本の紐でつながるのが世界だ」
「そしてオマエはこれから森を歩く」
「うん。そうすると思う」
「それは良かった」
「どうしてMは僕を選んだのかな?」
「選んじゃいない。」
「Mはいったいどこへ僕を導くつもりだ?」
「オレはオマエを選んじゃいないし、どこへも導かない。
これはオマエが望んだことだ」
「僕が望んだこと…?」
「気づいていなかっただけだ。
オレがやったことは…気づきをオマエに投げかけただけだ」
「気づき・・・」
「そう。気づきだ。
オマエはあるフレーズのある楽器の音を望んでいた。
オレはピアノの録音ファイルの音圧を少し上げた」
「僕は多くの楽器が奏でる演奏の音からピアノの音に気づく。
そしてそれを僕は望んでいた」
「そうだ」
「人は誰だって望んだようにしか生きられない」
「望むままにに生きられる人は少ないと思う」
「簡単なことだけど実行する人間は少ない」
「・・・・・」
「誰にだって望む夢がある」
「夢に蓋をする現実もたっぷりある」
「簡単なことだ。
夢と現実を交換するんだ」
「夢と現実を交換する・・・?」
「夢をみて生きる。現実をみるのは眠ってる時だけ。
覚醒した意識でリアルに夢を生きるんだ」
「そして僕は森を歩く」
「そうだ」
「木々と樹液の匂い、下草と苔の香り、森に住む生物たちの音、木洩れ日がつくる日溜ま
りの温かさ…その中を歩く」
「森はオマエにとってときにイノセントな存在じゃないかもしれない。
むしろ狡猾な黒い森となってオマエを搦め取ろうとするかもしれない」
「もしくは森が内包する混沌に僕は対応できずに煩悶するかもしれない」
「混沌に出会ったら少し調整すればいい。
ピアノ調律師が弦の張りを調整して音の混沌から光りをみつけるように」
「そんなこと…できっこない」
「はっはっは…」
「それでも僕は森を歩く」
「そうだ。立ちどまっているわけにはいかない。
オマエは森を歩き…なにかに出会い、なにかを手にするんだ」
「僕は森でなにかに出会い、なにかを手にする…それが僕のレシピだ」
「もしくは…なににも出会わず、なにも手にしないかもしれない」
「森の美女には出会えず、森の賢者の智恵を手にすることができなくても…
月に出会い、月の智恵を手にするかもしれない」
「ゲラゲラ。悪くない…そいつは悪くない出会いだ」
「オーケイ。僕は森を歩くことにする」
「あるいは森なるものの中を。
オマエにとっての森性なるものの中へわけいることになる」
「僕にとっての森性なるもの……」
* **
3日間かけて森なるものをイメージしてみた。
それでもイメージは玄関ドアをノックしないし、バスルームの窓から入ってくることもな
かった。
それでも歩くことにした。歩いていれば、そのうち僕が分け入る森に出会うことになって
いるのだろう。きっと。
少なくとも立ち止まっていては森に出会うことはできない。
キッチンの物音へ目をやると、そこにMが立っていた。
「何をしている?」
「バーボンソーダを作ってる」
「僕にも作ってくれ」
「分かった。
それで…どこに行くことにした?」
「明日、ハノイへ向かうことにした」
「どうしてベトナムなんだ…」
「どうしてだろ…?そんな気分なんだ…としか言えない」
「ゲラゲラ。うん。そいつは悪くない。気分にまかせるのは悪くない」
「それに…」
「それに…?」
「ベトナム料理は美味しいし、ビールも僕の好みだ」
「うんうん。オマエが美味い料理とビールに惹かれる土地なら…
そこにはオマエが行かなきゃならない森があるんだろう」
Mはバーボンソーダを2つ作って持って来た。
「1つ質問に答えてくれ。どうして僕の眠りは予期せず突然やってくるんだ?
森を探す旅に向かうのにこの眠りはやっかいだ」
Mはゲラゲラ笑いながら答えた。
「そいつは脳のオーバーフローだ。それで脳が突然シャット・ダウンする」
「コンピュータの強制終了みたいに?」
「そうだ」
「どうして?」
「人間の脳の休息には30分は短すぎたからだ。
月だってときにはミスをおかす。ゲラゲラ。
心配するな。90分に調整しておいた。ダ・ヴィンチなみの充分な睡眠だ。
明日からは不意打ちの眠りが襲ってくることはない」
2人ともバーボンソーダを飲み終えるとMはこうきりだした。
「オマエはもう気づいていると思うが…今日でお別れだ」
「うん。そうだと思った」
「オマエが1人で歩き続ける気になったならオレの出番はない」
「うん。君が歩く気にしてくれた。ありがとう。
月のやることは、そつがない」
「ゲラゲラ。そうだ。月のやることは、ぬかりがない!」
笑いながらMの姿はおぼろに滲み部屋の景色に溶けて…消えた。
部屋の壁に嵌め込んだ飾り棚の上のラジオから突然音が流れてきた。
ラジオ局をチューニングする音が数秒鳴った。
突然…イントロなしのジョン・レノンのシャウトが大音量で始まった。
やっぱりね。
ふふっ。月のやることには…そつがない。
ミスター・ムーンライト
あの夏の夜に君は僕の目の前にあらわれた
君のやさしい光りが僕を夢心地にしてくれた
君は世界中から探して彼女を僕へ届けてくれた
君は空の上から僕と彼女に愛を届けてくれた
そして今、彼女はぼくのもの
ねえミスター、君は素敵な月明かりだね
ねえミスター、僕も彼女も君が大好きなんだ
The Beatles “ Mr. Moonlight “
森の蝉たちが鳴きやむように。木々をゆらす風が去るように。
それは不意にやってくる。
***
キリンが大きな瞳で僕をみていた。長い首を下げ僕の顔を正面からみていた。
3分ほどするとキリンは首をもとに戻して去っていった。
キリンは1度ふり返りニッと笑った。
横から笑顔の男が現れた。ダークなスーツを着た、額が後退した白髪の西洋人だった。
彼は満面の笑顔のままでこう言った。
『 Ready to suffer ?(キツいかも…大丈夫かな?)』
そんな夢だった。
それから僕は眠れなくなった。
正確には…1日に30分だけしか眠れなくなった。
* **
これは不眠症だ…。だって眠れないんだからきっとそうだ。
3日目にそう結論づけた。
5日目に総合病院の睡眠診療科を受診した。
検査結果に異常はなかった。
45才の男にしてはまだ充分に若い脳と肉体ですと担当医は言った。
「まあ君がロメインレタスだとしたらシーザーサラダに使うほど新鮮じゃないけど、
ハンバーガーには使うヘッドレタスくらいの新鮮さは保たれている」
睡眠診療科担当の50代前半の神経内科医は話を続けた。
「知ってるかい…シーザーサラダにヘッドレタスを使うレストランがあるんだ。
けしからん」
「それは初耳です…しかし僕が先生から聞きたいのはシーザーサラダのことじゃない」
「いいから聞きなさい。検査結果は異常ない、君は健康だ。ブラボーだ。
するとだ…不眠の原因は分からない。種も仕掛けもない不眠だ」
そう言って担当医は両手をヒラヒラと回した。
「原因不明の不眠がブラボーなもんか」
「いいかい。朝まで眠れなかったら精神は淀むかもしれない。
だから君は精神をフレッシュに保つために朝摘みのロメインレタスでつくったシーザー
サラダに思いを馳せて夜を過ごしなさい」
「・・・・・」
「かりかりのガーリック・クルトンに思いを馳せなさい…パルメザンチーズに、オリーブ
オイルに、塩胡椒に、白ワインビネガーに、ウスターソースに、半熟玉子に…思いを馳
せなさい…ほうら眠くなって…こない?」
「こない!」
処方された睡眠薬を飲んだが効果はなかった。
* **
幸いなことに30分だけの睡眠にも関わらず身体の調子に変化がなかった。
頭痛も倦怠感も疲労感も感じなかった。
困ったことは…30分の睡眠がなんの前触れもなく突然にやってくることだ。
僅か30分だけの突然やってきて突然去っていく睡眠は眠っていた記憶さへ残さなかった。
最初は会社のデスクでコンピュータの液晶画面に向かっている時、不意に睡眠が襲い睡眠
が去っていった。
液晶画面の時計が30分経過していたことに気づかなければ眠ったことにきづかなかった
筈だ。
数日すると周囲は慌てた。しばらくすると、突然動かなくなる男を周囲は持て余した。
その30分間の睡眠発作がいつ出現するか分からないからだ。
そしてそれが勤務中にやってきたときに周囲は慌て、持て余した。
困ったことがいくつもでてきた。
30分間の睡眠がいつ襲ってくるかが分からないのはやっかいなものだった。
車の運転は危険だった。エピソードを説明する必要もないだろう。
浴槽のお湯がもう少し多かったら溺れるところだった。以来シャワー浴だけにした。
会社のトイレは個室の洋式トイレに座ることにした。あまり人目を気にしない僕でも、
ペニスを出して眠りこける姿を同僚にみられるのは2度とごめんだ。
ある日の午後、デスクの内線電話にでると他の部署にいる同期の男からだった。
「おい。噂になってるぞ。オマエさ、ペニスを出すと失神する病気らしいな」
「明らかな誤解だ!しかし、内線電話で説明する気にはならない」
女友達とレストランで食事しているときだった。僕は突然前のめりにテーブルの上へ
うつ伏せに倒れ眠ってしまった。目覚めると彼女は興奮していた。
「びっくりした。私はあわてて君の背中をみたの。ほら映画でよくあるじゃない…
食事中の男が無言でテーブルに伏すと背中にナイフが刺さっているの。でも君の背中には
ナイフはなかった…」
別の女友達は僕が前のめりにテーブルの上の料理に倒れ眠ってしまうと帰ってしまった。
目覚めてから見たiPhoneメールで彼女は怒っていた。
「料理を台無しにしたことを怒っているんじゃないの。
私の話を聞いてるときに眠るのが許せないの」
さらに別の女友達との食事の時だ。僕はもう前に倒れるのは避けたいと思った。僕は椅子
に深くかけ重心を後ろへ傾け、反り返って座った。彼女は僕に言った
「今日はやけにエラそうね…」
困ったことはマーチングバンドのように集団で押し寄せてきた。
困ったことリストは順列組み合わせで増えていった。
トランペットが錆びたファンファーレを鳴らした。
* **
それから僕は夕食を自宅で1人で食べるようになった。
たいていは夜8時から9時には夕食をすませ音楽を聴いて本読んだ。
よく聞いたのはコールドプレイのアルバム『パラシューツ』だ。理由はとくにない。
きっと個人的なひそやかな長い夜にはこの1stアルバムがフィットしていたんだと思う。
みずみずしい朝摘みの野菜の歯触りと香りを思わせるこの曲達が。
音楽を聴き、本を読むときにはバーボンソーダを飲んだ。
酒を飲めばもちろん酔う、しかし眠くはならない。これがやっかいだった。
例えば…ハードリカーの重い酔いが脳を支配しても眠れないから飲み続ける。すると酔い
はますます重くなった。普段は物事を深く考えず処理して、悩んだりしない僕だが(言う
までもなく不眠には悩んでいたが)、重く深い酔いは脳の森に分け入り鬱屈を引きずり出
してきた。
僕は鬱屈の処理にはむいていない人間だったし、助けてくれる人もいなかった。
ボクシングのリングへマネージャーが投げるタオルのように、30分の睡眠がとんできて
眠れないかと思ったが…マネージャーも奇妙な不眠も追い詰められた選手の気持ちなんか
分かっちゃいない。眠れないまま鬱屈と対峙するのはやっかいだった。
「ああ。誰かこの試合を終わりにしてくれないか…」
その点、バーボンソーダの酔いは浅く軽い。酔っても眠れない45才の男には相応しい酒
だった。バーボンソーダの酔いは森に分け入ることがあっても鬱屈には出会わない。
バーボンソーダの酔いは浅く軽い。鬱屈には出会わないが…森の美女や賢者にも出会えな
かった。
僕は子供の頃から本を読むのも眺めるのも好きで良かったと今回はつくづく思った。
もし僕が本好きでなかったら、長い夜に精神が適応できずにイレギュラー・バウンドを起
こしたかもしれない。
以前まで睡眠にあてがわれていた7時間の夜を僕は読書で消費した。毎日7時間をかけ
て本を読んでいると7時間はけっして短くない時間であることに気づいた。7時間は職種
によっては1日の労働時間にも相当する長さだ。つまり僕は…「年齢・経験不問、但し読
書好きであること」という条件の仕事に就いたように毎日本を読んでいた。
勤勉な読書就労者だ。
もしその時間帯に睡眠が訪れても6時間30分の夜は残った。睡眠は読書勤務の短い休憩
にすぎない。
問題だったのは、7時間の時を忘れるくらいの面白い本を次々にストックしなければなら
ないことだった。
面白すぎる本に興奮して眠れなくなってしまったら…という心配は必要なかった。
深夜に本を読んでいると一緒に暮らしているオス猫が夜行性の親密さで話しかけてきた。
15才のキジトラ猫はしなやかさには欠けるが優美さをたたえた存在で、知恵と機知を併
せ持ったかっこうの話し相手だった。彼は会話には必ずジョークを挿入せずにはいられ
ない性格だった。
月は太陽がくれた光を謙虚に反射し夜を淡く照らし、ひかえめな口調で語りかけてきた。
45億才の月は昂揚や哄笑には無縁だが、内省と沈思が丁寧に紡いだ真理の言葉で僕の
部屋を優しく照らした。月は会話に愛をそそがずにはいられない性格だった。
しかし太陽が昇ると猫は眠り、月は消えた。
それでも僕の意識だけは残った。
猫と月との会話はもちろん観念的なものだ、ここで断るまでもなく。
不眠症が始まって1週間。幻覚がドアを開けて入ってくる気配さへなかった。
* **
僕は毎日本屋へ行き3冊の本を買った。ときに本は読んでいる途中で飽きたり失望したり
することがある、残念ながら。そこで1冊ではなく3冊にした。先発・中継ぎ・抑えだ。
しかしこの選択がなかなか難しい。運悪く先発・中継ぎ・抑えの出来が悪くてゲームが台
無しになるときがあった。つまりは3冊が3冊とも退屈で失望する出来のときだ。そん
なときは帯のキャッチコピーを「嘘つき」とののしった。立ち読みで読むであろう書き出
しの分量だけ面白い小説に遭遇したときは「この悪徳商法め」と呪った。
不眠が始まり2週間が経過したとき僕は書店で「睡眠学」、「不眠症」の本をまとめて
10冊買った。ついでに「シーザーサラダ」の本も1冊買った。
あの医者が言ったことを思いだしたからだ。
「眠れない夜は…シーザーサラダに思いを馳せて過ごしなさい」
うん。100匹の羊たちに思いを馳せるよりは、シーザーサラダの本を読むほうが楽しそう
だ。気まぐれに「羊飼い入門」というタイトルの本も買った。
午後9時に1杯目のバーボンソーダをつくり、「睡眠学」の本を開いた。学術的な専門
書ではなく、研究者が一般読者向けに書いた本だったが理解するのは困難だった。
3日前には…クルト・ゲーデル「不完全性定理」の入門書を読んだがまったく理解出来な
かった。半島の突端に1人取り残された気分になった。しかもそれが「抑え」の本だった
ので途方にくれて夜を過ごした。
「睡眠」の本を読んでみるとショートスリーパーという言葉が出てきた。世の中にはショ
ートスリーパーと呼ばれる短い睡眠時間でも健康が損なわれない人がいるらしい。ショー
トスリーパーはレム睡眠が圧倒的に少ないと書いてある。ほう。脳が活動している睡眠が
少ないなら夢をみることも少ないってことだな。ナポレオンの睡眠時間が3時間ってのは
聞いたことがあったが、レオナルド・ダ・ヴィンチは90分だったらしい。それでも
ダ・ヴィンチは僕の3倍の睡眠時間だ。それに僕のように睡眠が突然前ぶれもなく襲って
くることはなかったはずだ。
「不可解なスーパーショートスリーパー」なのか…僕は。
そして僕は夢をみなくなった。レム睡眠は立ち去り、ノンレム睡眠が残った…僕の30分
間の睡眠。
結局僕が読んだ本からは、この症状の問題解決の糸口はみつからなかった。
睡眠学の本は机に置いたままにして、シーザーサラダの本を開いた。
ローマ帝国のジュリアス・シーザーがこのサラダを好きだったという俗説があるがそれは
嘘だということだ。シーザーはこのサラダを作った料理人の名前だった。
メキシコにある人口140万人の都市ティファナ。アメリカとの国境沿いに位置する都市
だ。ティファナへはサンディエゴから車で15分、ロスアンゼルスからは車で3時間だっ
た。
1924年、ティファナで営業していたレストラン「シーザーズ・プレイス」のオーナー、
イタリア系移民のシーザー・カルディーニ、彼がシーザーサラダを作った男だった。
『・・・・・どういうことだ?』
その本にはページ半分の大きさのシーザー・カルディーニの写真が載っていた。
『おい。いったいどうなってるんだ・・・?』
5杯目のバーボンソーダをつくり一口飲んだ。
『本当にこの男がシーザー・カルディーニなのか?
彼がシーザーサラダを作った男なのか・・・?』
写真の中のシーザー・カルディーニは60代後半に見える男だった。ダークなスーツに
ドット柄のネクタイをしている男がフォークを左手に持ち木製のサラダボウルの前に立っ
ていた。
髪はサイドに白髪を残すだけで禿げあがっていた。黒く太い眉と大きな鼻の男は、目と頬
と口で笑顔をつくっていた。
忘れるもんか。
『 Ready to suffer ?(キツいぜ…覚悟はできてるか?)』
そう僕の夢の中で話しかけてきたあの男が写真の中で笑っていた。あのときと同じ笑顔で。
キリンが立ち去った後でふいに横から現れた男はシーザー・カルディーニだった。
キリンとシーザー・カルディーニが現れた夢をみてから僕の不眠症は始まった。
机の上に開いたままの睡眠学の本、左のページには表が載っていた。
それは動物の睡眠時間が記入された一覧表だった。
ヒト:6〜10時間
イヌ:10時間
ネコ:12〜13時間
ゾウ:3〜4時間
キリン:30分
僕は右ページの数行を読んで本を机に置いていた。つまり僕は表をみていなかった。
* **
僕は翌日病院へ行った。当然だ。シーザー・カルディーニが夢にでてきたあとに僕の不眠
症が始まった。僕が受診した睡眠診療科の神経内科医…たしか村木という50代の男だっ
た…村木は僕に言った「シーザーサラダに思いを馳せなさい」と。
いったいどういうことなんだ。
綜合病院のエントランスから中央ホールを横切り東棟1階の各科の外来診察室が並ぶ場所
へ歩いて行った。
しかしそこには睡眠診療科は…なかった。
僕はあわてて中央ホールに戻り総合受け付けの女性事務員に訊ねた。
彼女は小さい声だがきっぱりと言った。
「当院には神経内科はありますが、睡眠診療科という科はありません。
パソコンで職員名簿を検索してみましたが村木という医師は…いませんね」
僕はポケットから診察カードを出して彼女に渡した。そのカードを彼女はカードリーダで
読み込んだ。パソコンの画面に表示された情報をみて彼女は小さく首をふった。
ひかえめな声で彼女は言った。
「先週の受診記録はありませんね。3年前の整形外科の受診記録ならありますが・・」
睡眠診療科は元々ない…僕は先週どの科も受診していない。
ふう。
なにがおきているんだ?
奇妙なことがおきていることは確かだ。
それなのに僕は…睡眠診療科も僕を担当した医者も存在しないと聞いたとき、こう思った。
「やっぱりね」
やれやれ、どうやら僕は奇妙な物語に足を踏み入れたらしい。と、気づいたからだ。
奇妙な物語なら不思議なことが連続しておきるのだろう・・
そして今後もそれはおきるのだろう。
そのとき僕はまた少し慌てて溜め息まじりに、こう思うのだろう。
「やっぱりね」
* **
その日の夜11時、30分の睡眠が始まった。もちろん突然に。
カウチで横になり本を読んでいたときだったから突然意識がなくなっても問題はない。
当然のこと、突然意識が戻っても問題はない……はずだったのだが。
意識が戻ると、カウチと対面の壁に沿って置いたソファに男が座りウイスキーを飲んでい
た。
「23:00を過ぎたらウイスキーが美味しくなるのはなぜなんだ?」
男は大きな声で僕に話しかけてきた。それは質問にも聞こえるし、独り言にも聞こえた。
上下が白い麻のスーツを身につけた、でっぷりと肥った50代後半の男だった。
スーツ・ジャケットの下に黄色いYシャツを着ていたがネクタイはしていなかった。
髪は無かった。毛根さへ残らないスキンヘッドは、額と頭がシームレスに連続していた。
大きい目と太い鼻に薄い唇がついた顔は丸かった。それは生半可な丸さじゃない、顔の輪
郭ほぼ円形に近かった。それはほぼ破綻のない円だった。
奇妙な顔の男が、奇妙な出かたで僕の部屋に現れた。
僕はもう慌てることなく、溜め息もつかずに思った。
『やっぱりね』
男はウイスキーと大きな球形の氷が入ったグラスをテーブルに置き、キッチンにある冷蔵
庫からメーカーズマークの瓶を取り出した。
「オマエが眠ってる間にバーボンを冷蔵庫の中へ入れておいた。
いいか。バーボンソーダは氷で冷やすんじゃない、冷やしたバーボンで作るんだ。
氷で冷えるのを待っていたらソーダの炭酸が飛んで消えちまう」
「・・・・・」
「それからウイスキーグラスはだめだ。飲み口が広くて炭酸が逃げてしまう。
飲み口の小さいビールタンブラーにするんだ。
そして氷は最後に入れる。氷の上にソーダを注いだら炭酸が反射して飛んでいってしま
う。ほら。オレが作ったバーボンソーダを飲んでみろ」
「・・・・・」
僕は男が作ったバーボンソーダを飲んでみた。
バーボンとソーダの比率が寝起きの僕の身体に相応しい割合だった。
男が言うようにソーダの炭酸はフレッシュネスを損なわれていなかった。
「今まで飲んだバーボンソーダの中では、これがベストだ」
「当然だ」
「それじゃ、こういうことか。あなたはバーボンソーダ作りのプロフェッショナルで、
僕に美味しいバーボンソーダを飲ませるために僕が眠ってる間に家に入ってきたと」
「まさか。本気でいってるのか?」
「まさか!」
「だよな」
「あなたは何者なんだ?」
「オレか…オレは月だ」
ふう。『やっぱりね』と言うのはさすがに今回はためらわれた。
「確かに顔や体型は…満ちている。満月そのものだ。
それに…今夜は十五夜だ。
それじゃあ。あなたは日増しに欠けていくのか…損なわれていくのか?」
「バカ言え。いいか。月の満ち欠けは太陽との位置関係でそう見えるだけだ。
まあオレが月だって信じなくてもいいさ。
なあ。相談相手になってやるよ。1人で考えても解決がつかないときは年寄りに相談し
てみるもんだ」
「45億年分の経験と智恵を持つ年寄りに相談しろとでも……」
「ほう。オレが月だって理解したか」
「僕は理解する前に、大抵のことは受け入れるんだ」
「やっぱりね…と?」
「・・・・・」
「なあ。どうだ。一緒にメキシコへ行ってみようぜ」
「メキシコ…?」
「ティファナのシーザーズ・プレイスへ行ってみようぜ」
「あのシーザーズ・プレイスがまだ営業していることは本で読んだ。
だけどシーザー・カルディーニがシーザーサラダを作ったのは1924年だ。
今行っても彼に会えるわけがない」
「シーザー・カルディーニに会おうぜってオレが言ったか?」
「それじゃ何しにティファナへ行くんだ?」
「決まってる。美味しいシーザーサラダを食べるためさ」
「・・・・・」
「困ったときはくよくよ悩まないで美味いものを食べるにかぎる」
「あなたは相談相手になるために来たと言ったじゃないか?」
「いいか。困ったときは美味いもの食べて、満腹になって…ぐっすり眠ればいい。
朝になったら悩みなんか…」
「眠れない」
「・・・・・」
「僕は眠れないんだ」
「ゲラゲラ。そうだった。まあいいじゃないか。
シーザーズ・プレイスのシーザーサラダを食べにティファナへ行こうぜ」
「・・・・・」
「いいか。シーザーズ・プレイスじゃ料理人が客のテーブルの前でシーザーサラダを作っ
てくれるんだ。
大きな木製ボウルへ、にんにく、オリーブオイル、塩、胡椒、レモン汁、卵黄、
ワインビネガー、ウスターソースを入れてソースを作る。
そこへロメインレタスを入れてソースとからめる。
皿に盛りつけたら、かりかりのガーリッククルトンをのせ、チーズカッターから摺り
おろしたパルメザンチーズをふりかける。最後に半熟玉子をのせる。
大きなロメインレタスをナイフとフォークで切って口に運ぶ。
よく冷えたカリフォルニア・シャブリを飲む…どうだ?」
「・・・・・」
「うん…食べたくないのか?
分かった。オマエはバーボンソーダを飲んでいいぞ」
「いや僕はよく冷えたビールを飲むとしよう」
「じゃあ決まりだな」
「これから…あなたをなんて呼べばいい?名前をおしえてくれ」
「だからオレは月だ。そうだな…月と呼ぶのに抵抗があるならMと呼んでくれ。
オレはオマエをこれからもオマエと呼ぶことにする」
Mはニヤリと笑うと言った。
「How does it feel ?」(どんな気分だ?)
「極度の不眠症と突然やってくる睡眠発作。
夢にでてきたシーザー・カルディーニ。
シーザーサラダを思いなさいと言って消えた睡眠専門医。
僕の家に登場した月男。
やれやれ。
それで僕は今どんな気分かなだって?
まあ奇妙な物語のようではあるけれど…それでも、
ひとりぼっちの帰る家もなくした誰にも知られることのない…
転がる石になった気分じゃないな」
「ゲラゲラ。やっぱりオマエはボブ・ディランが好きだと思ってたんだ。
ひねくれ者だろオマエ、なあ」
「“ライク・ア・ローリング・ストーン”は僕が15才のときに撃たれた曲だ」
僕はMにつられて低い声で笑った。
Mが言った。
「1965年、ボブ・ディランは夢と現実を交換したんだ」
「夢と現実を…交換した…?」
Mは言った。1週間以内にメキシコへ飛べ。オマエはティファナのホテルで待っていろ、
オレがオマエの部屋へ行く。どのホテルでもオレにはすぐに分かる。オレは月だからな。
もちろんメキシコだろうがどこだろうがオレは道に迷うことはない。
「じゃあ今日はこれで帰る」
と言ったMの姿はおぼろに滲み部屋の景色に溶けて…消えた。
消えたMが数秒後にまた現れて言った。
「オマエさあ。キリンの睡眠時間を知ってるか?
たったの30分なんだぜ」
そう言い残してMは消えた。
キリンの睡眠時間は30分…。
『やっぱりね』
* **
見知らぬ町を歩いてる時に突然意識を失うことは避けたい。それでもホテルの部屋にこも
ってばかりいるのはいくらなんでもごめんだ。
シャワーを浴び、白いTシャツとグレーのカーゴパンツに着替え通りに出た。パンツの
ポケットに入れた紙にはホテルの電話番号とスペイン語でこう書かれていた。
『慌てないで。僕は眠っているだけなんだ。ほら。息をしている、脈も強く拍動してい
る。なにより血色が良い。30分すると目覚めるから心配はいらない。
愛を込めて』
ティファナ…時間を1/2世紀ほど遡上し時が停止したような建物の街並みの、アメリカと
の国境にあるメキシコの町。青い空に白い雲が羊の放牧のように群れていた。
通りを歩く外国人も多く特にアメリカ人の多さが目立った。調べてみると、アメリカ側の
国境の町サンイシドロまではサンディエゴから路面電車が出ていた。サンイシドロから国
境ゲートを通過しメキシコのティファナへ入国するには入国審査がない。メキシコはドル
をいつでもウエルカムということだ。ティファナからサンイシドロへ行くときは審査があ
る。アメリカはペソと一緒に持ち込まれる可能性のある物がウエルカムじゃないというこ
とだ。
ティファナの街中には薬局や歯医者が多い。通りすがりのアメリカ人の男は言った。アメ
リカで薬を買ったり治療を受けるより安いのさ。男はニヤリと笑った。多くのアメリカ人
がティファナを歩いてるのも頷けた。
ホテルへ戻り、部屋のベッドに座りテレビでサッカーの試合ををみていた。ふと気づくと
2つのチームがサイド・チェンジをしていた。30分眠ったらしい。物音に振り向くとM
が立っていた。時計をみると午後5時30分。月の登場には相応しい時間だ。赤基調の派
手な半袖開襟シャツと青いデニムのパンツ、黒いサングラスをかけた月は笑って立ってい
た。
レストラン「シーザーズ・プレイス」。
横に長く造られた建物の内部は白黒格子柄の床が長く伸び、白いクロスでおおわれた茶色
の木製テーブルが1列に並んでいた。とても長く。テーブルの列と平行にカウンター席が
あった。とても長いカウンターだ。古いレストランにしては照明が明るかった。サラダを
食べるには好感がもてる照明だ。
Mは予約をとっていた。
「月はそつがないんだ」と言ってククッと笑った。
店の人間に案内され僕とMはテーブル席にについた。
白Yシャツに黒のチョッキとネクタイ、腰から下は白エプロンの男がカートを押して僕
たちのテーブルに現れた。簡単な挨拶をすると男は大きな木製ボウルでシーザーサラダを
作った。そしてサラダを皿に盛りつけると男は去っていった。
僕は大きなロメインレタスをフォクークとナイフを使って切り分け口へ運んだ。
そうか、そういうことか。おろしたにんにくをサラダソースにつかっているのに、男は皿
に盛りつける前におろしにんにくを皿に塗りこんでいた。にんにくの香りが鼻腔を刺激し
軽く興奮した。
「・・・・・」
もう1度ロメインレタスを口へ運び、冷えた白ワインを飲んだ。良い出来のカリフォルニ
アシャブリだった。
「・・・・・」
Mもサラダと白ワインを交互に口へ運んでいた。時おり目をつぶりながら。
「・・・・・」
食べ終えるまで僕とMは一言も言葉を発しなかった。勤勉な機織りのような食事だった。
「・・・・・」
「・・・・・」
僕とMはほぼ同時に食べ終えるとゲラゲラ笑った。
美味しいサラダとワインのおかげで僕たちの脳は無防備に服を脱ぎすて開放されたらしい。
笑いは数分たってもおさまらなかった。
笑いが止むとMが聞いてきた。
「おい。この店のサラダを食べてみてどうだった?」
「素晴らしい。僕のサラダ歴の中ではベスト・オブ・ベストだね」
「そうじゃない。オマエの夢にでてきたシーザー・カルディーニの店でだ…ヤツが考案し
たサラダを食べたんだぞ」
「もちろんオリジナルにも興味はあるけど今食べたサラダは素晴らしかった」
「そうじゃない。今オマエに起きてる奇妙なことの謎に迫る何かを思い出さないのか?」
「ない。何も思い出さないし、何も思い浮かばない」
それからピノ・ノワールの瓶を開けた。チーズと干し葡萄をかじりながらルビー色のワイ
ンを僕たちは飲んだ。
「オマエはどうして奇妙な出来事に出会っても慌てないんだ?」
「じゅうぶん慌てているけど」
「オレにはそうみえない。
オレは毎晩オマエを空から観察していた。
本と音楽とバーボンソーダ。それだけだ。
慌てない、嘆きも怒りもない。
せいぜい溜め息くらいのもんだ。
次の夜も、また次の夜も…本と音楽とバーボンソーダ。それだけだ」
Mは両切りの煙草に火をつけ一息吸うと大きく煙を吐き出した。
「奇妙な出来事もオマエはそのまま受け止めて、あわてない。
やっぱりね…なんて思ってる。そうだろ?」
「僕の祖父はタイのゴム農園で働いていたことがる」
「・・うん?」
「ゴムの反発係数は小さい、石や木や金属と比べるとね」
「何を言ってる?」
「反発係数が限りなく0(ゼロ)に近い非弾性ゴムがある」
「・・・・・」
「衝突したモノを跳ね返さない」
「・・・・・」
「受け入れるんだ」
「じゃあ何か…オマエの心はゴムなみの反発係数で奇妙なことも受け入れるのか?」
「まさか。僕の心はゴムじゃない。
それでも僕は子供のころからあまりにもムチャなことに出会うと…」
「出会うと・・・」
「ああ運命かもしれないと思うところがあった」
「ふん。そんなことだと思ったぜ」
次に太陽がぎっしり詰まったような100%シラーの瓶を開けた。濃赤色のワインの酔いは
さざ波のように寄せてきたけど眠くはならない。月はもちろん眠らない。
「僕の眠りを何者かが持ち去った…あるいは僕の眠りは自律的に立ち去った」
「自律的に立ち去った眠り…不思議なことだ」
「でも僕にとって最も不思議なことは…月とワインを飲みながら話していることだ」
「夢かもしれない」
「まさか」
「だよな。眠れないんじゃ夢はみれない」
「・・・・・」
「自律的に立ち去った眠りか…オマエに失望して立ち去った友人のように」
「・・・・・」
「もしくはオマエが退屈な友人から立ち去ったときのように」
「僕が眠りは自律的に立ち去った…退屈だから、もしくは失望したから?」
***
昨夜Mはこう言い残して消えた。
「マヤの遺跡を訪ねてみろ」
「どうして?」
「旅に必要なものはなんだ?」
「・・・・・」
「ロマンだ!」
Mは赤ワインのタンニンが着色した歯を剥き出してゲラゲラ笑っていた。
朝になると僕は荷物をまとめてティファナのホテルを出た。バスで国境ゲートへ向かい、
入国審査をすませアメリカ側の国境の町サンイシドロへ入った。そこから路面電車に乗り
サンディエゴの街に入るとタクシーをつかまえサンディエゴ国際空港へ向かった。ティフ
ァナからサンディエゴの空港まではわずか24kmだった。
目的地はメキシコ南部ユカタン州のウシュマル遺跡。
サンディエゴ国際空港で運良くエアロメキシコのキャンセルチケットを手に入れ、ユカタ
ン州メリダへ飛んだ。さらに運が良かったのは飛行機に乗り込むまで眠りがやってこなか
ったことだ。しかし、5時間50分の飛行時間の間に消化したかった眠りはメリダ国際空
港に着くまで残念ながらやってこなかった。ここからウシュマルまではレンタカーだ。空
港内で眠りをやり過ごすほかなかった。
僕は空港ロビーのベンチに座り眠りをじっと待った。やがて眠りは訪れ30分後に去って
いった。
オーケイ、23時間30分の1日の始まりだ。
レンタカーに乗り込み国道261号線に入った。ここからウシュマルまで110km、もう目
の前だ。1時間30分後にウシュマルに入り最初に目についたホテルに飛び込みでチェッ
クインした。
ユカタン州ウシュマル、人口2万5千人の町。
ユカタンはマヤ語で「お前の言っていることは解らない」らしい。
やれやれ、わからないことだらけだ。
ウシュマルはマヤ語で「3度にわたり建てられた町」。
時代に押しやられたこの町に4度目はなかった。
荷物を部屋に放り込み、タクシーで「魔法使いのピラミッド」へ向かった。
腕時計の液晶表示は15:30だった。
魔法使いのピラミッド。
魔法使いの老婆が温めた卵から生まれた小人が1夜のうちに創ったという伝説があった。
楕円形の土台に建てられた巨大なピラミッドだ。頂点には神殿を戴いていた。
高さ36m、およそ12階建のマンションと同じ高さだ。
ピラミッド土台の楕円形の幅は高さと同じ36m、長さは73mもあった。
果てなくどこまでも広がる青い空の下、白い石組のピラミッドが緑の草地の上に建ってい
た。
ピラミッド近づいてみると、それは精巧に切り取られた石を組み合わせて造られていた。
斜面全体には凹凸が殆どないように整えられ、楕円形の4つ角は破綻のない見事な曲面を
描いていた。
思わず息をのむそれは、約1200年前のマヤの人々が建てた神話だ。
ピラミッドの斜面しつらえられた118段の階段は、遠くから見るのと違い実際に昇り始
めると気が遠くなるような急傾斜で壁をよじ登るような勾配だった。
夕刻に近づいても太陽は容赦なく照りつけ、僕は汗を拭うのも息を整えるのも面倒くさく
なりただただ黙々と昇った。この階段を昇り始めたことを心底後悔したころに頂上にある
神殿の断片が見えてきた。
神殿にたどり着いたときには陽が傾き始めていた。
そこには予想通りMが立っていた。
Mは瓶ビールを2本持っていて、蓋を開けて待っていた。それはよく冷えたコロナビー
ルで瓶の中にはカットしたライムまで入っていた。
ふう。月のやることは…そつがない。
軽いテイストの冷えたビールを飲みながら180度に広がる地平線を眺めているとMが話
しかけてきた。
「知ってるか…マヤは“時間・周期”という意味だ。つまり彼らは自らを、“時の民”と呼ん
でいたんだ」
「・・・・・」
「金属を持たない石の文明、農耕は単純な焼き畑だ。それなのに高等数学を使い天文学を
操っていたとされる。なんといっても0(ゼロ)の概念を発明したんだからな」
「・・・・・」
「いいか。彼らは20進法を操り1年が350日の暦を作り、9世紀には月や火星や金星の
軌道も計算していたんだぞ」
Mはポケットからメモ帳を取り出すと3つの記号を書いた。
睫毛のない仏像の目のようなもの、丸い点、横棒。
「これは記号じゃない数字だ。
マヤの20進法は、0と1と5で表現する。丸い点が1だ。横棒は5だ。
0から19の20進法で…19はこう表す」
Mは手帳に丸い点を横並びに4つ書き、4つの丸点の下に横棒を3本書いた。
「これが19だ」
「この…目のような記号は?」
「これは0(ゼロ)だ。それにな、これは目じゃない。月だ。
数学の起点のゼロは…月なんだ」
そう言ってMはニヤリと笑った。
「起点は…月?
時の民が操った天文学、それを支えた数学の起点が…月だって?」
Mはそれには答えずゲラゲラ笑った。
夕空には星々の明りがまたたいていた。Mはこうきりだした。
「どうしてマヤの民は星々の運行を観察し暦をつくったんだ?」
「・・・・・」
「どうして自らを“時の民”と呼んだんだ?」
「・・・・・」
「この世界で不変なものは時間だと知っていたんじゃないか。
一定の速度で移動する普遍なものが時間だと気づいていたんじゃないか」
「月の満ち欠け…」
「そうだ。月の満ち欠けはサイン(象徴)じゃない、時間の移動だと気づいたんだ」
「時間の起点は月…月は0(ゼロ)」
「うん。オレもそう思う。月のオレだってそう思う」
Mはゲラゲラと長く笑った。
「なあ。単純に考えないか。
オマエの内部で意識の“時間”がちょっと移動しただけなんだ。眠りから覚醒へ。
オマエの暦が書き換わったんだ」
「・・・・・」
「オマエは眠りが立ち去ったと思ってるけどな…こうは考えられないか。
覚醒した意識の時間がやって来たんだ」
「・・・・・?」
「眠りと覚醒の2進法だ」
「眠りが0で、覚醒が1の2進法。
0と1で書かれた脳のプログラム・コードの中の1が増加した。
そして0は…月」
「そりゃあ、人間が眠るときは月の出番だからな。ゲラゲラ」
「・・・・・」
「眠りは無意識の意識だ。
無意識より覚醒した意識のほうが面白いに決まっている。
なあ。眠りを取り戻すことなんか忘れてしまえ!」
***
成田から自宅に戻りソファに座ると同時に眠りがやってきた。
僕は夢をみた。確信はないがそれはおそらく夢だ。
不眠症になってから初めてみる夢だ。
僕は森を歩いていた。
僕が生まれた町の神社に連なる大きな森だ。
僕が子供の頃に、よく1人で遊んでいた森だ。
でもこれは夢だ。
現実と違い、それは大きく深い森でどこまで歩いても森は終わらなかった。どこまでも。
木洩れ陽の指す方角が東だとみきわめ、一定方向へ向かって歩き続けたが森は尽きなかっ
た。
鳥のさえずりが聞こえる。虫の声も聞こえる。緑に染まった空気が漂っている。
樹木の翳から栗鼠が出てきて立ち止まり僕をじっと見ていた。
歩き疲れた僕は下生えの草の上に寝転んだ。
頬をチクチク刺激する草の感触と匂いが心地よかった。
どれくらい眠っただろう。
目覚めると樹木の間から5年前に亡くなった父親が出てきた。
乱暴で口数が多く(しかも口うるさい)、そのくせ息子思いの父親だった。
僕が油断するとしっぺ返しにあう、取り扱いに注意を要する面倒な父親だった。
そして僕は父親が好きだった。
「おい。こんな所で眠ってるんじゃねえ、ほら、起きろ」
「・・・・・」
「久しぶりに会ったからってな、オマエと話すことなんかオレにはねえ。
ほら、とっとと行け」
そこにMが現れ父親の隣に立った。
「おい月!オマエは余計なことをコイツに言うんじゃねえぞ。
月はなんでも知ってるそうじゃねえか。いいか、コイツに入れ知恵するな!
コイツは自分で考えんなきゃいけないんだ」
Mはゲラゲラ笑い出したが父親は構わず話し続けた。
「おい月!ありがとな。コイツが世話になった。
コイツは森に来なきゃいけなかったんだ。
コイツは森を歩かなきゃいけない。そうしないと何も始まらない」
Mはニヤニヤ笑うだけで何も話さなかった。
「おい眠ってなんかいないで考えろ。
眠ってなんかいないで森を前に進め。
森をただ歩くんじゃない。森をイメージしろ。
目を閉じるな。足を動かせ。森を歩くんだ。考えるんだ。
イメージしろ」
「・・・・・」
「そうすりゃ、オマエはなにかに出会い、なにかを手にする」
「・・・・・」
「おい月!コイツは1人で行かなきゃいけない。オマエもオレも一緒には行けない。
コイツは1人で歩かなきゃいけないんだ。
おい月!オマエはここに残ってオレの話し相手になれ。ギャハハ」
僕はそれからしばらく森の中を歩いた。森をイメージして森を歩いた。
1時間くらい経つと父親は僕の頭の中へ直接話しかけてきた。
父親は森の住人となった今でも話好きなのは変わっていなかった。
『いいか。人間に生まれて面白いことはなんだ?前に向かって歩くことだ。
人間やってて楽しいことはなんだ?考えることだ。
眠れねえなんて上等じゃあねえか。
歩く時間と考える時間が増えたってことだ。
森を前へ進むんだ。そして…考えるんだ
そうすりゃ、オマエはなにかに出会い、なにかを手にする』
遠くに見える木洩れ日の光量が急に大きくなった。
***
翌日僕は本屋へ行き、森に関する本を買ってきた。
森林は、草原など他の植物群落よりはるかに多い動物が住む。地上生物のあらゆる型のも
のが森林には生息する…。と、書いてあった。
森とは…あらゆる形態の生物を保持する世界。
数学では…閉路を持たない無向グラフを「森」という。
なんのことだ?本では鉄道路線図のイラストを使って解説されていたが僕には理解できな
かった。
僕には…その路線図のイラストが枝々を伸ばした木に見える、ということだった。
森なるものは閉路をもたない無向なもの…そして、あらゆる形態の生物を保持する。
よくは分からないが、それはもう構わないと思った。
僕は森へ行こうと思った。森なるものへ向かおうと思った。
あらゆる形態の生物が生息する世界をイメージした。
閉じないフィールドをイメージした。
***
この数週間のうちに僕が巡り逢った奇妙なことを思った。
夢に現れたキリンとシーザーサラダを作った男。
自律的に立ち去った僕の眠り。
シーザーサラダを語る睡眠専門医。
本の写真で見たシーザーサラダを作った男。
消えた睡眠診療科と睡眠専門医。
部屋に現れた、月だと名乗る男。
そして。マヤ文明が編み出した数学の起点の0(ゼロ)は月。
「始まりは月。
全ては君の手配したことなんだね」
目の前のソファの上にMが現れ座っていた。
「・・そう。全てはオレの仕業だ。月のやることには…そつがない」
「やっぱりね」
「分かってたんだろ?」
「うん。
たくさんの不思議なことも大抵の場合は1本の紐でつながるのが世界だ」
「そしてオマエはこれから森を歩く」
「うん。そうすると思う」
「それは良かった」
「どうしてMは僕を選んだのかな?」
「選んじゃいない。」
「Mはいったいどこへ僕を導くつもりだ?」
「オレはオマエを選んじゃいないし、どこへも導かない。
これはオマエが望んだことだ」
「僕が望んだこと…?」
「気づいていなかっただけだ。
オレがやったことは…気づきをオマエに投げかけただけだ」
「気づき・・・」
「そう。気づきだ。
オマエはあるフレーズのある楽器の音を望んでいた。
オレはピアノの録音ファイルの音圧を少し上げた」
「僕は多くの楽器が奏でる演奏の音からピアノの音に気づく。
そしてそれを僕は望んでいた」
「そうだ」
「人は誰だって望んだようにしか生きられない」
「望むままにに生きられる人は少ないと思う」
「簡単なことだけど実行する人間は少ない」
「・・・・・」
「誰にだって望む夢がある」
「夢に蓋をする現実もたっぷりある」
「簡単なことだ。
夢と現実を交換するんだ」
「夢と現実を交換する・・・?」
「夢をみて生きる。現実をみるのは眠ってる時だけ。
覚醒した意識でリアルに夢を生きるんだ」
「そして僕は森を歩く」
「そうだ」
「木々と樹液の匂い、下草と苔の香り、森に住む生物たちの音、木洩れ日がつくる日溜ま
りの温かさ…その中を歩く」
「森はオマエにとってときにイノセントな存在じゃないかもしれない。
むしろ狡猾な黒い森となってオマエを搦め取ろうとするかもしれない」
「もしくは森が内包する混沌に僕は対応できずに煩悶するかもしれない」
「混沌に出会ったら少し調整すればいい。
ピアノ調律師が弦の張りを調整して音の混沌から光りをみつけるように」
「そんなこと…できっこない」
「はっはっは…」
「それでも僕は森を歩く」
「そうだ。立ちどまっているわけにはいかない。
オマエは森を歩き…なにかに出会い、なにかを手にするんだ」
「僕は森でなにかに出会い、なにかを手にする…それが僕のレシピだ」
「もしくは…なににも出会わず、なにも手にしないかもしれない」
「森の美女には出会えず、森の賢者の智恵を手にすることができなくても…
月に出会い、月の智恵を手にするかもしれない」
「ゲラゲラ。悪くない…そいつは悪くない出会いだ」
「オーケイ。僕は森を歩くことにする」
「あるいは森なるものの中を。
オマエにとっての森性なるものの中へわけいることになる」
「僕にとっての森性なるもの……」
* **
3日間かけて森なるものをイメージしてみた。
それでもイメージは玄関ドアをノックしないし、バスルームの窓から入ってくることもな
かった。
それでも歩くことにした。歩いていれば、そのうち僕が分け入る森に出会うことになって
いるのだろう。きっと。
少なくとも立ち止まっていては森に出会うことはできない。
キッチンの物音へ目をやると、そこにMが立っていた。
「何をしている?」
「バーボンソーダを作ってる」
「僕にも作ってくれ」
「分かった。
それで…どこに行くことにした?」
「明日、ハノイへ向かうことにした」
「どうしてベトナムなんだ…」
「どうしてだろ…?そんな気分なんだ…としか言えない」
「ゲラゲラ。うん。そいつは悪くない。気分にまかせるのは悪くない」
「それに…」
「それに…?」
「ベトナム料理は美味しいし、ビールも僕の好みだ」
「うんうん。オマエが美味い料理とビールに惹かれる土地なら…
そこにはオマエが行かなきゃならない森があるんだろう」
Mはバーボンソーダを2つ作って持って来た。
「1つ質問に答えてくれ。どうして僕の眠りは予期せず突然やってくるんだ?
森を探す旅に向かうのにこの眠りはやっかいだ」
Mはゲラゲラ笑いながら答えた。
「そいつは脳のオーバーフローだ。それで脳が突然シャット・ダウンする」
「コンピュータの強制終了みたいに?」
「そうだ」
「どうして?」
「人間の脳の休息には30分は短すぎたからだ。
月だってときにはミスをおかす。ゲラゲラ。
心配するな。90分に調整しておいた。ダ・ヴィンチなみの充分な睡眠だ。
明日からは不意打ちの眠りが襲ってくることはない」
2人ともバーボンソーダを飲み終えるとMはこうきりだした。
「オマエはもう気づいていると思うが…今日でお別れだ」
「うん。そうだと思った」
「オマエが1人で歩き続ける気になったならオレの出番はない」
「うん。君が歩く気にしてくれた。ありがとう。
月のやることは、そつがない」
「ゲラゲラ。そうだ。月のやることは、ぬかりがない!」
笑いながらMの姿はおぼろに滲み部屋の景色に溶けて…消えた。
部屋の壁に嵌め込んだ飾り棚の上のラジオから突然音が流れてきた。
ラジオ局をチューニングする音が数秒鳴った。
突然…イントロなしのジョン・レノンのシャウトが大音量で始まった。
やっぱりね。
ふふっ。月のやることには…そつがない。
ミスター・ムーンライト
あの夏の夜に君は僕の目の前にあらわれた
君のやさしい光りが僕を夢心地にしてくれた
君は世界中から探して彼女を僕へ届けてくれた
君は空の上から僕と彼女に愛を届けてくれた
そして今、彼女はぼくのもの
ねえミスター、君は素敵な月明かりだね
ねえミスター、僕も彼女も君が大好きなんだ
The Beatles “ Mr. Moonlight “
前の10件 | -



